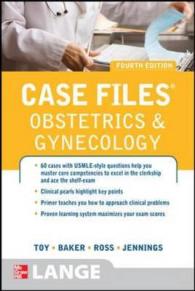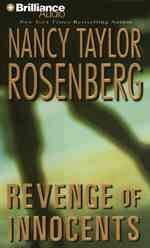内容説明
IT(情報技術)革命とグローバリゼーションで、世界経済システムは大きく変容した。1995年を境に、もう戦後経済の常識は通用しない。詳細な経済データと巨視的な歴史分析によってグローバリゼーションの意味を問い直す。各誌紙絶賛のロングセラーを文庫化。
目次
第1章 覆される戦後経済の常識―分水嶺となった一九九五年(日本のデフレーター、史上最長のマイナスに―デフレだと景気は回復しないのか;ルービンの「強いドルは国益」は米国の「金融帝国」化宣言―経常赤字の増加は成長の制約になるのか ほか)
第2章 重層的に二極化する世界経済―再来する帝国の時代(テイクオフの条件が整うBRICs―日本は再近代化で危機を乗り切れるか;世界経済の二極化―先進国vs.BRICs ほか)
第3章 長期循環の「超」長期化と短期循環の「超」短期化―不安定さ増す世界経済(密接不可分の関係にあるグローバル化と米国の「帝国」化;長期循環を「超」長期化させるグローバリゼーション ほか)
第4章 「大きな物語」の終わりと「バブルの物語」の始まり―ストックがフローを振り回す時代(軍需・公共投資主導経済の終わり―インフレの時代の終焉;資産価格激変の時代の始まり―金融経済が実物経済を振り回す時代 ほか)
第5章 資本の反革命における二つの選択―成長か定常状態か(誰のための、なんのための景気回復か―成長は政策目標となりえるのか;格差拡大と中流階級の没落―グローバル化の本当の脅威は雇用ではなく賃金 ほか)
著者等紹介
水野和夫[ミズノカズオ]
日本大学国際関係学部教授。1953年愛知県生まれ。77年早稲田大学政治経済学部卒業。80年同大学大学院経済学研究科修士課程修了。同年八千代証券(国際証券、三菱証券を経て現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社。98年金融市場調査部長、99年チーフエコノミスト、2000年執行役員、02年理事・リサーチ本部チーフエコノミスト、05年より三菱UFJ証券チーフエコノミスト。10年退社。10年‐12年、内閣官房内閣審議官などを経て、13年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Francis
壱萬参仟縁
AM
アトム
Noboru Matsuda