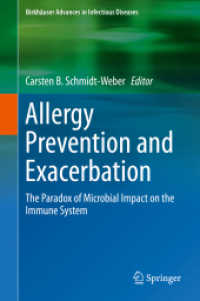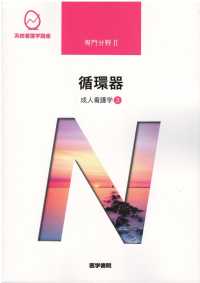内容説明
グローバル化する経済社会において欠かせないキーワードになっているが、日本人に最も欠けているセンスが「インテリジェンス」だ!本書は、その歴史と発想法を、国内外の名著から読み解く日本初のインテリジェンス・ガイド。
目次
第1部 インテリジェンス研究の古典(情報分析の礎を築く―S・ケント『アメリカの世界政策のための戦略インテリジェンス』;情報史研究の金字塔―H・ヒンズリー他『第二次世界大戦におけるイギリスのインテリジェンス』 ほか)
第2部 インテリジェンスを学ぶためのテキスト(インテリジェンスを学ぶ最初の一冊―M・ローウェンソル『インテリジェンス秘密から政策へ』;インテリジェンス運営の「秘訣」とは―M・ハーマン『平和と戦争におけるインテリジェンス・パワー』)
第3部 戦争とインテリジェンス(クラウゼヴィッツ主義者の情報論―M・ハンデル『戦争、戦略とインテリジェンス』;連合軍の対日インテリジェンス―R・J・オルドリッチ『日・米・英「諜報機関」の太平洋戦争』 ほか)
第4部 冷戦―東西対立とインテリジェンス(冷戦におけるインテリジェンスの役割―L・フリードマン『アメリカのインテリジェンスとソ連の戦略的脅威』;インテリジェンスは誤った政策を救えるか―P・クラドック『汝の敵を知れ合同情報委員会は世界をどう見たか』 ほか)
第5部 秘密情報部の足跡(対外情報機関の栄光と挫折―P・ベルネール『フランス秘密情報機関ファンビル部長の華麗な冒険』;スパイの歴史としての二〇世紀―J・T・リチェルソン『トップシークレット20世紀を動かしたスパイ100年正史』 ほか)
著者等紹介
小谷賢[コタニケン]
防衛省防衛研究所戦史部教官。1973年京都府生まれ。立命館大学国際関係学部卒業後、ロンドン大学キングス・カレッジ大学院修士課程修了。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。2004年から現職。専門はイギリス政治外交史、インテリジェンス研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Humbaba
さきん
おっくー
しろくまZ
guranobi