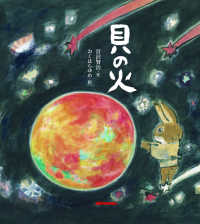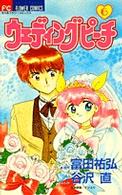出版社内容情報
国境が薄れ「新しい中世」へ向かう先進諸国、なお国民国家たらんとする中進国、存亡の危機にあるアフリカなど貧しい国々――。冷戦後の世界の枠組を独自の視点で分析したサントリー学芸賞受賞の名著、待望の文庫化。
内容説明
相互依存が進む世界はどこへ向かうのか。ヨーロッパ中世になぞらえた「新しい中世」の概念で、冷戦後の世界システムを構想。世界の国々を、国境が薄れた「新中世圏」、国民国家たらんとする「近代圏」、秩序が崩壊した「混沌圏」の3つに分類し、移行期の世界を独自の視点で鋭く分析する。
目次
第1章 冷戦とは何であったか
第2章 ポスト冷戦
第3章 アメリカの覇権とは何か
第4章 ポスト覇権
第5章 相互依存が進む世界
第6章 制度化する相互依存
第7章 現在の世界システムは「新しい中世」?
第8章 三つの圏域の相互作用
第9章 アジア・太平洋―「新しい中世」と「近代」の対決
第10章 日本は何をすべきか
文庫版のための補章 九・一一事件後の世界を読む
著者等紹介
田中明彦[タナカアキヒコ]
東京大学東洋文化研究所教授。1954年生まれ。77年東京大学教養学部卒業、81年マサチューセッツ工科大学でPh.D(政治学)取得。84年東京大学教養学部助教授。同大学東洋文化研究所助教授を経て現職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
13
冷戦後、国家外組織が台頭し、相互依存がますます進む社会では、近代国家の影響力が低下した「新しい中世」が訪れようとしている、と論じた本。国際政治学の基礎を踏まえながら話が進んでいくので明快ながら分かりやすいが、今読むとなんとなく惜しい感じ。アジア情勢分析もなかなか的確で、全体におかしなことはほとんど言っていないのだけど、今のウクライナや中東情勢をめぐる混迷をこの枠組みで読み解けるかはわからない。それ以外でもむしろ、新しい中世への移行にたいして近代国家主権が抵抗している気がするのだが2014/07/21
サアベドラ
3
冷戦が終結してアメリカの覇権に陰りが見えるようになると、国家間の相互依存が深まり、さらに国家的枠組みも薄れてきて中世ヨーロッパのような「新しい中世」が到来する・・・という未来予測本。96年に書かれた本で、2012年現在から見ると当たってるのもあればハズレもあったり。中世史を勉強してる人間からすれば、封建制と農奴制とキリスト教を都合よく無視して「ほら!中世に似てる!」とか言われても「はあ、そうですか」としか言えないんですけれども。2012/11/01
Saiid al-Halawi
2
国家間の相互依存が進み、国家以外の行為主体が台頭してくる「新しい中世」。そう考えると、国境によってあらゆる事柄が整然と区分けされていた近代こそが特殊な状況だったのかもしれない。ヘゲモニーの考え方を扱った部分はかなり面白かった。2011/08/10
大菩薩
2
冷戦後の世界秩序について、覇権、多極化とは違った『新しい中世』という未来像を提示する。強い相互依存で結ばれ、もはや戦争が不可能となる日本やアメリカ、EUに代表される第一圏域、国家が強い影響力を保持し続け、必要とあらば戦争にも訴える第二圏域、そして国家の統治が危うくなり混沌に支配される第三圏域というカテゴライズはロバート・クーパーのものと共通する。戦争が不可能になった世界で『智の競争』が起こるというアイディアは面白い。90年代に書かれているが、2010年代の今読むと現在そしてこれからの世界が良く理解できる。2011/02/28
yagian
1
世界を三つの圏域に分類する第八章以降が興味深かった。筆者は「新中世圏」「近代圏」「混沌圏」と命名しているが、もっと単純に「ポスト・モダン」「モダン」「プレ・モダン」と呼んだ方がわかりやすいように思う(この命名だと進化論的な考えと誤解されるのを恐れたのかもしれないけれど)。自由主義的民主主義と市場経済を基本とした「新中世圏」(日本もここに含まれる)が、いかに「近代圏」「混沌圏」に接するべきかは、解答がない問題だし、昨今は「新中世圏」内部からも「近代圏」的な考え方が台頭しているようにも見える。2016/08/01