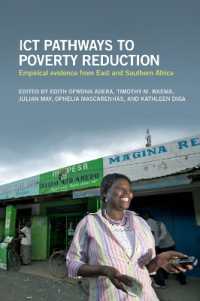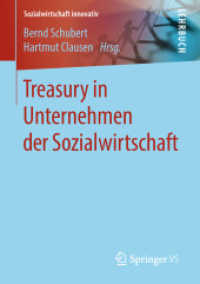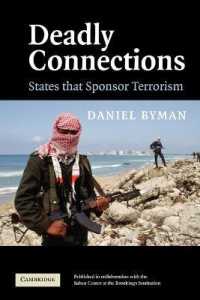内容説明
重大な危機から国をまもるには、時に権力を譲り渡し、沈黙する、という政治決断もある。日本の資本主義の父はなぜ、“生涯の主君”の伝記編纂に心血を注いだのか。
目次
第1章 敗軍の将・徳川慶喜―幕末の前半生
第2章 一橋家家臣・渋沢栄一―“生涯の主君”との出会い
第3章 静岡藩士・渋沢栄一―幕臣から亡国の遺臣に
第4章 敗者が新政府の土台に―渋沢栄一、大蔵省へ
第5章 海舟の功績か、慶喜の深慮か―政権交代の深層
第6章 「朝敵」の汚名を晴らす―徳川慶喜公伝の編纂
終章 敗者として生きた二人の意地
著者等紹介
安藤優一郎[アンドウユウイチロウ]
歴史家。文学博士(早稲田大学)。1965年、千葉県生まれ。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業、早稲田大学文学研究科博士後期課程満期退学。江戸をテーマとする執筆・講演活動を展開。JR東日本大人の休日・ジパング倶楽部「趣味の会」、東京理科大学生涯学習センター、NHK文化センターなど生涯学習講座の講師を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
44
大河ドラマを見ては、幕末から明治にかけての歴史像の再構築を試みる。主人公である渋沢栄一の半生は、当事者としての具体的な動きを追うことで、教科書などより余程分かりやすい。その一つ一つが、当時の歴史に位置づけられ、全体に絡んでくる事が少なくない。本書は、栄一が仕え、後年その詳細な伝記を記すことになる徳川慶喜と栄一本人、彼らの周りに蝟集する人々の動向に焦点を当て、幕末明治の歴史に対するもう一つの見方を提供する。歴史は一筋縄では解き得ないということと、その面白さは細部に宿る、ということを感得させられる一冊である。2021/06/26
kawa
42
幕末、慶喜の側近、維新後は政府の要人・実業家として活躍した渋沢栄一。彼は維新後も長年に渡って慶喜を支えたのだが、その渋沢から見たものとして筆者が慶喜をドキュメント。幕末の慶喜の行動には多くの矛盾があり不可解な点が多いのだが、本書によりその一部の謎が解ける気分も。例えば、慶喜の列挙諸国との破約攘夷の主張は、幕府と有力諸侯の主導権争いの中で天皇の信任を得るための方便という説明にナルホドの感。(コメントへ)2021/07/12
yyrn
27
現在放映中のNHK大河ドラマ『青天を衝け』を文章で追っていくような展開で大変面白く読めた。ドラマだから多少大袈裟に、主人公を引き立てるように脚色されているのだろうなと思いながらテレビは見ていたが、本書から教えられた徳川慶喜と渋沢栄一の、その時々の苦悩と決断、知らなかった二人の強い関係性などはかなり忠実に再現されているようだ。渋沢栄一と言えばどうしても実業家としての功績に目が行くが、そんなに篤い男だったのか!と驚くほどの男気をいたるところで発揮している。だから、徳川側からも薩長の新政府側からも信頼され、⇒2021/07/22
やまとさくら
10
運と能力で前進した渋沢栄一。商業もする農家から武士へ、政治家、実業家で自分の力を発揮する。反面、生まれの定めと時代の流れで 朝敵とされ、謹慎・恭順生活を送った徳川慶喜。東京に転居したのが明治30年。皇居へ参内も/慶喜への世間の誤解をただす為に 生涯をかけて 力を尽くす渋沢栄一が 慶喜の伝記を作成、慶喜の死後完成◎勝海舟の家を 慶喜の息子が継いだ。松平容保の孫娘と慶喜の孫娘が宮家に嫁いだ。2017/01/19
マーボー王子
9
幕末と維新の裏が判る本。大政奉還、江戸無血開城、明治維新、その後の急速な近代化など教科書では書き切れていない事情がよく判る一冊です。渋沢栄一は、日本近代化の父であることがよくわかります。2015/01/10
-

- 和書
- 昏き日輪 文春文庫