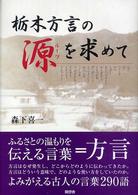出版社内容情報
21世紀の世界を左右するものは何か。世界経済、通貨体制の行方から、日米中の関係、地球環境問題まで、各分野の著名な専門家が展望する。不透明な世界の中で、日本が進むべき道を見通すヒントを提供する。
詳しい目次
序章 21世紀世界の全体像を読み解く ……土志田征一
1 世界政治:大きな平和、小さな戦争
2 世界経済:もろさを秘める繁栄
3 世界の勢力展望:アメリカ・EU・アジア
4 地球的課題:地球人としての知恵
5 21世紀の担い手:国家、企業、NGOと個人
6 日本の戦略
第1部 21世紀世界の形成
1章 国家・企業・NGOの分業によるグローバル・ガバナンス ……山本吉宣
1 一世紀前の構想
2 地球社会の形成
3 グローバリゼーションとグローバル・ガバナンス
4 協調的安全保障の枠組み
5 パワー・トランジション
6 日本の対応
2章 日米中三国の関係を読む ……猪口 孝
1 アメリカは中長期的な衰退を免れないのか
2 中国は民主化するのか
3 日本は最強国と同盟を結ぶだろうか
3章 ユーロの成功に学ぶ世界経済 ……福島清彦
1 ユーロの成功
2 東方への拡大----ドイツの優位の確立
3 統合の深化----政治統合への歩み
4 同心円が重なる多重の構造----統合を支える統治制度
5 市場原理の利口な活用
6 焦点になる国際金融改革
7 地域協力の時代を先取り
4章 地球温暖化問題と文明の転換 ……佐和隆光
1 京都会議の歴史的意義
2 ポスト京都会議の地球温暖化対策
3 80年代半ば以降のCO2排出量の推移
4 地球温暖化対策の経済的影響
5 京都メカニズムとは何か
6 21世紀型文明はメタボリズム文明
第2部 主要プレイヤーの動きを読む
5章 第一人者の地位を維持するアメリカ経済 ……宮本邦男
1 アメリカの世紀となった20世紀
2 第一の課題----バブルコントロール
3 21世紀初頭におけるアメリカの絶対優位
4 21世紀初頭におけるアメリカの相対優位
5 高齢化とその課題
6章 文化多元主義と個人尊重のアメリカ社会 ……松尾弌之
1 大統領のサラダボウル論
2 統計が語る多様性
3 多様性は力である
4 異端分子がつくるルール
5 文化多元主義は活力源
7章 中国のカギはこの十年の改革にあり ……鮫島敬治
1 創業から守成に移った開国近代化
2 家父長絶対制型地方利益集団体質
3 逆流に歯止めをかけた鄧小平憲法
4 党官僚不正腐敗は構造矛盾の核心
5 購買力平価ではすでに世界第二位
6 15~20年周期で二段階発展の試論
7 短絡して暴発すると逆行や混迷へ
8 WTOが問う利益と権利の再配分
8章 IT化で台頭するインド経済 ……島田 卓
1 アメリカに見るインド傾斜の意味
2 注目を浴びるインド・マーケット
3 将来に向けたパートナーシップ構築の重要性
9章 東アジア経済再生の条件 ……木村哲三郎
1 震源地タイでの危機発生
2 東アジア経済危機
3 FDI主導の工業化の問題点
4 21世紀東アジアの課題
10章 グローバル経済の縮図としてのユーロランド ……浜 矩子
1 国際化からグローバル化へ
2 ユーロランドの内なるグローバル化
3 ナショナル・チャンピオンを求めて
4 多様性に基づく繁栄なるか
11章 ソフトパワーとしてのイスラーム世界 ……小杉 泰
1 日本とイスラーム世界
2 イスラームの政教一元論
3 イスラーム復興運動
4 イスラーム銀行の登場
5 ソフトパワーとしてのイスラーム
第3部 21世紀世界の枠組みづくり
12章 21世紀の国際通貨体制 ……行天豊雄
1 変遷を重ねた国際通貨体制----20世紀後半
2 変貌著しい世界経済----世紀末の状況
3 世界経済の三極化----北米・ユーロランド・東アジア
4 ドル本位制が続く----21世紀最初の四半世紀
13章 ブレトン・ウッズ体制の再構築 ……岩田一政
1 BISとWTO
2 IMF改革
3 国際的な最後の貸し手
4 世界銀行改革
5 現実の改革と将来の課題
14章 地域協力としてのアジア通貨機構 ……篠原 興
1 アジア危機の意味するもの
2 AMF構想の経緯
3 日本に負託されていること
15章 企業依存型の労働政策からの脱却 ……島田晴雄
1 変化するメガトレンド
2 個人が生涯職業設計をする時代に
3 求められる労働市場政策
4 総合サービス業で家族機能を支援
5 開かれた移民法の整備を
内容説明
台頭する中国のパワーにどう対応するのか?アメリカ経済、社会の行方をどう見ればよいのか?国家連合の新しい姿を模索するヨーロッパから何を学べるのか?第一級の専門家が新世紀を左右する潮流をとらえ、日本が進むべき道を提言。
目次
二十一世紀世界の全体像を読み解く―地球人が創る多様で一体化する世界
第1部 二十一世紀世界の形成(国家・企業・NGOの分業によるグローバル・ガバナンス―日本は開かれた強靱な中級国家を目指せ;日米中三国の関係を読む―アメリカの覇権と中国の民主化をにらむ日本の同盟関係;ユーロの成功に学ぶ世界経済―市場原理の利口な活用;地球温暖化問題と文明の転換―循環代謝型文明構想へ日本は先導的役割を)
第2部 主要プレイヤーの動きを読む(第一人者の地位を維持するアメリカ経済―バブルコントロールと高齢化による財政再悪化の克服が条件;文化多元主義と個人尊重のアメリカ社会―公平で透明性の高いルールが世界のスタンダードに;中国のカギはこの十年の改革にあり―三十年前と構造変化した国際環境への視点も;IT化で台頭するインド経済―姿を現しはじめた巨大市場 ほか)
第3部 二十一世紀世界の枠組みづくり(二十一世紀の国際通貨体制―揺るがぬアメリカ中心の構造;ブレトン・ウッズ体制の再構築―IMFは危機管理対策に特化せよ;地域協力としてのアジア通貨機構―構想実現へ求められる日本のリーダーシップ;企業依存型の労働政策からの脱却―個人がキャリアを形成する時代に)
著者等紹介
土志田征一[トシダセイイチ]
日本経済研究センター理事・研究参与。1940年神奈川県生まれ。1964年東京大学経済学部卒業。同年経済企画庁入庁。調査局内国調査第一課長、調査局長、総合計画局長、調整局長を経て、1997年日本経済研究センター理事長。2000年10月より現職。著書に『経済成長』(共著、日本経済新聞社、1981年)、『大統領の経済学』(翻訳、日本経済新聞社、1985年)、『レーガノミックス』(中央公論社、1986年)、『自立経済社会の構想』(共編著、日本経済新聞社、1999年)、『どうなる日本のIT革命』(共編著、日本経済新聞社、2000年)、『ネットワーク資本主義』(共編著、日本経済新聞社、2000年)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。