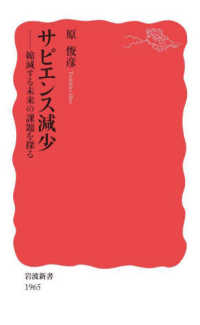出版社内容情報
「先立つもので苦労した戊辰戦争」「対露戦争準備という陰のテーマがあった日清戦争」「財政の持続可能性という面で危機にあった大正期の軍備拡張」――。
出兵をすると経費が発生する、それゆえ議会の承認をえなくてはならない。戦争には輸送費、弾薬費諸々のコストが発生するため事前の見積もりが欠かせない、その上そのコストをどのように調達するかは国家にとって難問だ。また対策は、戦費調達という財政面に止まりません。国内資金の吸い上げ、償還を効率的に進めるインフレ政策など金融政策も対になります。第1次世界大戦時のクレマンソー仏首相が述べたように「戦争は将軍だけに任せておくにはあまりに重大な事業」。戦争はマクロ経済学の視点から分析されるべき対象なのです。
このように戦争と経済は切っても切れない関係であるにも関わらず、日本では正面から分析されては来ませんでした。戦前は机上の空論の統制経済論で終始し、戦後は実証分析を牛耳ったマルクス経済学者が戦争をネガティブな存在とし、経済問題としてとらえることは論外だったのです。同様に戦史研究はアカデミックな世界では戦後長らく等閑視される一方、戦史研究家は経済への関心が薄く、戦争と経済という枠組みでの研究成果はわずかに松方財政、金解禁、高橋財政などの政治史アプローチのものがあるだけでした。
本書は、戊辰戦争から太平洋戦争までの日本が直面した戦争をマクロ経済面から分析する初の書。本書のアプローチは(1)日本の明治・大正・昭和(戦前)を通した戦時経済政策の主軸をインフレ政策にあると捉える、(2)戦争を数字で把握する(戦費、国力(GDP、財政・金融)、動員兵力)、(3)数字で国際比較を行う(明治・大正期の国力の国際比較)というもの。「経済と戦争」という問題設定で日本が経験したすべての戦争を分析する。
内容説明
日本はいかにして戦争経済をマネジメントしたのか。戦争は経済的に見ると、政府による大規模な消費活動である。交戦国は経済活動によって生産した付加価値を戦争遂行に利用する。こうして軍は兵士を養い、弾薬や燃料を消費し、兵器を調達する。本書は、戊辰戦争から太平洋戦争まで日本が直面したすべての戦争をマクロ経済面から分析する初の書。明治・大正・昭和(戦前)を通した戦時経済政策の主軸を通貨金融政策にあると捉え、戦争を数字で把握(戦費、国力、動員兵力)し、国際比較を行う。
目次
序章 近代の戦争と戦費
第1章 日本の戦争経済の座標軸:理論的背景と国際比較
第2章 戊辰戦争:過渡期の戦時通貨金融政策
第3章 西南戦争:不換紙幣による戦費調達
第4章 日清戦争:戦時通貨金融政策の原型
第5章 日露戦争:戦時通貨金融政策の完成形
第6章 第1次世界大戦・シベリア出兵:曲がり角の戦時通貨金融政策
第7章 日華事変・太平洋戦争:戦時通貨金融政策の最終形
終章 戦費の終焉:戦費借入れの戦後処理
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さすらいの雑魚
鯖
俊介
masabi
エジー@中小企業診断士