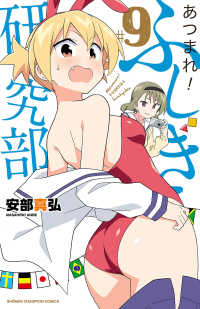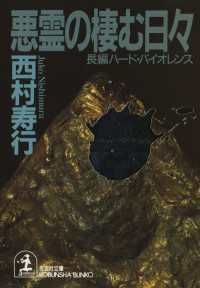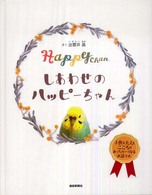出版社内容情報
●日本経済を議論する上での基本書登場
バブル崩壊、デフレ、少子・高齢化などの他の国に先駆けた重い課題、苦悩を背負ってきた日本経済は1990年代以降模索を継続しています。様々な政策も実行してきましたが、低成長・低体温から脱却できてはいないのは何故なのでしょうか。このパズルを解くことが必要です。
本書は、この30年で日本経済のメカニズムがどのように変わり、新しいパターンが生み出されているのかを解明するもの。(マクロ)経済学の発展・最新成果・オリジナルな研究を十分取り入れ、これまでの経済学の理論・実証分析の蓄積を活用し、日本の状況に合った「テーラーメイド」の経済学を意識し、日本のマクロ経済の変化と現状の鳥瞰図を示し、包括的に論じます。
本書の基本アプローチは、経済白書など公開データを活用しながら、理論、歴史(1980年代~)、国際比較の三位一体で日本経済の変質を明らかにするもの。
また本書では、最先端のマクロ経済学を柔軟に活用する。具体的には、各経済主体の行動様式を解明しながら(ミクロ的基礎重視)、それらの主体が相互連関しながら経済全体としてどう動くか(一般均衡視点重視)を考えていきます。マクロ的視点、ミクロ的視点を自在に行き来しながら様々な主体、要因などの連関を考える。
政策提言については、エビデンスに基づいた政策が強調され、エコノミストや経済学者が政策決定プロセスにより関わるようになったにもかかわらず、むしろ、現実にはエビデンスから離れた政策が行われるようになってきているという問題意識で臨みます。平成のマクロ経済政策をそうした視点から批判的に検討し、警告を発します。
日本経済をデータから正面からとらえた本書は、これからの日本経済を語る上での基本書となります。
内容説明
バブル崩壊、デフレ、少子・高齢化などの他の国に先駆けた重い課題、苦悩を背負ってきた日本経済は1990年代以降模索を継続している。様々な政策も実行してきたが、低成長・低体温から脱却できてはいないのは何故なのか。このパズルを解くことが必要だ。本書は、この30年で日本経済のメカニズムがどのように変わり、新しいパターンが生み出されているのかを解明するもの。(マクロ)経済学の発展・最新成果・オリジナルな研究を十分取り入れ、これまでの経済学の理論・実証分析の蓄積を活用し、日本の状況に合った「テーラーメイド」の経済学を意識し、日本のマクロ経済の変化と現状の鳥瞰図を示す。
目次
序章 「課題先進国」としての苦悩とその克服に向けて―本書の立場・スタイル
第1章 鈍化した経済成長
第2章 大きく変化した日本経済の部門間バランス
第3章 変貌する景気循環
第4章 労働市場からのアプローチ―人手不足、賃金、物価をめぐるパズル解明
第5章 企業行動戦略からのアプローチ―物価と設備投資をめぐるパズル解明
第6章 家計の貯蓄率はなぜ低下したのか―消費・貯蓄行動をめぐるパズル解明
第7章 平成の財政・金融政策の機能不全―残された政策課題とは何か
第8章 「低成長・低温経済の自己実現」の打破を目指して
著者等紹介
鶴光太郎[ツルコウタロウ]
慶應義塾大学大学院商学研究科教授。1984年東京大学理学部数学科卒業、2003年オックスフォード大学経済学博士号(D.Phil.)取得。1984年経済企画庁入庁、OECD経済総局エコノミスト、日本銀行金融研究所研究員、経済産業研究所上席研究員などを経て現職。主な著書に『人材覚醒経済』(日本経済新聞出版社、日経・経済図書文化賞受賞)などがある
前田佐恵子[マエダサエコ]
内閣府大臣官房人事課企画官。1999年京都大学経済学部卒業、2003年京都大学経済学修士取得。2000年経済企画庁入庁。連合総研主任研究員、内閣府経済社会総合研究所総務部総務課課長補佐、内閣府政策統括官(経済財務分析担当)付参事官補佐(総括担当)、日本経済研究センター研究本部主任研究員などを経て現職
村田啓子[ムラタケイコ]
首都大学東京経済経営学部教授。1986年東京大学経済学部卒業、99年オックスフォード大学経済学博士(D.Phil.)取得。1986年経済企画庁入庁。OECD経済総局エコノミスト、内閣府経済社会総合研究所上席主任研究官などを経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鳥遊 和
Kooya
しゅー
みみずばれ
se1uch1