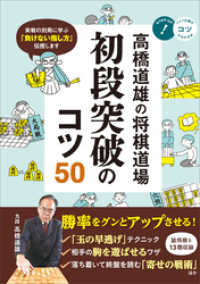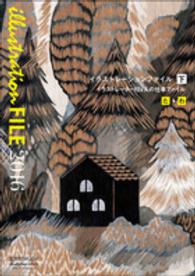出版社内容情報
●技術は発展すれど、便益、意義の議論は不十分。経済学的にアプローチする
モビリティイノベーションの進展はめざましい勢いで進んでいる。CASE(「つながる(connected)」「自動化(autonomous)」「シェアリング(sharing)」「電動化(electric)」)革命という言葉も登場し、「こういうことが実現できる」「こういうことが便利になる」という近未来が(一種、夢物語のように)語られることが多くなった。
一方で、それが世の中に具体的にどのような便益を提供し、意義があるのかを理論化、モデル化した本というのは存在していない。本書は経済学を使ってその答えにアプローチする。
●ゲーム理論やマーケットデザインが制度設計に有効
モビリティ革命の利便性を享受するためには、個人の情報の開示が欠かせない。オープンになったデータが増えるほど、分析力が増し、生活の利便性も大きくなる。一方で、「自分だけは情報を開示したくない」という人もいる。このとき、その人の利得(効用)はどうなるだろうか? この場合は、ナッシュ均衡に代表されるゲーム理論の考え方が有効になる。
また、シェア経済(ライドシェアなど)の進展には、マーケットデザインの考え方が欠かせない。マーケットデザインでは、自分も選ぶが、相手も選ぶことが前提になっている。「誰がどこへ行きたいのか」「誰がどこまで乗せたいのか」のマッチングが重要となる。一方で相乗りとなると対象者が複数になり、最適解も複雑になる。今後、自動運転が実現されれば、運転手がいない相乗りも可能になる。社会的に一番効用が大きいマッチングを導き出すのも、経済学の役割だ。
内容説明
CASE革命による経済的便益を詳細に解説。モニタリングによるスピード違反取り締まりは有効か。複数の人を最適に送り届ける手法。脱炭素、地域社会に貢献する次世代モビリティ。自動車エンジニア×気鋭の経済学者による画期的分析書。
目次
第1章 社会課題解決に貢献する次世代モビリティ(市場とは何か;大衆車の発達と普及(モータリゼーション) ほか)
第2章 モビリティサービス市場(モビリティサービスの定義と特性;シェア(共有)が可能な財の性質 ほか)
第3章 次世代モビリティのモニタリング機能(モニタリングの選択問題)(モニタリング;モニタリング選択問題 ほか)
第4章 モビリティマッチング市場のデザイン(シェアリング市場の分類;一対一の二部マッチング市場の分析 ほか)
第5章 次世代モビリティの市場デザイン論(グリーン社会とデジタル化;社会資本としての次世代モビリティ考 ほか)
著者等紹介
〓原勇[タカハライサム]
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官。1964年生まれ。トヨタ自動車株式会社入社、クラウン・レクサスGSの新型車両のボデー設計ならびに衝突安全の開発を担当。BR‐VI室長、VA開発部長、技術統括部主査を経て2017年筑波大学未来社会工学開発研究センター長、2019年内閣府大臣官房審議官。筑波大学大学院システム情報工学研究科博士後期課程修了、博士(社会工学)。2021年4月より現職。筑波大学特命教授、慶應義塾大学特別招聘教授を兼務
栗野盛光[クリノモリミツ]
慶應義塾大学経済学部教授。同大学マーケットデザイン研究センター長。1973年生まれ。京都大学工学部土木工学科卒業、米国ピッツバーグ大学経済学部博士課程修了(Ph.D.)。予約システムや就活市場などマッチング市場のデザインを研究。マックスブランク経済学研究所研究員、マーストリヒト大学経済学部助教、ベルリン社会科学研究所(WZB)研究員、筑波大学システム情報系社会工学域助教・准教授を経て、2018年4月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koji
Go Extreme
takao