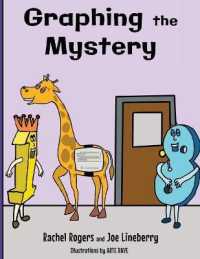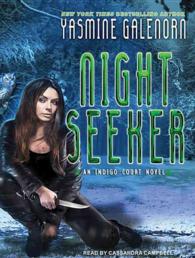出版社内容情報
現代日本人の働き方に関する事実や問題を、個票データを用いた緻密な分析によって幅広く検討した上で、今後の働き方はどうあるべきかを論じる労作。わが国労働市場分析の本格的決定版。
内容説明
「効率的に非効率なことをする」慣習は改まるか?高齢化が進むなか、グローバル競争に勝ち抜くには何が必要か。現代日本人の働き方に関する事実や問題を個票データを用いた緻密な分析によって幅広く検証し、「長時間労働には一定の経済合理性が存在する」「多くの仕事に過度なサービスを要求する非効率が常態化している」「周囲の環境次第で働き方は変えられる」などの知見を導いた労作。
目次
第1部 日本人の働き方(日本人の労働時間はどのように推移してきたか―長期時系列データを用いた労働時間の検証;労働時間規制と正社員の働き方―柔軟な働き方と労働時間の関係;長時間労働と非正規雇用問題―就業時間帯からみた日本人の働き方の変化;日本人は働きすぎか―国際比較や健康問題等からの視点)
第2部 労働時間の決定メカニズム(日本人は働くのが好きなのか―仮想質問による希望労働時間の計測;労働時間は周囲の環境の影響を受けて変わるのか―グローバル企業における欧州転勤者に焦点を当てた分析;長時間労働は日本の企業にとって必要なものか―企業=従業員のマッチデータに基づく労働需要メカニズムの特定)
第3部 日本人の望ましい働き方の方向性(ワーク・ライフ・バランス施策は企業の生産性を高めるか―企業パネルデータを用いたWLB施策の効果測定;ワーク・ライフ・バランス施策に対する賃金プレミアムは存在するか―企業=労働者マッチデータを用いた補償賃金仮説の検証;メンタルヘルスと働き方・企業業績の関係―従業員および企業のパネルデータを用いた検証)
統計データappendix
著者等紹介
山本勲[ヤマモトイサム]
1970年生まれ。93年慶應義塾大学商学部卒業、95年同大学大学院修士課程修了、2003年ブラウン大学経済学部大学院博士課程修了・博士号取得。95~2007年日本銀行(調査統計局、金融研究所などで経済分析に従事)。07年慶應義塾大学准教授を経て、慶應義塾大学商学部教授
黒田祥子[クロダサチコ]
1971年生まれ。94年慶應義塾大学経済学部卒業、99年青山学院大学大学院修士課程修了、2009年慶應義塾大学大学院博士号取得。94~2006年日本銀行(金融研究所で経済分析に従事)。06年一橋大学助教授、09年東京大学准教授、11年早稲田大学准教授を経て、早稲田大学教育・総合科学学術院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
koji
まろにしも
hurosinki
Ryota