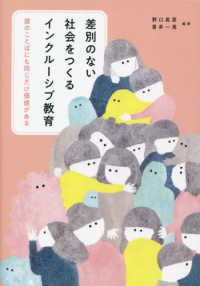内容説明
歴史や構造を解読。真に必要な改革を提示。『ベーシック医療問題』を大幅改訂。医療の特殊性から、日本の医療・介護制度の仕組み、一体改革の課題まで、わかりやすく示す。
目次
第1章 医療問題の構造―特殊性を理解する(医療のどこが特殊なのか;医師の特性;医療における政府の役割―お金の流れで整理する)
第2章 日本の医療―歴史的な背景と構造上の課題(公的医療保険制度;医師と医療機関;診療報酬による制御)
第3章 医療改革の課題―国の対応と筆者の対案(財源をどう確保するか;提供体制をどう再構築するか;成長戦略の課題)
第4章 介護保険の概要と改革の課題(高齢者ケアの課題とその歴史的背景;介護保険制度の仕組み;介護保険の課題;改革に向けて)
著者等紹介
池上直己[イケガミナオキ]
慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授。1949年東京都に生まれる。1975年慶應義塾大学医学部卒業。1981年医学博士。慶應義塾大学総合政策学部教授、ペンシルベニア大学訪問教授を経て現職。医療・病院管理学会理事長、医療経済学会会長、及び中医協の調査専門組織委員や終末期医療に関する意識調査等検討会委員などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
25
知り合いの方のご著書。国税に比べてGDP比増加率が高く、地方税も合算するとかなりの税率になる(NHK受信料も同様)が、制度が複雑で痛税感がごまかされている健保。消費税が今後10年間上がらないとしても、年間で同額とはいわないまでもかなりの値上げが健保と介護で行われることは目に見えています。消費税よりもこちらに関心を向けるべきでは。これが批判に向かわないのは高齢者の医療費を負担しているからですが、このフローは年金の問題と同じということです。後期高齢者の自己負担を1割から上げる議論は目途がついたが遅きに失した。2020/09/30
hurosinki
4
医療に加え介護も検討しているのが特徴的。医療費が診療報酬によってある程度制御できてるのに対し、介護費を抑制する試みはあまり成功していないという(p203)。介護費は医療費よりも高齢化の影響を受けやすいこと、介護費の殆どが建物の減価償却費や人件費で、医療保険のように薬剤費や材料費からコストを引き下げる余地が乏しいことなどが理由(p205)。2021/12/31
パット長月
2
久々の日経文庫。元々ベーシック・シリーズに入っていたとは信じがたいほど凝縮され、かつ充実した内容。コストパフォーマンスは良いが、良すぎていささか消化不良。それにしても、社会保障の関する財政危機を訴える書籍は多々あれど、現状の制度の内容と意味を解説するものは余りない。金も問題は確かに重要だが、現状の制度の良さも知ったうえで財政危機に思いを馳せるというのが、我々一般人の正道だろう。消化不良でお腹を下し気味の読者がいうのは生意気かもしれないが、希少価値を有するすばらしい本だと思う。そういうわけで、いずれ再読を。2014/09/23
cochou
1
慶応大学医学部医療政策・管理学教室教授による日本の医療・介護の現状と課題、処方箋に関する本。「医療の特殊性は、平等性(生命・健康は平等に扱われるべきという考えが強く働く)、不測性(いつ病気にかかるかわからない)にあり、これを踏まえて制度を構築すべき。」という基本スタンスに基づいている。 本書の解説は悪くないと思うのだが、制度自体が余りに複雑で、理解するのが難しい。日本の場合、保険者の数が多すぎて合理的な設計を妨げていることがわかる。 2014/06/30
脳疣沼
1
ものすごく勉強になったが、なんか著者特有の文体のせいか、時折分かりにくくなる箇所がある。日本語がおかしいわけではないので、繰り返し読めば分かるのだけれど。 新書にありがちな、切れ味鋭いけれど、本当にそれで大丈夫か?というような極端な主張はなく、とても勉強になった。2021/11/27
-
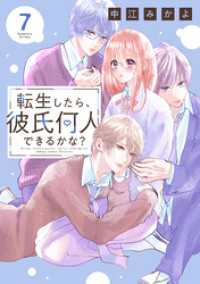
- 電子書籍
- 転生したら、彼氏何人できるかな? 分冊…