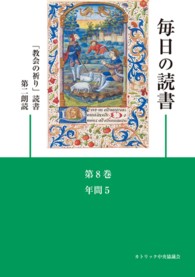内容説明
本書では、経営システムの変遷を、イギリスで興った産業革命、アメリカを舞台とする大企業の時代、日本をはじめとする各国による戦後の大競争時代という3つの時代区分でたどる。それぞれの時代に繁栄した企業が、どのような背景を持ち、いかにして時代に適応したのかを解き明かす。経済の高度化・グローバル化の進展や、行き過ぎた金融資本主義への反省などをふまえ新版化した。
目次
序章 経営史はなぜ必要か
1 戦略商品と経済覇権の変遷
2 会社の誕生―イギリスの産業革命
3 ビッグ・ビジネスの成立―アメリカの第二次産業革命
4 大競争時代―多様化する競争のかたち
終章 ものづくりとファイナンス―大企業、ベンチャーネットワーク、マネー
著者等紹介
安部悦生[アベエツオ]
1949年東京生まれ。東京都立大学経済学部卒、東京大学経済学部中退。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。81~83年フルブライト研究員として、アメリカのボストン大学経営学部留学。89年明治大学経営学部教授。92~93年明治大学在外研究員としてイギリス・ケンブリッジ大学歴史学部留学。97年ロンドン大学(Royal Holloway)にてVisiting Professor。現在、明治大学経営学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
22
(p.140)最初のビッグビジネスとしての鉄道会社が誕生し、続いて鉄鋼、石油、電機、化学、自動車などでビッグビジネスが誕生しました。その主たる推進力は、規模の経済、統合の経済、範囲の経済でした。2020/10/16
Tomoyuki Kumaoka
13
経済活動を規定する商品を戦略商品と定義する。「戦略商品の遷移」をベースに、主にイギリス、アメリカ、日本の経営の歴史を学べる本。ポイントの一つは、取引コスト削減。イギリスは取引所により、アメリカでは大企業となることにより取引コストを削減した。日本は後者に近い。 現在の戦略商品は携帯端末、スマホやタブレットであろう。いかに人々の需要を満たすサービスを生み出せるか。もしくは別の新たな戦略商品を生み出すことができれば、急成長企業となれる。しかし、日本企業は新たなモノを生み出す「異質競争」に弱いと述べられている。2017/02/27
とび
3
ある時代の経済活動を規定するような、あるいはその国を最も反映させるような商品を「戦略商品」と呼ぶ。この本では、そのような戦略商品を軸に、イギリス産業革命、アメリカのビッグビジネス、日本の1980年代、そして現代を経営学的視点から読み解いている。経営史の知識がほとんどない私でも、気軽に読め、かつ経営史の概略が非常によく理解できうる一冊であった。2014/09/20
クレストン
1
明治大学経営学部の教授である著者による経営の歴史的変遷を辿った本。基本的には大まかな時系列に沿った内容となっており、最初は貿易と株式会社をつなぐ「戦略商品」を軸に進み、その次はイギリス・アメリカの企業の変遷を辿り、現在の大競争時代を俯瞰する内容となっている。経営学の授業をよりよく理解しようと思い立ち読了。時系列順・体系的にまとめられているので手軽に俯瞰ができるのが本書の強みだと感じる。内容は細かいので理解するのが難しいが、上手く経営システムの変遷・流れを掴みたいと思った。2019/06/26
Studies
1
面白くなおかつ必須知識であると感じた。2019/06/20