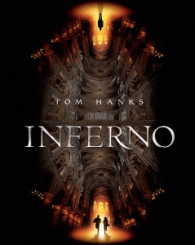内容説明
株主の委託のもとに会社を運営していく取締役は重要な責任と権限を持っています。本書では取締役として知っておくべき知識を網羅しました。2006年施行の会社法によって、株式会社はさまざまな機関設計をすることが可能になりました。それぞれの設計の中で取締役がどんな役割を果たすのかが理解できます。「取締役受難の時代」にあって、取締役はさまざまな訴訟にも対応しなければなりません。関係する法規定を概観し、その方法を考えます。最新の判例も引き、専門用語を避け、ていねいに解説します。
目次
1 取締役とはなにか
2 「株式会社」の仕組みと取締役
3 株式会社 三つのタイプと取締役
4 取締役の資格・任期・選任・解任
5 ボードの決定機能と取締役の義務
6 ボードの監督機能と取締役の注意義務
7 取締役の忠実義務
8 取締役の民事責任と刑事責任
9 株主代表訴訟
10 取締役の報酬
著者等紹介
中島茂[ナカジマシゲル]
1977年東京大学法学部卒業。79年弁護士登録。83年企業経営法務を専門とする「中島経営法律事務所」を設立。現在、中島経営法律事務所代表。弁護士・弁理士。警察庁情報セキュリティビジョン策定委員会委員、日本証券クリアリング機構監査役(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
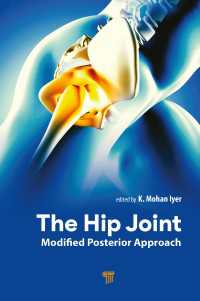
- 洋書電子書籍
-
股関節:修正臀部アプローチ
Th…