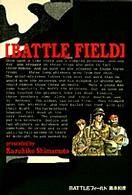内容説明
揺らぐ原油価格の原因はどこにあるのか?各国の対応を紹介しながら、その答えを探ります。特に石油需要の伸びている中国の対応は見逃せません。「資源パラノイア」と化す国の実像に迫ります。さらに、石油に対する誤った認識を排します。枯渇神話、OPEC神話、メジャー神話などについて指摘し、国際石油市場の実態について解説します。最後に、21世紀の石油・エネルギー戦略についてコメントします。日本の果たすべき役割についても触れます。
目次
1 揺らぐ原油価格の真犯人は誰か(ブッシュ政権の舵取りが高値を誘導する;輸入超過に転じた中国 ほか)
2 「資源パラノイア」と化す中国(激増する石油需要の背景;政府主導の石油開発 ほか)
3 「石油神話」を斬る(国際石油市場とは;OPEC、メジャー時代の終焉 ほか)
4 新しいエネルギー戦略を目指して(石油市場はどうなる?;調達手段にポートフォリオを ほか)
著者等紹介
藤和彦[フジカズヒコ]
1960年名古屋市生まれ。84年早稲田大学法学部卒業後、同年通商産業省(現経済産業省)入省。大臣官房、産業政策局、資源エネルギー庁、中小企業庁、石油公団などの勤務を経て、現在、内閣官房内閣参事官
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
James Hayashi
26
当時内閣参事官、2005年著。*気になる日中間の海底油田だが、春暁ガス田、尖閣沖などは台風銀座で大規模で頑丈な設備を必要とする割には鉱床は小規模だという。つまり開発生産コストが高く採算が合わない。*有事にマラッカ海峡封鎖が考えられるので、中国はロシアやミャンマーなどからのパイプラインを考慮。マラッカへの依存率を下げる戦略。*7シスターズやOPECの市場カルテルは過去で、現在は独立系や輸出国の増加によりマーケットで値段が決まっている。*技術革新、コンピューター化、シェールガスの回収で石油枯渇の危機は遠い。→2018/01/07
Kyo-to-read
1
若干古いデータながら、輸送、市場、地域、テクノロジー等石油を取り巻く各要素が簡潔に解説されており、石油に限らず、コモディティを学ぶ上での入門書として、薦められる一冊。2012/07/19