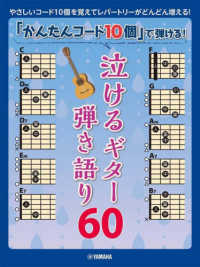内容説明
アメリカ人は年間五〇億個以上のハンバーガーを食べ、一時間に五〇〇〇頭以上の牛が肉にされている。「牛はどうやってハンバーガーになるのか」その現実のすがたを本に書こうと、一人のジャーナリストが自ら子牛を買い、誕生から解体までの現場を追いはじめる。しかしいつの間にか、彼は子牛たちに愛情を覚えてしまっていた…。牛たちにとって、「肉」になる以外の道はあるのか?そして彼の最後の決断とは?読者に「生き物を食べること」とは何かを問いかける、一人の男と二頭の牛たちの「最終目的地」への旅。
目次
第1章 子牛誕生
第2章 ボナンザの精子―蘇る記憶
第3章 肥育と去勢
第4章 フレンドシップ
第5章 放牧
第6章 牛舎の前庭で
第7章 淘汰
第8章 と畜
第9章 選択肢
第10章 決断
著者等紹介
ローベンハイム,ピーター[ローベンハイム,ピーター][Lovenheim,Peter]
『ニューヨーク・タイムズ』『ニューヨーク・マガジン』等で活躍するジャーナリスト。ボストン大学ジャーナリズム学科およびコーネル・ロー・スクール卒業。『民間調停者になるには』など法律関係の著作がある。ニューヨーク州ロチェスター市在住
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Uzundk
5
ここではアメリカでの農業の収入形態や、その取り巻く経済状況が書かれている部分が特に良かった。読んでて思い出すのが荒川さんの「銀の匙」であちらは農業/畜産を行う主体側の視点が強く、こちらは経済の繋がりにそって視点が移るものである。もう一つ特筆すべきは宗教的に反対する人、動物保護団体が出てくるところだろう。結論については私は十分あり得る選択だしそれが取れるアメリカの状況も興味深いと思った。しかし反発を覚える理由として邦題の所為でバイアスがかかっているように思える。その点は残念。2015/09/30
くさてる
4
「牛はどうやってハンバーガーになるのか」というテーマの為に、自分で子牛を購入し、飼育を牧場に依頼して、その牛が精肉されるまでを見届けようとしたジャーナリスト。しかしその成長の過程を見守るうちに…という内容。アメリカの現状が良く分かるし、登場してくる人々も個性豊かで面白い。自分が目をかけた牛を食べることが出来るかどうかという選択がのしかかっているので、当然といえば当然だけど全体にどこか重苦しい雰囲気が常に立ちこめていて、ちょっと読んでいて気づまりだった。そして、最終的な決断には、私もちょっと納得がいかない…2012/07/16
とかげ
3
牛が生まされてから食べられるまでを追ったドキュメンタリ。 個人的には結末が納得いかないが、作者の結論ではあるのだろう。 「いただきます」の語のありがたみというか、私なら迷わず食べる。 動物愛護というなら人間も一動物であるし、植物は生きていないのだろうか?という考え方をしてるので、やっぱりどこか悔しい。 食べる食べないは個人の趣向で済むようになった昨今だが、皿に乗っているものを除けて捨てる人の気がしれないという憤り。2009/09/12
takao
2
ふむ2023/05/11
あとぅーし
1
オチには納得していないが、 肉を食べる人すべてにとって良本だと思う。 自分たちが食べる肉がどのようにして製造されるのか知ることができる。 酪農家さんの大変さを知ることができる。 牛が生まれてから死ぬまで、 いや、生まれる前の精子選び、種付けなど、いかにして作られているかの工程を読むことができる。 去勢の方法なんか知ると、タマキンがすくみ上る思いでした。 当たり前の食卓には様々なドラマがあるのですね。2021/07/23
-
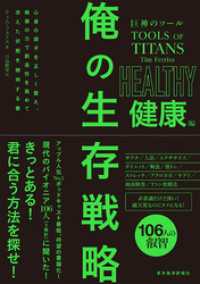
- 電子書籍
- 巨神のツール 俺の生存戦略 健康編
-

- 電子書籍
- めっちゃ召喚された件 THE COMI…