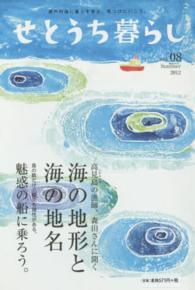出版社内容情報
結晶材料研究分野に関わる学生や企業の技術者を対象に、結晶材料の育成・評価など製造技術に関する基本知識から最新技術までを体系的にまとめた。
目次
第1章 結晶のつくり方(物質の結晶状態;結晶成長法―溶液成長・融液成長を主として)
第2章 溶液成長(溶液成長における結晶成長メカニズム;化学組成に基づくフラックスの分類 ほか)
第3章 融液成長(融液成長における結晶成長メカニズム;CZ法 ほか)
第4章 育成した結晶の評価(結晶構造;電子線キャラクタリゼーション ほか)
著者等紹介
吉川彰[ヨシカワアキラ]
1997年5月、東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻博士課程を中退し、東北大学金属材料研究所助手着任。1999年4月に博士(理学)取得。多元物質科学研究所の准教授を経て、2011年4月より東北大学金属材料研究所・未来科学技術共同研究センター教授(現職)。2012年に東北大学発ベンチャー企業の株式会社C&Aを起業。2021年より大阪大学レーザー科学研究所・委嘱教授を兼務。日本フラックス成長研究会・常任理事。日本結晶成長学会・理事。最近の研究テーマは単結晶および共晶体の液相成長、形状制御結晶成長、シンチレータ・圧電結晶・高温強度材料・難加工性合金などの新規単結晶材料開発およびボディメイク
横田有為[ヨコタユウイ]
2008年3月、東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻博士課程を修了し「不定比酸素量を制御したペロブスカイト型Mn酸化物単結晶の低温物性」のテーマで博士(工学)の学位を取得。その後、2008年4月に東北大学多元物質科学研究所にて助教に着任し、2011年4月から東北大学金属材料研究所の助教、2013年4月から東北大学未来科学技術共同研究センター准教授を経て、2020年5月から現在の東北大学金属材料研究所の准教授として着任し、現在に至る。無機材料科学および結晶化学をもとにした機能性単結晶材料の創製や新たな結晶成長技術の開発を行っている
我田元[ワガタハジメ]
2011年3月、東京工業大学総合理工学研究科物質電子化学専攻を修了し、博士(工学)の学位を取得。2011年4月~2012年3月、日本学術振興会特別研究員(PD)として東京工業大学応用セラミックス研究所およびUniversity of Konstanz(ドイツ)に勤務。2012年4月~2016年3月、助教として信州大学工学部環境機能工学科に勤務。2016年4月より、明治大学理工学部応用化学科に専任講師として着任、現在に至る。研究テーマは水溶液法やフラックス法などによる結晶育成と結晶性薄膜の作製、および新規結晶性材料作製法の開発(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。