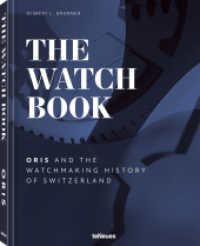出版社内容情報
血圧について、そのもととなる血液の状態から、心臓の動き、血圧のしくみ、血管の状態などを図解で解説する。
目次
第1章 血圧のメカニズムを知ろう!
第2章 血圧は人間の身体を支えている
第3章 血圧を正しく測るのは結構難しい
第4章 血圧と血液はどのように関係しているのか
第5章 血圧をコントロールするには生活習慣病の克服が最優先です
第6章 高血圧で怖い動脈硬化をどう予防するか
著者等紹介
毛利博[モウリヒロシ]
昭和24年10月11日生(67歳)。昭和50年横浜市立大学医学部卒業。昭和50年‐昭和52年聖路加国際病院内科研修医。昭和62年‐平成元年米国サンディエゴ市スクリップス研究所Research Associate。平成元年‐平成12年横浜市立大学医学部第一内科学講座講師。平成12年‐平成15年慶応義塾大学伊勢医学部伊勢慶応病院内科助教授。平成16年‐平成19年藤枝市立総合病院副院長。平成17年‐平成28年北里大学医学部客員教授。平成20年‐平成28年藤枝市立総合病院病院長。平成24年‐藤枝市立病院事業管理者。平成28年‐藤枝市立総合病院名誉院長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どぶねずみ
25
5年ほど前に義母からいただいた血圧計を使ってずっと計測していた。最初は上が110程度で、計測の必要あるのか?とも思っていたのに、段々と日々増え続けて最近は起床時に150を越えることが多くなった。自覚症状は何もないので、義母には感謝しかない。そこで早速、血圧について、何も知らない私は1から学び直すことにした。特に睡眠不足の日は170近かったりするので、睡眠との関係には気づいていたが、他に女性は更年期が近づくと血圧が上がってくるのだと学んだ。今のところそこまで深刻ではなさそうだが、やはり数値は下げておきたい。2023/01/01
Танечка (たーにゃ)
5
これまで血圧をテーマにした本を読んだことがなかったので、初めて知ることが多く、全体的に興味深く読んだ。しかし、本の構成として、あるセクションの内容が別のセクションにもほぼ同じような形で出てきて冗長に思えることが多々あった。また、1文が長くて主語と動詞が適切に対応しておらず意味が分からない箇所があったり、文と文をつなぐ接続詞がなくてロジックが不明だったり、注釈なしで専門用語が使われていたりといった箇所もあり、素人がきちんと読もうとするとなかなか疲れる。2024/02/16
ちゅん
3
血圧について詳しく書いている本。 中医学については突っ込みどころがあったが、血圧の事をわかりやすく書いてくれている本もなかなか無いと思うので、読んで良かったと思う。2021/07/04
みっぴのぱぱ
3
血圧とは何ぞや?その仕組みは?なぜ管理する必要があるのか。どのようにしたらコントロールできるか、できなか。一般的に言われているのが加齢、食事、ストレス、血圧が上がる要因。気を付けよう。2018/06/17
Hiroshi Ono
2
簡易なものであれ医学関係本を読むと貧血を起こしそうなヘタレですが、頑張って読んでみると役立つ情報が論理的に書かれていてとても良い勉強になった。アディポネクチンとかカテコラミンとか専門用語はこの際無視。生活習慣病対策として食生活改善だ適度な運動だと耳にタコができるほど聞こえ来るのだけど、本書によりその根底にある血液、血圧、心臓などとの関連性から紐解くとその重要性が驚くほど腑に落ちる。まずは血圧を測ろうと血圧計もポチった。教えてくれたどぶねずみさん、ありがとう!要再読。 ☆☆☆☆☆2023/01/16