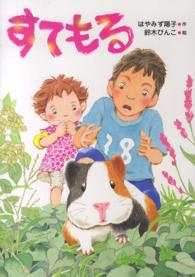目次
第1章 変化した半導体の事業環境
第2章 SOCのビジネスモデル
第3章 ASICとASSP
第4章 SOCとEDAツールの歴史
第5章 SOCの生き残り策
第6章 SOCの設計
第7章 まとめ
著者等紹介
佐野昌[サノショウ]
1953年愛知県生まれ。1977年、東京大学理学部物理学科修士課程修了。1983年、プリンストン大学エレクトリカルエンジニアリングコンピュータサイエンス学科修士課程修了。1977年日立製作所入社。半導体部門にてメモリとマイコンの設計および事業企画に従事。ルネサステクノロジ、半導体理工学研究センター、ルネサスエレクトロニクスを経て、グレイセル・コンサルティングを設立。現在、(株)古賀総研勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 傍白 - 句集