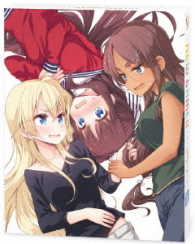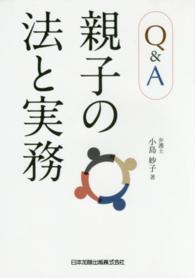内容説明
ものが壊れるのはなぜ?どうすれば壊れなくなるの?身近なエピソードからその謎に迫る。
目次
第1章 力と破壊―ものを壊す力とは?(破壊力―ものを壊す力って何者?;弾性―ばねの性質と反力 ほか)
第2章 ガラスの壊れ方―強化ガラスはなぜ割れにくい(ガラスとは何か―ガラスは液体それとも固体?;ガラスはなぜ割れやすい―力は弱いところを衝く ほか)
第3章 金属は柔らかいから割れない!?―その強さとタフさの秘密(金属とは何か―金属ってホントは柔らかい?;鋼を引張って切る―引張って壊してわかること ほか)
第4章 さまざまな破壊とそれを防止する取組み(低温脆性―タイタニックの悲劇;疲労破壊―金属も疲れるのだ ほか)
著者等紹介
谷村康行[タニムラヤスユキ]
1951年4月山口県生まれ。1976年3月北海道教育大学釧路校卒業。1982年2月(株)ホクハイ入社。1992年4月(学)日本航空専門学校に勤務。1994年~(社)日本非破壊検査協会主催の技術講習会講師指導員。2006年5月(社)日本非破壊検査協会石井賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
更紗蝦
6
「強化ガラスは破片が体にあたっても深い傷を負わないように粒状に割れるようにできている」「携帯ゲーム機のタッチパネルに使われている強化ガラスは、過剰な力で叩くとペンの方が壊れる設計になっている」という話には「なるほど!」と思いました。もしかしたら原発の脆弱性についての記述があるのでは?と予想しながら読んでいたら、132pに美浜原発の蒸気配管事故(2004年に発生)についての説明が少しだけ書かれていました。2014/08/01
ひろし
1
とても優しく材料力学の基礎を解説してくれる本。身近な事例を扱ってくれるのでとてもわかりやすい。最近破壊試験を仕事で扱い始めたので、こういうわかりやすい本はすごくありがたい。残留応力の考え方がイマイチピンと来てなかったんだけど、強化ガラスの説明で理解できた。内側が収縮して表面を引っ張るから、表面は圧縮残留応力が残る。線膨張係数が異なるガラスを貼り合わせたり、表面だけ冷やして密度を高めたり。陶器の貫入はそれが逆ってことよね。表面がバキバキになるんだから、釉薬部分のガラスの方が収縮が大きくて、引張応力がかかる。2018/08/18
あさやん@中四国読メの会参加中
1
破壊しないために、破壊する科学を考える。という、矛盾してるようだけどよく読めば納得できるエピソードが書かれている。 4週間かかったけど、やっと読み終えた。 物理や化学の教科書を読んでるようで、箸の進まない日もあった。 …が、丁寧に書かれていたので、内容は理解しやすかった。2012/06/08
ehanayome
0
淡々とした文体で壊されていく具体例の構造物たちに個人的にときめく本。破壊という行為の定義から破壊のバリエーションまで豊富な内容が良い。2014/10/24
HAL.T
0
☆5つ。物はどうして形を保ってられるのか、どうやって破壊されるのか、をわかりやすく書いた本。これは小学校の高学年ぐらいから中学生に読んで欲しい内容だが、ふりがなが無いのが残念。2012/07/24