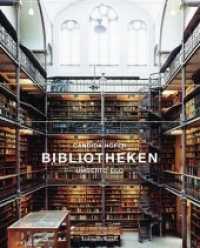出版社内容情報
「力を受けてものが壊れる」あるいは「力を受けているのもかかわらず壊れない」といった領域を扱う学問が破壊工学である。本書では、破壊工学の諸概念をわかりやすく解説するとともに、この学問が破壊事故を防ぐうえで有益なアプローチと知見を持っていることを示す。
目次
第1章 強度と破壊
第2章 力のかかり方と破壊
第3章 き裂と破壊
第4章 部材の中のき裂と破壊靱性試験
第5章 時間経過が伴う破壊
第6章 き裂の検出と計測の技術
第7章 破壊を未然に防ぐ技術
著者等紹介
谷村康行[タニムラヤスユキ]
1951年4月山口県生まれ。1976年3月北海道教育大学釧路校卒業。1982年2月(株)ホクハイ入社。1992年4月(学)日本航空学園千歳校(現日本航空専門学校)に勤務。1994年~(社)日本非破壊検査協会主催の技術講習会講師指導員。2000年4月~航空技術工学科学科長。2006年5月(社)日本非破壊検査協会石井賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まいくん
0
●仕事上勉強の為に読んだ。●破壊は部材が力を受けて分離し、力を伝達できなくなること。破損は形が変わって本来持っていた機能を果たせなくなること。●優れた工具は、壊れる予兆が作業者に伝わるような粘り強い材料で作るべき。確かにパーン!と壊れるよりぐにゃっと壊れるほうが安全だ。●大地震で建物が壊れる時はぐにゃっと曲がれば(塑性変形)瓦礫の中に生存空間が出来る可能性がある。ポキっと折れちゃう(脆性破壊)と建物に押しつぶされて命を落とす可能性がある。私は機械屋なので建築ではそういう考え方をするんだと目から鱗だった。2017/03/29
Azure
0
研究室の配属が破壊力学の分野になったので改めて勉強。1年次のときに買っておきたかった。数式でうやむやに理解していた部分がハッキリした。2017/01/12
TOK
0
破壊力学の導入本。大学生のときは材料力学はどちらかというと苦手だったので導入本なのに理解できないときがあった。ただかなり易しく書かれているので工学系の学生なら最初に読むべき本だと思う。まだシミュレーションはやっていないのでやってみて理解を深めたい。2015/04/27
新規注文
0
破壊工学ではどんな調査をしてどんなことが分かれば安全な設計ができるという最低限のイメージが付く。理論的な式の展開はない(丸暗記:実使用で変数を入れ込む)ので、理論的な理解にはもう少し詳しい本が必要と思われる。2014/08/29
LOWGAKUREKI
0
数式の説明は省略されているが、説明は分かりやすい。2020/07/01
-

- 電子書籍
- 反逆のソウルイーター -魂の捕食者と少…
-

- 電子書籍
- 皇帝の子供を隠す方法【タテヨミ】第57…