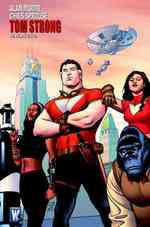出版社内容情報
研磨工程、電着塗装工程、放電加工、溶接工程などにおける微粒子、粉塵微粒子が機械加工品質、および生産性能に与える影響がクローズアップされている。本書では、製造工程における微粒子対策の基礎知識を解説し、実際の製造工程別にその分離、除去技術を紹介する。
目次
第1章 製造現場における微粒子ゴミとは(ようこそ微粒子ゴミの世界へ;微粒子ゴミの特徴;微粒子ゴミと他の微粒子との違い)
第2章 製造工程における微粒子ゴミ混入問題(製造現場が抱える問題;微粒子ゴミを対策することの技術的背景及び時代背景;5S活動との違い)
第3章 微粒子ゴミ対策の基礎技術(微粒子ゴミ対策の分類;洗浄による微粒子ゴミ対策;沈殿とろ過の基礎技術;シーリングの基礎技術;その他の基礎技術)
第4章 微粒子ゴミの計測と分析(微粒子ゴミの計測;微粒子ゴミの分析)
第5章 製造工程別の微粒子ゴミの分離・除去技術(研削加工;金属溶融加工;形彫り放電加工;塗装;表面処理;射出成形加工;食品製造)
著者等紹介
清水伸二[シミズシンジ]
埼玉県出身。1973年上智大学理工学研究科機械工学専攻修士課程修了。1973~1978年(株)大隈鐵工所(現(株)オークマ)にて工作機械の開発設計。1981年上智大学理工学研究科機械工学専攻博士課程修了。工学博士。現在、上智大学理工学部機能創造理工学科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
85
主に製造現場での微粒子ごみの発生の抑止、計測、洗浄などによる除去を整理している。技術士が参画しており、関連機関・企業情報の一覧があるのが嬉しい。公設試験研究機関の掲載もある。分析方法として、光学顕微鏡、SEM, EPMA, XRF, XPS, IR,ラマン分光がある。2.3(1)5S活動の限界という見出しにはわくわくした。http://www.amazon.co.jp/gp/mpd/permalink/m302FKZIMNK6NM/ref=cm_ciu_vr_1820223 に説明動画あり。2013/06/06
まつ
0
クリーンルームの関係で読んで見ましたが、比較的大きなごみ(視認できるサイズ)についてや、機械加工や製造ラインにおいて異物混入に値するような話が多い印象を受けました。しかし、共通項目や各種分析法などの説明も一通りあるので、大きさにかかわらず、タイトルに関係すると思ったら読んでおきたい一冊です。