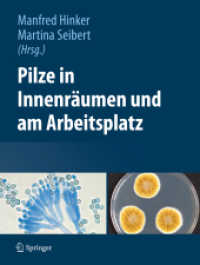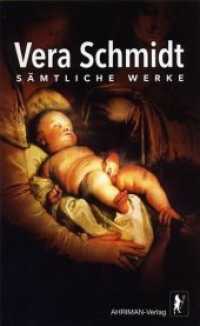内容説明
水や二酸化炭素の温度・圧力を臨界点以上にすると、「濃い気体状の溶媒」と表現される超臨界流体になる。超臨界流体は固体、液体、気体と並んで、物質の第4の姿。水による有機塩素化合物の分解、二酸化炭素による微量成分の抽出分離など、ユニークな応用が展開されている。
目次
第1章 はじめに
第2章 超臨界流体ってどんなもの?
第3章 豊富で無害な機能性溶媒―超臨界水と超臨界二酸化炭素
第4章 こんなところに使われようとしている超臨界流体―研究事例編
第5章 実用化の現状
第6章 超臨界流体でつくる循環型社会
著者等紹介
佐古猛[サコタケシ]
1976年名古屋工業大学大学院工学研究科修士課程修了。1986年工学博士。国立大学法人静岡大学大学院創造科学技術研究部教授
岡島いづみ[オカジマイズミ]
1997年室蘭工業大学工学部応用化学科卒業。2005年静岡大学大学院理工学研究科博士後期課程修了、博士(工学)。現在、国立大学法人静岡大学イノベーション共同研究センター研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふみすむ
0
【まとめ】超臨界流体は液体と気体の両方の特徴をもつ、臨界点を超えた物質の状態。抜群の分解力でダイオキシンやポリ塩化ビフェニルなどのあらゆる有害な有機物を完全に無害化し、バイオマスの効率的な分解・資源化、それまでリサイクル不可能だったプラスチックの迅速な分解・回収さえ可能にする。また、環境に悪影響を与える有機溶媒や化学原料の代替品としての応用も進んでおり、近年新素材として注目されるエアロゲルの製造にも欠かせない。超臨界流体の更なる実用化は21世紀の工業に変革をもたらし、環境問題への多大な貢献が期待できる。2011/09/18