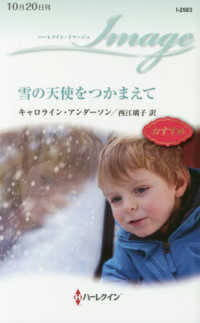出版社内容情報
まえがき
品質保証の国際規格として現在広く産業界において使用されている品質システム規格ISO 9001が,「品質マネジメントの国際規格」と名前も改められて2000年12月15日に2000年版規格として発行された.
改訂におけるポイントは,規格の使用者に対し経営を成功させることができる8つの品質マネジメント原理(1、顧客を重視する組織,2、リーダーシップ,3、従業員の熱意ある参画,4、プロセスアプローチ,5、マネジメントへのシステムアプローチ,6、継続的改善,7、意思決定への事実に基づくアプローチ,8、供給者との互恵関係─第II部表0. 1で詳述)の適用であり,それは組織を指揮し,運営するための広範囲で基本的なルール,もしくは考え方であり,顧客に焦点を当てている.さらに2000年版規格はすべての他の利害関係者のニーズを重視しながら長期に亘って企業業績を継続的に向上させることを目的としている.新規格ではこれらの原理から「顧客満足」という観点での要求事項が加わり,結果として製品品質を向上させて行く狙いを鮮明にして,「継続的改善」の概念を利用しながら品質マネジメントシステムを動かすことの重要性を前面に押し出してきた.
またこれまで大企業や加工・組立業を中心とした製造業を前提とした記述であった部分は,中小企業,サービス産業などあらゆる規模及び業態の組織に適用出来るよう書き改められた.様々な業種・業態に対して適用できる規格というものは,世の中にはそう多くはないが,そのような規格は汎用性がある反面初めて使用するユーザーからは理解し難いものになっている場合が多い.ISO 9001もそうした規格の1つであるが,改訂された2000年版規格においてもその傾向が一層顕著になったとしてその利用者に受けとめられている.
最近の調査によると,品質システムが審査・登録されている会社と事業所は日本国内だけに限っても20、000件を超えた.これらの企業は2003年12月15日までに,旧規格から2000年版規格に移行しなければならないが,従来の旧規格利用者にしてみればそれをどのように取りこみ,現状のシステムにスムースに浸透して行くかは大きな課題となっている.同時にこれから品質マネジメントシステム認証を取得しようとする企業にとっても,要求事項を正しく理解し,その意図するところを正確に把握しながら,企業独自の品質マネジメントシステムをいかに問題なく構築するかは,その企業オーナーや組織の従業員のみならず親会社や下請負業者などその企業と利害を共にする関係者にとっては重大な関心事である.
このようなところから本書は,審査登録される側に効果的な品質マネジメントシステムの構築にむけて,2000年版規格要求事項の正しい理解と正確な解釈を与えることを主題とした.その内容においては要求事項の具体化したイメージがより適格に読者に伝わるよう,審査登録機関側の立場から具体事例を交えて詳しく解説を加えている.特に2000年版規格においてはプロセスアプローチの採用が一つの目玉となっているが,本書では各所に品質マネジメントシステムの要求事項の相互関係を表したプロセスアプローチの構造モデルを図解して挿入している.組織内の業務のプロセスを明確にし,その相互関係を把握するうえで,それらは大きなヒントになるものである.これらの解説はISO 9001の入門書に飽きたらない向きの読者の要求を満たし,また現有するISO 9001マネジメントシステム認証にさらに磨きをかけようとする組織にとっても十分な助けになるものと考えている.
本書は2000年版規格に基いて正しく品質マネジメントシステムを構築する上での手助けになるほか,審査登録機関と被監査側組織との間で規格要求事項の解釈の不一致をなくすことにも役立つものと期待している.
2001年8月1日 著 者
まえがき
本書の内容
第 I 部 ISO 9001:2000年版規格改訂の背景と対応について
1.ISO 9000:2000年版規格改訂の背景とねらい
内容説明
本書は、ISO9001:2000年版に審査登録される側に効果的な品質マネジメントシステムの構築にむけて、2000年版規格要求事項の正しい理解と正確な解釈を与えることを主題とした。その内容は要求事項の具体化したイメージがより適格に読者に伝わるよう、審査登録機関側の立場から具体事例を交えて詳しく解説を加えている。
目次
第1部 ISO9001:2000年版規格改訂の背景と対応について(ISO9000:2000年版規格改訂の背景とねらい;ISO9000ファミリー2000年版規格改訂の特徴;2000年版規格によって期待される効果 ほか)
第2部 規格要求事項の詳細解釈(適用範囲;引用規格;定義 ほか)
第3部 品質マネジメントシステムの構築に向けて(1994年版から2000年版移行への手順;2000年版での新規取得のための手順;ISOに基づくシステム構築および維持のためのチェックポイント)
著者等紹介
伊藤純嗣[イトウジュンジ]
1950年大阪市生まれ。1969年日立造船(株)入社。築港工場、船舶修繕技術監理部門で、舶用エンジン、舶用機械、電気、無線機器検査を担当。1973年日立造船(株)有明工場、造船船舶検査部門で新造船品質保証を担当。1979年同工場陸上機械部門、品質保証部で品質保証システムエンジニア(QAE)ならびに米国非破壊検査協会(ASNT)認定レベル3として、米国機械学会(ASME)規格に基づく品質システム工場認定(ASME‐S/U/U2 Stamp)取得。1985年デット・ノルスケ・ベリタス(DNV)入社、船舶検査、品質システム監査(ISO9000およびQS‐9000)を担当、現在に至る。認証部技術マネージャー、先任検査員、JRCA主任監査員、IRCA Lead Auditor、QS‐9000監査員
須合雄幸[スゴウユウコウ]
1947年秋田県生まれ。1973年日産自動車に入社。中央研究所で新型エンジンの研究開発、設計、試作業務を担当。1983年本社品質保証部で生産車用新型エンジンおよび新型車の開発から量産までの品質保証プロジェクトを担当。その後車両工場で圧造、車体、塗装などの検査部門を担当し生産現場での品質保証活動を行う。1993年本社お客様サービス本部サービス技術課で市場の品質情報の収集、解析、品質向上活動、サービス部門の技術指導、お客様対応支援を行う。1998年1月デット・ノルスケ・ベリタス(DNV)入社、主にISO9000及びQS‐9000の監査を担当、現在に至る。認証部技術コーディネーター。主な資格、JRCA、IRCA、IATCA主任監査員、QS‐9000審査員、CEAR環境審査員補
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
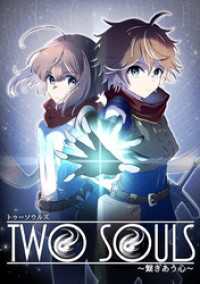
- 電子書籍
- TWO SOULS【タテヨミ】#076…
-

- 和書
- 凸解析と最適化理論