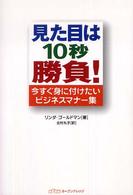- ホーム
- > 和書
- > 工学
- > 経営工学
- > 品質管理(QC等)標準規格(JIS等)
出版社内容情報
私たちは“あたり前”のことを追求する。“あたり前”のことが“あたり前”であるように、実施していく。私たち、リテール業は小口、小売段階のフードサービス業として、“あたり前”のこと、つまり“美味と安全”を通してビジネスを“存続”させる。
私たちの業(なりわい)にはミッションがある。それは人の“生命と健康を守る”ことである。たった一度のミスも、唯一人の不注意も許されない。なぜなら、リテール業には、他の食品業と異なり、是正も回収もできない(すでに胃の中に入いっている)からである。100万食(当社では1年間に相当)のメニュー提供のうち、ただ一度のメニュー失敗で、今までの努力や信頼、そして収益もすべてが泡となり、再起すら覚束ないことになる。
そうならないために、企業の生き残りを賭けて、新しい考え方や仕組みを構築する。特に食品安全という視点で、一人のミスも許されないので、全員が意識を変革し、この厳しい企業環境に適応してゆくため、すべての工程、すべての領域、すべての設備保全など、あらゆることを配慮しつづけねばならない。
そのツールとして、私たちはHACCPという食品衛生の国際規格と、体系的なマネジメント規格であるISO-9001を援用した。これらの規格をそれぞれ個別に使ってシステム(仕組み)を構築するムダを避けたいし、そんな余裕や時間もない。
そこで、この2つの融合システムを考え、そして実践してみた。本書は、その試行錯誤の事例と考え方の軌跡を示した実務論とも言える。
因みにHACCPは“食品安全”に特化したシステムであり、その固有手法は明快でかつ効用が大である。他方、ISOもマネジメントの体系化と体制の強化に効果的である。
にも関わらず、一部の企業では、システムとして機能不全に陥って食品事故を招いたり、形骸化してしまって、マネジメントの向上が見られないという。また、統合システムという言葉のみが、一人歩きして、その内容が伴なわないとの批判も聞く。
そこで、両者の拠って立つところを根本的に考察して、両者の差異を明らかにしつつ、融合に取り組んで私たちの仕組みのツールに供することにした。本書の主な対象は、企業のミドルマネージャー及びある程度ISOに通暁している人と、HACCPに初めて出会う方、さらに官学の諸先輩方、そして食品リテール業に係わる経営者や事務局の人たちである。
本書では、大きく2つの構成に分かれる。前半では、基本的な“考え方”の共通化を図る。具体的に言えば、システムとは何か、マネジメントとは何か、との問いかけを通して、HACCPとISOの差異と共通項目を明かにする。
それによって“マネジメントシステム”とはどういうことかを把握する。これをベースに“融合化”の利点と必要性を認識し、HACCP-9000の位置づけを設定する。
そこで、まず“安全”からスタートして、その食品安全を守るために、リスクとの関係を把握する。アセスメント(または、リスクアセスメント)の重要性を認識して共通項を理解しつつ、食品サービス業の本質的なシステムとマネジメントを考察する内容である。細かく言えばリスクアセスメントやAudit検証も微妙に異なる温度の決め事に到っては、大きな差異がある。それはナゼか。というような“考え方”を明らかにしてこの考察を深める。
後半では、前説設定の展開として具体的なHACCP-9000の融合化を図るべく、“構築”についての手順と考え方を示す。その融合(または統合)の共通モデルを説明し、その他の考え方や進め方もあわせて紹介する。このように構築の実務にも利用できるようにした。この構築の手順は、“Plan―Do―See”というマネジメントの手法に従っている。それぞれの内容、技術項目や言葉の使い方、ひいては当社の試行錯誤事例などをできる限り提示した。併せて、私たち自身で策定したHACCP-9000のガイドラインも一部紹介する。これらを参考にして、食品事業の規模や品種によって、それぞれの考え方や手法を使い分けていただければと思う。
[本稿の構成]
HACCP-9000
構造設定
マネジメントシステム
システム
マネジメント
HACCP
ISO
構築展開
手順P-D-S 要素
導入技術
考え方
融合モデル
ベース
リスク
安全
保証
(解説に当たっては、その該当項目を左記の構成表の示している。)
このようにマネジメントの原点を再認識し、システムの効用を把握しつつ、手作りの融合マネジメントシステム構築を、ISO9004-1(1994年版)ベースで着手した。これは、2000年改訂版ISO-9001の応用も可能にしている。
私たちは、フードサービス業として生き残るために、一人ひとりが“あたり前のことをあたり前にやる”ということ。マネジメントシステムとしては、その状態が“見える”こと。そして、私たちの業(なりわい)が個客一人ひとりを“守る”こと。この3点をキィーコンセプトとして、“HACCPとISO”の融合に挑戦してきた。まだその過程であり、論点の曖昧さや不備もある。意を尽くせぬところも非常に多い。しかし、それを敢えて曝けだす。それは、是非識者のご助言・ご高評を賜って本書を改善し、実践面でも効果を上げたいためである。そして、共に“生き残り”のために役立つことになれば、望外の喜びである。
なお、最後になるが、DNPファシリティーサービスのHACCP-9000研究部会の支援、さらに、当稿掲載を了とされたリコーユ=テクノ社の神戸社長、及び本書の出版に限りない忍耐をもってご助言をいただいた日刊工業新聞社出版局の清水 崇様、ひいては遅筆ゆえの印刷変更をご快諾いただいた大日本印刷㈱の高橋慎一朗氏にも心から謝意を示すものである。
2001年7月31日 編著者 大月弘行
推薦の言葉
まえがき
Ⅰ.基本編
1.HACCP-9000へのアプローチ……1
2.なぜHACCP-9000か……3
2.1 食品・飲料を取り巻く環境……3
2.2 食品の「安全または安全性」について……4
(1) 食品の「安全」/4
(2) 「安全性」とは何か/6
2.3 HACCPと国際標準ISOの共通項……8
(1) 歴史的潮流と“保証”/8
(2) リスクとリスクアセスメント(その1)/10
(3) リスクとリスクアセスメント(その2)/13
2.4 システムのHACCPとマネジメントのISO……19
(1) システム/19
(2) マネジメントとは何か(その1)/28
(3) マネジメントとは何か(その2)/33
(4) マネジメントとシステム/37
(5) MBOと戦略マネジメント/44
2.5 HACCPシステム……63
(1) HACCP原則と手順/63
(2) システムとしてのHACCP/68
(3) 食品(安全)衛生と微生物/72
(4) オーディットの基礎/81
(5) マネジメントとHACCP/85
3.ISOとマネジメント……95
3.1 標準化について……95
3.2 保証とISO 9004……100
3.3 マネジメントサイクルと責任……103
3.4 包括マネジメント……108
Ⅱ.構築編
1.HACCP-9000の構築の基本的な考え方……116
1.1 フードチェーンとハイジーン……116
1.2 構築の順序……122
1.3 統合タイプの分類……126
1.4 構築手法の分類……132
(1) HACCPシステム主体型/132
(2) ISO 9000主体型/132
(3) サイクルプラン型/133
(4) ハイジーンフロー型/133
(5) プログラムステップ型/134
(6) ストーリー型/134
(7) TQ-SHE型/135
1.5 統合のモデル原型……136
1.6 統合モデル図式……139
1.7 食品衛生モデル図……144
2.構築の要素……145
2.1 組織化とメンター制……145
2.2 土台としての5S(6S)……151
2.3 リテール業の事例……163
(1) 対象分野/163
(2) 調理の基本型/168
(3) 食品業態区分/169
2.4 アセスメント……186
(1) アセスメントの分野/186
(2) アセスメントの手順/189
(3) 微生物上のアセスメント表示/192
2.5 HACCPプラン……194
2.6 プロセスコントロール……199
(1) 施設運用側面/201
(2) 取扱い手順/204
2.7 検証・レビュー……209
2.8 衛生意識……215
3.ガイドライン構築……219
3.4 ガイドラインの考え方……219
3.2 統・融合のガイドライン……222
(1) ISO統合例/222
(2) 米国NFS社の統・融合事例/222
(3) 豪州・ニュージランドの統合規格の例/224
(4) SQF 2000統合事例/226
(5) ISO 9004(9004-1)融合事例/226
4.リスクコミュニケーション……232
Ⅲ.導入技術編
1.購買・外注について……239
1.1 購買・外注とは……239
1.2 受入れとは……243
1.3 原材料と受入れについて……249
(1) 見えること/249
(2) 冷凍食品とその受入れ/249
(3) レトルト食品その他/251
1.4 生鮮食材……253
2.運用管理基準と許容限界基準……256
2.1 製造基準……256
2.2 管理線(図)……257
3.温度と時間について……261
3.1 T・Tの重要性……261
3.2 温度……261
3.3 時間……263
3.4 科学的根拠の手順……265
4.微生物検査……272
(1) 一般細菌検査生菌数基準の設定/273
(2) 特定微生物検査基準値の設定/274
参考文献……276
参考資料[1]ISO/HACCP/CODEX関連表……279
[2]食品・飲料の安全・品質ガイドライン……280
索引……290
目次
1 基本編(HACCP‐9000へのアプローチ;なぜHACCP‐9000か;ISOとマネジメント)
2 構築編(HACCP‐9000の構築の基本的な考え方;構築の要素;ガイドライン構築)
3 導入技術編(購買・外注について;運用管理基準と許容限界基準;温度と時間について;微生物検査)
著者等紹介
嶋田茂[シマダシゲル]
1958年麻布獣医科大学卒業。現在、食品衛生コンサルタント(アドバイザー)、獣医師(獣医師免許第2856号)。昭和34年(1959年)東京都衛生局に入庁後、都内各地の保健所や食肉衛生検査所勤務を経て、東京都市場衛生検査所細菌検査室長や東京都動物管理事務所支所長等を歴任。平成8年(1996年)定年により退職。その後、サントリー株式会社品質保証部食品衛生指導センターに顧問として5年間勤務。現在は永年保健衛生に関する監視、指導、助言などの業務に巾広く携わってきた経歴を生かして、食品衛生コンサルタント(アドバイザー)として活躍中
大月弘行[オオツキヒロユキ]
1964年大日本印刷株式会社入社。現在、大日本印刷株式会社理事。株式会社ディー・エヌ・ピー・ファシリティサービス社長。株式会社アドバンスド・アイソ・マネジメント社長。入社以来、営業、企画開発、生産管理、品質管理、本社SS推進部(企画部門)及び技術本部にて、市場競争力開発、業務効率化、ファシリティマネジメント立案戦略、システム統括、ならびに国際標準構築(品質、環境、労働安全)に係わり、1992年より同社のISO認証取得も指揮する。この間、日本能率協会のオフィス革新全国大会審議員、ニューオフィス推進協議会のFM資格検討委員、社会経済生産性本部のEQS検討委員及び環境問題特別委員会委員、食品微生物技術懇話会員などを歴任。IRCA主任審査員、JRCA主任審査員、レイティングシステムIQRS審査員。構築及び支援分野は品質、環境、労働安全衛生、食品衛生、情報安全セキュリティ、品質改善、立地アセスメント、TPMなど。経営の視点から実践と理論の双方に基づく統合マネジメントISOの確立に注力
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
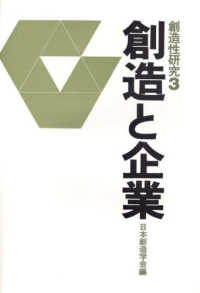
- 和書
- 創造と企業 創造性研究