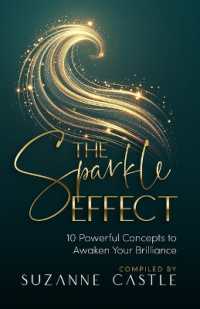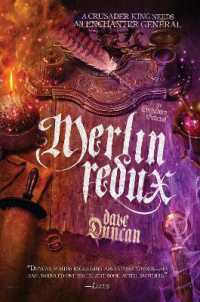出版社内容情報
IT(Information Technology:情報通信技術)革命時代に不可欠なデバイス! それは 超LSI(Very Large Scale Integrated Circuit:略してVLSI,あるいは,半導体集積回路/IC), 液晶ディスプレイ・デバイス(Liquid Crystal Display:略してLCD),そして 電池である。その理由は,ITに用いられる大半の電子機器はLSI/ICによってデータを処理し,得られた結果や中間情報等を表示デバイス(携帯性からみるとLCD等)によって人間に伝え,人間が情報操作等を行うからである。また,電子機器の駆動エネルギーにはポータビリティを考慮すると電池が不可欠なためである。
この入門シリーズは,先に出版した“超LSI工学入門”,“液晶ディスプレイ工学入門”の姉妹書として書かれたものであり,データ処理の基本であるパルス・ディジタル回路を易しくまとめたものである。本書では,パルス・ディジタル回路の基礎事項の説明から始まり,パルス波形操作回路,パルス発生回路,論理回路,同期回路,分周回路,計数回路,および,DA/AD変換器までを図面を多く取り入れて分かり易く解説している。
本書は,普通高校課程卒をはじめとし,機械系卒,化学系卒,物理系卒,および,電気系卒などの高校出身者の方々を対象に,また,これからデータ処理などのハードウェアの開発,あるいは,IT用電子機器の設計開発などの業務に携わる方々を対象に書かれている。さらに 本書は4年制大学における“パルス・ディジタル回路”の教科書として使用できるように工夫して書かれている。つまり,
半期2単位(1.5時間×12回)で「パルス回路」,あるいは,「ディジタル回路」
通期4単位,あるいは,半期4単位(1.5時間×24回)で「パルス・ディジタル回路」
を修得できるように書かれている。
「パルス回路」としては,第1章~第5章,および,第9章を熟読すればパルス回路の基礎的事項が修得できる。また,「ディジタル回路」としては,第1章,および,第5章~第9章を熟読すればディジタル回路全般が修得できるように書かれている。筆者らは,前述2コースを約5年間にわたり大学で教鞭をとっており,その成果としてパルス・ディジタル回路設計関係の技術者を多く社会へ輩出してきた。本書はそれらの経験をもとにして書かれたものであり,この本が社会の発展の一助になれば著者らにとって望外の喜びである。
さて,本書の構成は次のようになっている。第1章は“パルス波とその性質”と題して,パルス・ディジタル回路を学ぶ上で必要不可欠な基礎的事項について述べている。第2章は“線形回路のパルス応答”と題して,RC回路とRLC回路のパルス応答について詳細に解析している。また,応用上重要な分圧回路の動作特性について述べている。第3章は“半導体素子の特性とパルス応答” と題して,パルス・ディジタル回路を構成する上で必要なダイオード,バイポーラトランジスタ,MOS型電界効果トランジスタなどの構造,動作特性,および,等価回路について解説している。また,各素子のパルス応答について解析している。第4章は“パルス波形操作回路”と題して,ダイオードやトランジスタを用いた種々のパルス波形操作回路の構成法と動作特性について説明している。第5章は“マルチバイブレータとパルス発生回路”と題して,矩形波発生回路,トリガー発生回路,フリップフロップ回路,のこぎり波発生回路,正弦波発生回路等について解説している。以上の第1章~第5章まではパルス回路の基本編である。
第6章は“組み合せ論理回路”と題して,ダイオード,バイポーラトランジスタ,MOS-FETによる論理回路,そして,組み合せ論理回路の応用などについて述べている。第7章は“順序論理回路”と題して,フリップフロップの基本であるラッチ回路,遅延式ラッチ回路,1ビット遅延式フリップフロップ回路,シフトレジスタ等について書かれている。第8章は“比較・同期・分周・計数回路”と題して,大小比較回路,位相比較回路,同期回路,分周回路,カウンタ等について解説している。終わりに,第9章は“DA変換,AD変換器”と題して,電子機器に不可欠なディジタル・アナログ変換器,アナログ・ディジタル変換器について書かれている。以上の第5章~第9章まではディジタル回路の基本編であり,ディジタル回路設計技術者にとっては重要な事項が述べらている。なお,各章の執筆分担は次の通りである。
第1章~第4章・・・・吉田正廣, 第5章~第9章・・・・鈴木八十二
本書の執筆にご助言を頂いた東海大学・電子情報学部・高橋宣明学部長,エレクトロニクス学科・和泉富雄主任教授,コミュニケーション工学科・富山薫順主任教授をはじめとする諸先生方,および,東芝マイクロエレクトロニクス(株)・山本哲哉氏,田村岩夫氏,(株)双晶テック・奥野敏雄氏,鈴木悦四氏,UCOMM(株)・亀井武典氏,(株)アイテス・筒井長徳氏,NEC(株)エレクトロンデバイス・青木一道氏,ローム(株)持田博雄氏,金川清氏らに感謝すると共に,出版にご尽力頂いた日刊工業新聞社・出版局・大石龍生氏,清水崇氏,日刊工業出版プロダクション・井口隆子氏,中原大輔氏らをはじめとする関係諸氏に御礼を申し上げる。
最後に,本書を執筆するにあたり各章末に示した多くの著書や文献を参考にさせて頂いた。これら多くの著者の方々に心から感謝する次第である。
2001年4月初旬 著者記す
まえがき
第1章 パルス波とその性質
1.1 いろいろなパルス波 1
(a)ステップ波
(b)単一方形パルス
(c)周期方形パルス
(d)ランプ波
(e)のこぎり波
1.2 実際の方形パルス 5
1.3 パルス波の周波数特性 7
1.4 パルス波形と周波数帯域幅 12
第2章 線形回路のパルス応答
2.1 RC回路 15
2.2 RL回路 24
2.3 RLC回路 26
2.4 分圧回路 30
第3章 半導体素子の特性とパルス応答
3.1 pn接合ダイオード 35
3.1.1 静特性と直流等価回路 35
3.1.2 パルス応答(順方向回復特性,逆方向回復特性) 39
(a)順方向回復特性
(b)逆方向回復特性
3.2 バイポーラトランジスタ 41
3.2.1 静特性 41
(a)しゃ断状態
(b)活性(能動)状態
(c)飽和状態
3.2.2 大振幅等価回路 45
3.2.3 パルス応答(立ち上がり時間,蓄積時間,立ち下がり時間) 48
(a)立ち上がり時間
(b)蓄積時間
(c)立ち下がり時間
3.2.4 スイッチングの高速化 54
3.3 MOS型電界効果トランジスタ(MOS-FET) 56
3.3.1 構造と静特性 56
3.3.2 MOS-FETのパルス応答 59
3.4 その他の半導体素子 63
3.4.1 接合型電界効果トランジスタ(J-FET) 63
3.4.2 ショットキーバリアダイオード 65
3.4.3 サイリスタ 66
第4章 パルス波形操作回路
4.1 演算増幅器 69
4.1.1 反転増幅回路 70
4.1.2 非反転増幅回路 71
4.2 時間軸上での波形操作回路 73
4.2.1 微分回路 73
4.2.2 積分回路 74
4.2.3 サンプリング用ゲート回路 76
(a)ダイオードゲート回路
(b)バイポーラトランジスタゲート回路
(c)トランジスタチョッパ回路
(d)CMOSスイッチ
4.3 振幅軸上での波形操作回路 81
4.3.1 クリップ回路(クリッパ) 81
4.3.2 リミット回路(リミッタ) 82
4.3.3 クランプ回路(クランパ) 83
第5章 マルチバイブレータとパルス発生回路
5.1 非安定マルチバイブレータ(矩形波発生回路) 88
5.1.1 バイポーラトランジスタによる非安定マルチバイブレータ 88
5.1.2 MOSトランジスタによる非安定マルチバイブレータ 90
5.2 単安定マルチバイブレータ(トリガーパルス発生回路) 95
5.2.1 バイポーラトランジスタによる単安定マルチバイブレータ 95
5.2.2 MOSトランジスタによる単安定マルチバイブレータ 97
5.3 双安定マルチバイブレータ 100
5.3.1 バイポーラトランジスタによる双安定マルチバイブレータ 100
5.3.2 集積化に適したバイポーラトランジスタによる双安定マルチバイブレータ 102
5.3.3 MOSトランジスタによる双安定マルチバイブレータ- 103
5.3.4 MOSトランジスタによる双安定マルチバイブレータ- 104
5.4 のこぎり波発生回路 105
5.4.1 CR回路によるのこぎり波発生回路 105
5.4.2 ミラー積分回路 108
5.4.3 ブートストラップ回路 110
5.5 階段波発生回路 112
5.5.1 チャージポンプ回路による階段波発生回路 113
5.5.2 ラダー抵抗とディジタル回路による階段波発生回路 117
5.5.3 正弦波発生回路 123
第6章 組み合せ論理回路
6.1 ダイオードによる論理回路 127
6.1.1 ANDゲート回路 127
6.1.2 ORゲート回路 129
6.2 バイポーラトランジスタによる論理回路 130
6.2.1 インバータ回路 130
6.2.2 ダイオード・トランジスタ論理回路(DTL) 131
6.2.3 トランジスタ・トランジスタ論理回路(TTL) 132
(a)回路しきい電圧VC
(b)出力電圧VO
6.2.4 電流モード型論理回路(CML/ECL) 134
6.3 MOS-FETによる論理回路 136
6.3.1 インバータ回路 137
(a)E/D型MOSインバータ回路
(b)CMOSインバータ回路
6.3.2 NANDゲート回路,NORゲート回路 140
(a)E/D型MOSによるNANDゲート回路
(b)CMOSによるNANDゲート回路
6.3.3 複合ゲート回路 142
6.4 組み合せ論理回路の応用例 144
6.4.1 半加算器,半減算器 144
6.4.2 全加算器,全減算器 146
第7章 順序論理回路
7.1 ラッチ回路 151
7.1.1 非同期式ラッチ回路(別名:フリップフロップ回路) 151
7.1.2 同期式ラッチ回路 153
7.2 遅延式ラッチ回路 155
7.2.1 伝送ゲートを用いた遅延式ラッチ回路 157
7.2.2 NANDゲート・タスキ掛け回路による遅延式ラッチ回路 159
7.2.3 NORゲート・タスキ掛け回路による遅延式ラッチ回路 160
7.3 1ビット遅延式フリップフロップ回路 162
7.3.1 D型フリップフロップ回路 162
7.3.2 J-K型フリップフロップ回路 165
7.4 シフトレジスタ 168
第8章 比較・同期・分周・計数回路
8.1 比較回路 173
8.1.1 電圧振幅比較回路 174
(a)MOS-FETによるシュミットトリガー回路
(b)バイポーラトランジスタによるシュミットトリガー回路
8.1.2 ディジタル比較回路 181
(a)大小比較回路
(b)位相比較回路
8.2 同期回路 185
8.2.1 伝送ゲート,クロックドCMOSインバータによる同期回路 185
8.2.2 非安定マルチバイブレータによる同期回路 186
(a)CMOSを用いた非安定マルチバイブレータによる同期回路
(b)バイポーラトランジスタを用いた非安定マルチバイブレータによる同期回路
8.3 分周回路 190
8.3.1 遅延型フリップフロップ回路を応用したリップルキャリー型分周回路 190
8.3.2 LSIに応用されるダイナミック方式リップルキャリー型分周回路
192
8.3.3 J-K型フリップフロップ回路を応用したリップルキャリー型分周回路 193
8.3.4 タスキ掛け回路を応用したリップルキャリー型分周回路 194
8.4 計数回路(カウンタ) 196
8.4.1 非同期方式リップルキャリー型カウンタ 196
8.4.2 非同期方式リップルキャリー型任意カウンタ 199
(a)非同期方式リップルキャリー型任意ダウンカウンタ
(b)非同期方式リップルキャリー型任意アップカウンタ
(c)非同期方式リップルキャリー型プログラマブルダウンカウンタ
8.4.3 遅延型フリップフロップ回路を用いた同期方式カウンタ 202
8.4.4 シフトカウンタ 205
8.4.5 ポリノミアルカウンタ 211
第9章 DA変換器,AD変換器
9.1 DA変換器 219
(a)荷重抵抗型DA変換器(並列型DA変換器)
(b)分圧抵抗型DA変換器
(c)はしご抵抗型DA変換器
9.2 AD変換器 224
9.2.1 計数方式AD変換器 225
(a)ランプ型AD変換器(一重積分型AD変換器)
(b)二重積分型AD変換器
(c)電圧-周波数方式AD変換器
9.2.2 電圧比較方式AD変換器 232
(a)逐次比較型AD変換器
(b)並列比較型AD変換器
9.3 分解能,量子化誤差,オーバレンジ 236
付録1:ラプラス変換表 242
付録2:ラプラス変換基本公式表 243
付録3:論理用CMOS集積回路(74HCXXXシリーズ)で構成した8ビット二重積分型AD変換器 244
索 引 248
内容説明
本書では、パルス・ディジタル回路の基礎事項の説明から始まり、パルス波形操作回路、パルス発生回路、論理回路、同期回路、分周回路、計算回路、および、DA/AD変換器までを図面を多く取り入れて分かり易く解説している。
目次
第1章 パルス波とその性質
第2章 線形回路のパルス応答
第3章 半導体素子の特性とパルス応答
第4章 パルス波形操作回路
第5章 マルチバイブレータとパルス発生回路
第6章 組み合せ論理回路
第7章 順序論理回路
第8章 比較・同期・分周・計算回路
第9章 DA変換器、AD変換器
著者等紹介
鈴木八十二[スズキヤソジ]
1967年3月東海大学工学部電気工学科通信工学専攻卒業。1967年4月東京芝浦電機株式会社(現、(株)東芝)入社。1982年3月「クロックドCMOS大規模集積回路に関する研究」にて工学博士。1989年7月(株)東芝より特別社長賞を受賞―CMOSの東芝への道、クロックドCMOS開発と事業化―。1990年10月液晶事業部へ転勤(姫路工場駐在)、液晶担当副技師長として液晶ディスプレイ製品の開発と量産等の全体フォロ。1995年3月(株)東芝退職。1995年4月東海大学工学部通信工学科教授就任。1998年4月東海大学工学部通信工学科副主任教授。2001年4月東海大学電子情報学部エレクトロニクス学科教授。PCSフォーラム部品・材料分科会会長(SEMIジャパン主催)、ADY選考委員(リードエグジビションジャパン主催)、SID会員、IEEE会員、電子情報通信学会会員
吉田正広[ヨシダマサヒロ]
1976年3月東海大学第二工学部電気工学科通信工学専攻卒業。1978年3月東海大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了。1978年4月東海大学工学部通信工学科助手。1984年4月東海大学工学部通信工学科講師。1990年4月東海大学工学部通信工学科助教授。1990年9月「CMOS連想メモリセルに関する研究」で工学博士の学位を取得。1990年9月東海大学工学部通信工学科教授。2001年4月東海大学電子情報学部コミュニケーション工学科教授。電子情報通信学会会員、日本ファジイ学会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。