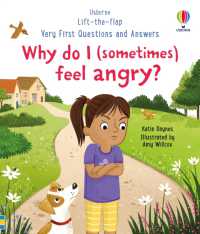出版社内容情報
《内容》 第14改正日本薬局方による改訂.局方に準拠し,確認試験法,定量法,成分含量の修正を行った.併せて今改訂では,局方にいう基原植物の範囲を明確に示し,局方外のものは脚注として基原に含まれない理由を解説.新しい生薬の研究法や漢方医学についても稿を改めた.
《目次》
【内容目次】
総論
I.生薬
1.生薬学
2.生薬学の課題
1)生薬の価値の再認識
2)医薬としての天然物のさらに広い研究と開発
3)中国の医・薬学(漢方医薬学)と各種方剤の研究
3.生薬の記載事項と研究法
1)本草学的考証
2)フィールドワーク
3)栽培・飼育・育種の研究
4)形態学的研究
5)含有成分の化学的研究,天然物化学
6)品質評価に関する研究
7)生薬製剤と剤形の研究
8)薬理学的研究
9)バイオテクノロジーを利用した新しい生薬研究
4.医薬としての生薬の特性
1)長所
2)欠点
5.生薬の調製
1)生産加工
2)切断,破砕および粉砕
3)保存
4)修治・炮製
付.日本薬局方生薬総則
6.生薬の製剤
1)エキス剤
2)流エキス剤
3)浸剤・煎剤
4)チンキ剤
7.生薬の品質評価法
1)基原の真偽に関する方法
2)生薬の良否を評価する方法
8.生薬の生産と取引
1)生産
2)生薬の流通と取引
II.生薬学小史
1.西洋の生薬学
2.メソポタミアの生薬学
3.インドの生薬学
4.中国の本草学
5.日本の本草学
III.漢方医学
1.漢方医学の流れ
1)“傷しょう寒かん論ろん”と“金きん匱き要ょう略りゃく”
2)大たい平へい恵けい民みん和わ剤ざい局きょく方ほう
3)金元医学
4)日本後世派
5)中医学
2.処方解析
3.用語解説
各論
1.皮類
2.材,茎および枝類
3.根類
4.根 茎 類
5.葉類
6.花類
7.果 実 類
8.種 子 類
9.草類
10.菌類・藻類
11.分泌物・細胞内容物
A.炭水化物
B.精 油 類
C.樹 脂 類2
D.エキス類,乳液類,植物滲出物
E.植物性油脂およびろう
12.動物生薬231
動物性油脂242
13.鉱物生薬246
付録
漢方の実用処方
索引
内容説明
日本薬局方では、平成10年の第十三改正第一追補、平成12年の第二追補および、平成14年の第十四改正版を経て、基原植物の定義が現実に合うよう改訂され、確認試験など、試験法も大きく変更された。本書も今回これに対応して、基原植物に関するあいまいな表現を廃し、現実に合ったものを明確に示すよう努力した。現在は使われなくなっていても歴史的には使われていたもの、日本薬局方の表現に学問的な問題を残しているものなどは、脚注あるいは類似生薬として紹介してある。
目次
総論(生薬;生薬学小史;漢方医学)
各論(皮類;材、茎および枝類;根類;根茎類 ほか)
付録 漢方の実用処方
著者等紹介
野呂征男[ノロユキオ]
名城大学名誉教授
荻原幸夫[オギハラユキオ]
名城大学薬学部教授、名古屋市立大学名誉教授
木村孟淳[キムラタケアツ]
第一薬科大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。