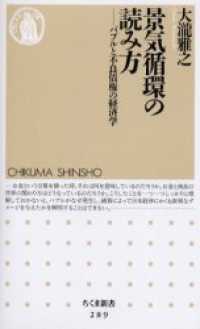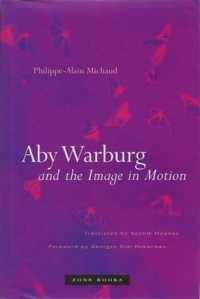出版社内容情報
《内容》 小児看護では,子どもと家族の全体像をとらえた上での臨床判断と,子どもにかかわる際の優れた技が要求される.本書は,看護師が実際に子どもと家族にかかわっている場面の観察,そして子ども・家族・看護師との面接を通して得られた研究結果から,多くの看護師が日々実践している優れた技を抽出している.また,本書にみられる子どもや家族の深い悩みや熱い思いは,看護実践への多くの示唆を与えている.
《目次》
【主要目次】
1.いま,小児看護に求められていること
2.外来を受診する子どもと家族へのかかわり
A.救急外来を訪れる子どもと家族へのかかわり
B.子育て支援
C.虐待の疑いのある子ども,不登校の子どもへのかかわり
D.障害をもつ子どもと家族へのかかわり
3.検査や処置に取り組む子どもへのかかわり
A.痛みを伴う処置に取り組む子どもへのかかわり
B.注射に取り組む学童へのかかわり
C.思春期の子どもにとっての検査結果の意味とかかわり
4.入院している子どもへのかかわり
A.入院している子どもどうしのかかわり
B.他児の退院を何度も体験する幼児へのかかわり
C.術後に体動制限されている幼児へのかかわり
D.内服が困難な子どもへのかかわり
E.悪心・嘔吐の苦痛がある学童へのかかわり
F.「絶食」をしている幼児へのかかわり
G.日々動けなくなる子どもへのかかわり
5.病気をもつ子どもの家族へのかかわり
A.子どもの造血幹細胞移植の選択に直面する家族へのかかわり
B.呼吸器を装着した子どもをもつ家族への援助
C.慢性疾患の子どもをもつ父親を含めた家族へのかかわり
6.死にゆく子どもと家族へのかかわり
7.子どもと家族を支援するチーム医療
付録
1.看護師の倫理規定
2.看護の倫理綱領(案)
3.病院における子どもの看護「勧告」
4.児童の権利に関する条約(抜粋)
内容説明
本書では子どもと家族への援助とその効果(アウトカム)に焦点を当てている。具体的な場面における子どもや家族の行動をどのように理解、判断(臨床判断)し、かかわればよいかを説明している。本書の特徴は具体的な援助だけでなく、援助による子どもと家族の変化まで書かれているところである。援助の結果、子どもや家族がどのように変化したのか、すなわちかかわりの効果(アウトカム)についても書かれている。また、各著者は“かかわりの技のポイント”で、多くの看護師が日々実践している卓越した技を抽出している。子どもと家族のそれぞれの状況(物語り、ナラティブ)のなかで、小児看護における臨床判断、卓越した技とは何かに迫っている。
目次
1 いま、小児看護に求められていること
2 外来を受診する子どもと家族へのかかわり
3 検査や処置に取り組む子どもへのかかわり
4 入院している子どもへのかかわり
5 病気をもつ子どもの家族へのかかわり
6 死にゆく子どもと家族へのかかわり
7 子どもと家族を支援するチーム医療
著者等紹介
筒井真優美[ツツイマユミ]
日本赤十字看護大学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 心理学 〈2〉 その応用