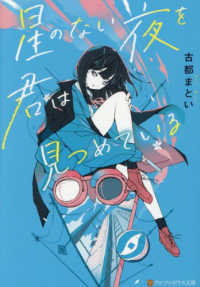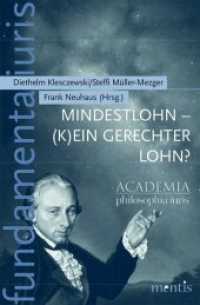- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学外科系
- > 麻酔科学・ペインクリニック
出版社内容情報
《内容》 痛みの原因や発生機序の概説と,行動学的研究から遺伝子学的研究まで幅広い実験法のアウトラインをわかりやすく解説.最新の研究成果も提示し,また重要事項には,詳細な解説を加えるポイント欄も設けた.痛みのコントロールへの関心が高まる中で,これから実験を始める若手医師に格好の手引書であり,また基礎研究の経験のない臨床医が痛みのメカニズムを理解するための啓蒙書にもなっている. 《目次》 【主要目次】 総 論 1.疼痛機序についての概説 A.疼痛の種類 1.生理的疼痛(急性侵害性疼痛) 2.組織損傷性・炎症性疼痛 3.ニューロパシックペイン B.疼痛機序の概説 1.末梢性機序 2.脊髄性機序 3.内因性鎮痛機構 C.最近注目されている疼痛情報伝達における受容体とイオンチャネル 1.電位依存性イオンチャネル(voltage-dependent channel) 2.リガンド感受性イオンチャネル D.疼痛と鎮痛の研究法の概説と将来の方向性 実験法 1.行動学的研究法 1・1疼痛モデルと疼痛評価 A.急性侵害刺激 B.炎症性疼痛モデル(化学刺激) C.ニューロパシックペインモデル D.内臓痛 E.ノックアウト(knock out)マウスモデル 1・2 薬物投与 A.薬物投与法 B.薬物投与に用いる器具 C.研究に使用される疼痛物質,鎮痛物質 D.鎮痛評価法 2.電気生理学的研究法 2・1 in vitro記録を用いた研究 A.細胞内電位記録法 B.パッチクランプ法 2・2 in vivo記録を用いた研究 A.細胞外電位記録法 B.細胞内電位記録法 C.in vivoパッチクランプ法 3.組織学的研究法 3・1 免疫組織化学的染色法 A.酵素抗体法 B.実 験 3・2 in situハイブリダイゼーション法 A.in situハイブリダイゼーション法の基本概念 B.in situハイブリダイゼーション法の具体的方法 4.神経化学的研究法 A.マイクロダイアリシス法 B.組織抽出法 C.高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による測定 D.受容体結合実験法 E.イムノアッセイ法(酵素免疫測定法) 5.光学的研究法 A.細胞内Ca2+濃度―カルシウムイメージング法 B.電位感受性色素を用いた研究 用語解説