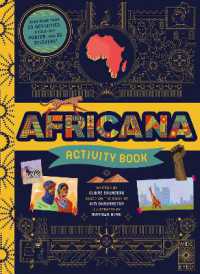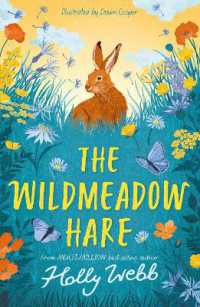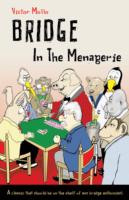出版社内容情報
《内容》 さまざまな生物種でゲノムのデータが充実しつつあるいま,バイオインフォマティクスはすべてのライフサイエンス研究者に必須の技術です.どのデータベースからどのように必要な情報を得,どのように利用できるのかを,基礎からわかりやすく解説しました.
《目次》
CONTENTS
1章 生物情報データベースを覗いて見よう
生物情報データベースの基礎知識/ゲノムネットへアクセス/p53遺伝子データを検索する/どの情報から調べればいいの?/分子グラフィックス操作にチャレンジ/パスウェイデータベースにアクセスする/ポストゲノム解析で注目されるパスウェイ ほか
2章 他の生物種にもガン抑制遺伝子はあるの?
配列の相同性とは?/配列解析の基本概念/配列を比較する/相同性配列検索プログラムBLASTを使ってみよう/P53_MACMU はどのような生物が持つ遺伝子か調べてみよう/遠い進化関係にある配列を探し当てる/遠縁性について/PSI-BLASTによる遠縁性配列検索 ほか
3章 遺伝子配列情報を使って生物の類縁関係を調べてみよう
多重配列比較と系統樹解析/多重配列比較/系統樹解析/配列データの取得/マルチプルアラインメントの実行/マルチプルアラインメントの結果から系統樹を作成する/マルチプルアラインメントに基づく機能分類樹と立体構造へのマッピング:Evolutionary Trace 法 ほか
4章 タンパク質の立体構造を覗いて見よう
タンパク質の形とは?/タンパク質の階層構造/タンパク質の折りたたみ様式/分子グラフィックスによるタンパク質立体構造の表示/タンパク質立体構造データベースProtein Data Bankへアクセスする/タンパク質の立体構造分類を調べる/ホモログとアナログ/立体構造と機能 ほか
5章 配列情報からタンパク質の機能を予測してみよう
モチーフデータベース/膜貫通領域の推定/統合モチーフデータベース検索システムの利用/モチーフデータベースの観察/Pfamデータベースを調べる/膜貫通領域を予測する/シグナルペプチドの予測 ほか
6章 ゲノムレベルでデータを見る! ヒトゲノムデータベースへ
ゲノム配列決定について/ゲノム地図の作成と塩基配列の決定/ゲノム配列を調べる/キーワードによるパーキン遺伝子の検索と染色体地図へのマッピング/BLASTによるパーキン遺伝子配列の検索と染色体地図へのマッピング/オーソログ遺伝子に注目した比較ゲノム解析/オーソログ遺伝子とパラログ遺伝子/COGデータベース ほか
7章 解析の実際:配列解析から立体構造予測、機能予測まで
タンパク質の立体構造予測/立体構造情報を利用した機能解析/配列解析によるタンパク質判別、局在予測、モチーフ検索/インターネットによる立体構造予測/予測構造の評価/立体構造に基づいた機能解析/プラスワン ゲノムスケールでの配列解析と構造予測 ほか
8章 文献検索システムPubMedを使う
Entrez:分子生物学データ統合検索システム/PubMedへのアクセスと既知の文献の検索/関連論文の検索/同じコンセプトを持つ広域論文の検索:MeSH項の利用/PubMedの自動用語マッピング機能 ほか
9章 「生物の情報」と「生理機能」について
生物は情報機械である/化学物質による情報伝達/細胞を伝わる電気信号/細胞内への信号伝達/生物のシステムは物質変換でできている/細胞内外の物質輸送/分子の合成・分解/超分子の形成/分子間相互作用による生理機能 ほか
付録:バイオインフォマティクス実践のためのURL集
目次
1 生物情報データベースを覗いてみよう
2 配列を比べると何がわかるの?
3 遺伝子配列情報を使って生物の類縁関係を調べてみよう
4 タンパク質の立体構造を覗いてみよう
5 配列情報からタンパク質の機能を予測してみよう
6 ゲノムレベルでデータを見る!―ヒトゲノムデータベースへ
7 解析の実際―配列解析から立体構造予測、機能予測まで
8 文献検索システムPubMedを使いこなす
9 「生物の情報」と「生理機能」について
著者等紹介
広川貴次[ヒロカワタカツグ]
沖縄に生まれる。東京農工大学工学部物質生物工学科(現生命工学科)卒業。同大学大学院工学研究科博士課程修了。(株)菱化システム計算科学部勤務を経て、現在、産業技術総合研究所生命情報科学研究センター(CBRC)ゲノム情報科学チーム研究員。工学博士。膜タンパク質を対象としたバイオインフォマティクス研究に従事。創薬分野に結びつく方法論、プログラムの開発を目指している。日本生物物理学会、日本蛋白質科学会、日本バイオインフォマティクス学会会員
美宅成樹[ミタクシゲキ]
三重県に生まれる。東京大学理学部物理学科卒業。同大学大学院を終了後、東京大学工学部物理工学科助手を経て、現在は東京農工大学工学部生命工学科教授・総合情報メディアセンター長。理学博士。所属学会は、生物物理学会、物理学会、分子生物学会、バイオインフォマティクス学会など。1990年から始まったヒトゲノム計画にはゲノム情報の側面から関わり、プロジェクトの推移を内部で体験することできたのは幸運だった。当初からゲノム科学における教育の問題と社会との接点の問題が重要だと考え、バイオインフォマティクス講習会や市民講座などを継続的に行ってきた
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。