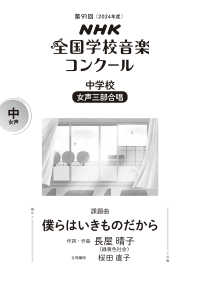出版社内容情報
コンピュータは,1940年に誕生して以来,ハードウェア技術,ソフトウェア技術を基盤として,基礎技術から応用面に至るまで常に急速な進歩を続けている.これに伴ってコンピュータ工学の扱う内容は高度化,広範囲化している. 本書の目的は,コンピュータ工学に関する入門書である.本書は,初めてコンピュータを学ぶ学部2年生を想定した講義用として編集したものである.また,専門高校生から技術者の入門書として活用できるように,基本的技術を重視し,章の独立性に配慮して構成した. 1章 コンピュータの歴史と原理
コンピュータの発達の歴史を振り返るとともに,コンピュータの基本的な原理について解説する.
2章 マイクロプロセッサ
CPUとして中心的役割を担うマイクロプロセッサを取り上げ,その構成要素と役割について解説する.
3章 主記憶装置と周辺装置
半導体メモリを中心として構成される主記憶装置とハードディスク,ディスプレイなどの代表的な周辺装置について解説する.
4章 データの表現
コンピュータ内部で扱われる数値,文字,ファイル,データベースについて解説する.
5章 論理回路
ハードウェアを構成する論理回路の基礎とコンピュータの基本論理回路について解説する.
6章 ディジタルIC
論理回路を実現する手法として,TTL,標準CMOS,SRAM,マイクロコントローラを取り上げ,その取り扱いを解説する.
7章 CASLⅡによるプログラミング
CPUの機械語命令に対応するアセンブラ言語について,「(財)日本情報処理開発協会」によるアセンブラ言語「CASLⅡ」を取り上げ解説する.
常に発展を続けるコンピュータ分野において,柔軟かつ独創的な応用技術力が求められている.応用技術力は十分な基礎技術力の上に培われるものである.将来の技術者達の足がかりとして本書が活用されれば幸いである.
終わりに,本書を出版するにあたり多大なご尽力をいただいた東京電機大学出版局の植村八潮氏,石沢岳彦氏に深く感謝申し上げる.
2002年夏 著者しるす
第1章 コンピュータの歴史と原理
1.1 コンピュータの歴史
1.2 コンピュータの原理
・演習問題
第2章 マイクロプロセッサ
2.1 マイクロプロセッサの処理性能
2.2 マイクロプロセッサの種類
2.3 マイクロプロセッサの構成
2.4 COMETⅡの基本構成と命令の形式
2.5 COMETⅡの構成要素
・演習問題
第3章 主記憶装置と周辺装置
3.1 主記憶装置の構成
3.2 主記憶装置の特性
3.3 ICメモリ
3.4 キャッシュメモリ
3.5 補助記憶装置
3.6 入出力装置
・演習問題
第4章 データの表現
4.1 数体系
4.2 数値データ
4.3 文字データ
4.4 ファイル
4.5 データのチェック
4.6 データの構造
4.7 データベース
・演習問題
第5章 論理回路
5.1 論理回路の表現
5.2 基本論理回路
5.3 順序回路
5.4 組合せ回路の応用
5.5 順序回路の応用
5.6 論理回路の簡単化
・演習問題
第6章 ディジタルIC
6.1 標準ロジックIC
6.2 規格表の見方・使い方
6.3 規格表の例
6.4 標準ロジックICの使用例
6.5 ICメモリの使用例
6.6 マイクロコントローラの使用例
・演習問題
第7章 CASLⅡによるプログラミング
7.1 レジスタ操作とデータ転送
7.2 条件分岐
7.3 数値計算
7.4 データ列の扱い
7.5 ビット操作
・演習問題
付録 アセンブラ言語の仕様
1.システムCOMETⅡの仕様
1.1 ハードウェアの仕様
1.2 命令
1.3 文字の組
2.アセンブラ言語CASLⅡの仕様
2.1 言語の仕様
2.2 命令の種類
2.3 アセンブラ命令
2.4 マクロ命令
2.5 機械語命令
2.6 その他
3.プログラム実行の手引
3.1 OS
3.2 未定義事項
参考資料
1.命令語の構成
2.マクロ命令
3.シフト演算命令におけるビットの動き
演習問題回答
参考文献
索引
内容説明
コンピュータは、1940年に誕生して以来、ハードウェア技術、ソフトウェア技術を基盤として、基礎技術から応用面に至るまで常に急速な進歩を続けている。これに伴ってコンピュータ工学の扱う内容は高度化、広範囲化している。本書の目的は、コンピュータ工学に関する入門書である。初めてコンピュータを学ぶ学部2年生を想定した講義用として編集。また、専門高校生から技術者の入門書として活用できるように、基本的技術を重視し、章の独立性に配慮して構成した。
目次
第1章 コンピュータの歴史と原理
第2章 マイクロプロセッサ
第3章 主記憶装置と周辺装置
第4章 データの表現
第5章 論理回路
第6章 ディジタルIC
第7章 CASL2によるプログラミング
付録 アセンブラ言語の仕様
著者等紹介
浅川毅[アサカワタケシ]
東海大学工学部電子工学科卒業(1984年)。東京都立大学大学院工学研究科博士課程修了(電気工学専攻)(2001年)。博士(工学)。(仮称)太田地区単位制工業高校開設準備室。東海大学電子情報学部講師(非常勤)。東京都立大学大学院工学研究科客員研究員。第一種情報処理技術者
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。