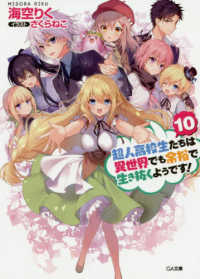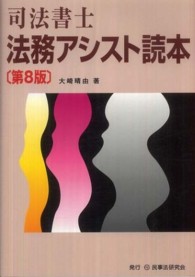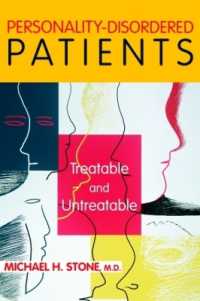出版社内容情報
まえがき
「地球は青かった」というのは1961年に人類初の宇宙飛行士となったロシアのユーリ・ガガーリンの言葉である.ガガーリンの見た地球は,実際には,環境破壊によって「青さを失いつつある地球」であった.その失われた地球の「青さ」を回復しつつ技術発展することが21世紀に課せられた人類の課題となっている.気圏と地圏,水圏そして生物圏から構成されている地球環境は全球的な規模で変化しており,そのような環境変動の要因を理解し対処するためには地球規模の観測データを周期的に収集し解析することが必要である.そこで,人工衛星を使って宇宙空間から地球環境の情報を解析する試みが20世紀後半から国際的なスケールで行われてきた.現在に至るまでの衛星打ち上げ技術とコンピュータの急速な発達もさながら,センサ(観測器)と手法論の開発,データの地球科学への応用に関する研究の進歩には目ざましいものがあり,着々と成果をあげつつある.そのなかでも,雲や霧を貫通し昼夜を問わず観測の可能な合成開口レーダ(SAR: Synthetic Aperture Radar)は,1978年に打ち上げられた海洋観測衛星としては初のSEASAT-SAR以来,最も重要で有用なセンサの一つとして衛星やスペースシャトル,航空機に搭載され世界各国で利用されている.SAR技術の急速な発展にともなって大量のSARデータが比較的自由に利用できるようになった反面,これらのデータの解析技術と応用に関する基礎研究は後塵を拝している状態である.一般的なSARシステムを使って得られたデータ,さらに干渉SARやポラリメトリックSARによって得られたデータから観測対象の特性を定量的に解析し高精度の情報を抽出するためには,観測対象に入射したマイクロ波が散乱されるプロセスと,受信された信号からSAR画像を生成するプロセスの知識が必要不可欠である.前者の散乱問題はSAR分野に限らず,すべてのマイクロ波および光学系リモートセンシングに必要な知識として学問の一分野を築いている.本書では後者のSAR画像生成プロセスの基礎を解説する.2004年には可変入射角でポラリメトリックモードを持った国産衛星ALOS-PALSAR(Advanced Land Observation Satellite-Phased Array L-band SAR)が打ち上げられる予定で,現在運用中のERS-2, ENVISAT, Radarsat衛星搭載のSARやRadarsat 2号,3号計画を考えると,本書の出版は時期的にも適していると思われる.SARデータは,海洋, 雪氷,水文,地学,地理学, 農学,森林,都市,気象,防災,考古学から軍事情報収集といった多岐の分野で利用されている.これらの応用分野でSARデータを有効に活用する場合,まず SAR 画像がいかにして生成されるかという基礎的な知識が必要となる.SAR 画像の生成過程は光学系データのそれとは大きく異なり,処理・解析方法も複雑である.日本においては,SAR搭載の国産衛星JERS-1が1992年に打ち上げられてから,SARシステムやデータ処理,画像解析に携わる技術者や研究者が増えつつある.このようなトレンドの中で「硬い」ながらも,SAR画像生成プロセスの最も基本となる理論を数学的に解説した専門書が必要と考えて執筆したのが本書である.最も基礎的なレベルでの理解なしにSAR画像の解析はできないだろうし,ましてや干渉SARやポラリメトリックSAR,インバースSARデータの厳密な意味での定量解析は困難である.したがって本書は,SARの研究者,技術者,利用者,大学院修士課程以上のレベルの学生を対象としており,写真を多用せず応用に関する記述も最小限にとどめ,図と数式を使った解説を中心に構成されている.現在,SARの分野で活躍している人たちや入門者にとって本書がSARを理解する一助となり,地球環境をはじめとする多岐にわたる分野でSARデータが活用されるようになることが筆者の願いである.
本書の出版にいたるまでには,多くの人たちの御尽力があった.なかでも,未来技術研究所所長で東海大学教授の中山泰喜博士,本書の刊行をして下さった東京電機大学出版局編集課の植村八潮氏と菊地雅之氏,千葉大学名誉教授の土屋清博士には本書の内容と構成に関する大変有意義な助言を頂いた.SARの歴史やレーダ方程式,画像解析に関してはJohns Hopkins大学応用物理研究所のKeith Raney博士との長年にわたる意見交換に負うところが多い.SARプロセッサに関しては英国Phoenix Systems社のAndy Smith氏に多くの示唆と助言を頂いた.本書で使用した SAR 画像は,NASA/JPL,宇宙航空研究開発機構(JAXA),三菱電機鎌倉製作所の原芳久氏,英国Royal AerospaceEstablishment, Farnborough(現 QinetiQ)のGordon Kyte博士とBrian Barber氏の御好意による.アロングトラックInSARデータはイスラエルTel-Aviv大学のLev Shemer教授に提供して頂いた.第7章の航空機搭載SAR画像は通信総合研究所の浦塚清峰博士と佐竹誠博士の御好意による.統計解析データは高知工科大学特別研究員のGlen Davidson博士に協力して頂いた.また,SEASAT衛星のイラストは英国 EllisHorwood出版社のSir Ellis Horwood, MBEの許可を得て筆者が修正,加筆したものである.
2003年12月
大内 和夫
はじめに
第1章 序論
1.1 合成開口レーダとリモートセンシング
1.2 合成開口レーダの応用分野
1.3 本書の構成
第2章 合成開口レーダの概要
2.1 合成開口レーダの歴史
2.2 SARの原理と光学ホログラフィ
第3章 電磁波の基本概念
3.1 電磁波と波動
3.2 電磁波の定量的記述
3.3 ヘルムホルツ方程式の解
3.4 偏波特性
3.5 電磁波の減衰と散乱係数
第4章 レーダ方程式とマイクロ波の散乱
4.1 レーダ方程式
4.2 アンテナパターン
4.3 マイクロ波の散乱
第5章 パスル圧縮技術とレンジ方向の画像生成
5.1 画像レーダの概念
5.2 非圧縮パルスによるレンジ方向画像生成
5.3 ジオメトリック画像変調
5.4 パルス圧縮技術を使ったレンジ方向の画像生成
第6章 合成開口技術とアジマス方向の画像生成過程
6.1 アジマス方向の分解能
6.2 合成開口技術の概要
6.3 時間領域での合成開口処理
6.4 周波数領域での合成開口処理
6.5 アジマスアンビギュイティ
6.6 マルチルック処理
6.7 オートフォーカス
6.8 移動体の画像
6.9 SARの種類
第7章 SAR画像解析の基礎
7.1 3次元散乱面の複素画像
7.2 強度画像生成プロセス
7.3 スペックル
7.4 スペックル軽減
7.5 ガウス統計にしたがわないスペックル
付録A 波動の複素関数表示
A.1 複素関数と特性
A.2 波動の複素振幅と強度
付録B コヒーレンス
B.1 時間的コヒーレンス
B.2 空間的コヒーレンス
付録C フーリエ変換と応用
C.1 ディラックのデルタ関数
C.2 フーリエ変換
付録D 主要パラメータのリスト
参考文献
索引
内容説明
本書では、SAR画像生成プロセスの基礎を解説する。
目次
第1章 序論
第2章 合成開口レーダの概要
第3章 電磁波の基礎概念
第4章 レーダ方程式とマイクロ波の散乱
5章 パルス圧縮技術とレンジ方向の画像生成
第6章 合成開口技術とアジマス方向の画像生成過程
第7章 SAR画像解析の基礎
付録A 波動の複素関数表示
付録B コヒーレンス
付録C フーリエ変換と応用
付録D 主要パラメータのリスト
著者等紹介
大内和夫[オオウチカズオ]
1971年、日本大学理工学部物理学科卒業。1976年、Southampton University,Bachelor of Science in Physics卒業。1977年、Imperial College,University of London,Master of Science in Physics修了。1980年、Imperial College,University of London,Doctor of Philosophy in Physics修了。1980年、Imperial College,University of London,Blackett研究所助手。1984年、King’s College,University of London,Wheatstone研究所主任研究員。1992年、Imperial College,University of London,Blackett研究所特別研究員。1996年、広島工業大学環境学部教授。1999年、高知工科大学工学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。