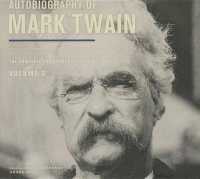出版社内容情報
第1部 一般問題
第1章 電気に関する基礎理論
1.1 直流回路
1.2 熱量・電力・電力量
1.3 分流器・倍率器
1.4 電線の抵抗
1.5 単相交流回路
1.6 単相交流の直列・並列回路
1.7 三相交流回路
第2章 配電理論及び配線設計
2.1 単相3線式回路と電圧
2.2 単相3線式回路の電圧降下
2.3 配電線路の高圧降下
2.4 許容電流と電流減少係数
2.5 分岐回路
2.6 過電流遮断機の性能
2.7 過電流遮断機の定格電流
2.8 幹線の許容電流
2.9 分岐回路における開閉器の省略
第3章 電気工事の施工方法
3.1 施設場所による工事の種類
3.2 ケーブル工事
3.3 金属管工事
3.4 合成樹脂管工事
3.5 可とう電線管工事
3.6 ダクト工事
3.7 地中電線路の施設
3.8 コードの使用制限
3.9 屋内のネオン放電灯工事
第4章 一般用電気工作物の検査法と測定方法
4.1 電圧,電流,電力の測定
4.2 変圧器とクランプメータ
4.3 接地抵抗の測定法
4.4 絶縁抵抗の測定法
4.5 竣工検査の手順,検査の義務
第5章 電気機械・器具
5.1 蛍光灯回路
5.2 照明器具・機器の力率
5.3 三相誘導電動機の運転
5.4 電気工事と工具
5.5 電線
5.6 スイッチの種類
5.7 点灯回路
5.8 コンセントと差し込みプラグ
5.9 過電流遮断器
第6章 電気設備技術基準
6.1 電圧の区分と絶縁抵抗
6.2 接地工事
6.3 接地工事の省略
6.4 漏電遮断器の施設
6.5 電線の接続法
6.6 対地電圧の制限と例外
第7章 電気関係法規
7.1 電気事業法
7.2 電気工事士法
7.3 電気工事士の作業
7.4 電気工事業の業務の適正化に関する法律
7.5 電気用品安全法
第2部 鑑別問題
第8章 電線管工事
8.1 電線管工事の工具1
8.2 電線管工事の工具2
8.3 電線管工事の器具1
8.4 電線管工事の器具2
8.5 電線管工事の器具3
第9章 ケーブル工事
9.1 ケーブル工事の器具
9.2 ケーブル工事の工具
第10章 ダクト工事
10.1 ダクト工事の器具
第11章 配線器具
11.1 配線器具1
11.2 配線器具2
11.3 配線器具3
11.4 配線器具4
11.5 配線器具5
第12章 工具
12.1 いろいろな工具1
12.2 いろいろな工具2
第13章 計測器
13.1 いろいろな計測器1
13.2 いろいろな計測器2
第3部 配線問題
第14章 配線用図記号
14.1 一般配線
14.2 配線に関する記号と機器
14.3 照明器具
14.4 コンセント
14.5 点滅器
14.6 開閉器。計器
14.7 配電盤・分電盤,呼出
第15章 木造住宅の施工方法
15.1 引込口から屋側配線まで
15.2 開閉器の省略
15.3 メタルラス張り等の工事
15.4 接地工事と絶縁抵抗
15.5 屋内配線
15.6 200V配線と過電流遮断器
第16章 単線図から複線図への変換
16.1 スイッチに至る電線の本数
16.2 ジョイントボックス間の電線の本数
16.3 ジョイントボックス内の配線
受験ガイド
索引
内容説明
本書は、第二種電気工事士の筆記試験受験者のために、短期間で国家試験に合格できることをめざしてまとめたものである。
目次
第1部 一般問題(電気に関する基礎理論;配電理論及び配線設計;電気工事の施工方法 ほか)
第2部 鑑別問題(電線管工事;ケーブル工事;ダクト工事 ほか)
第3部 配線問題(配線用図記号;木造住宅の施工方法;単線図から複線図への変換)
著者等紹介
粉川昌巳[コガワマサミ]
日本大学理工学部電気工学科卒業(1979)。東京学芸大学大学院技術教育専攻修士課程修了(1998)。東京都立蔵前工業高等学校電気科教諭
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。