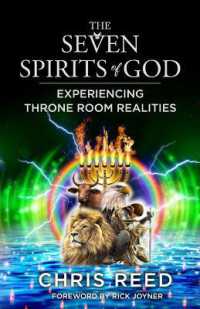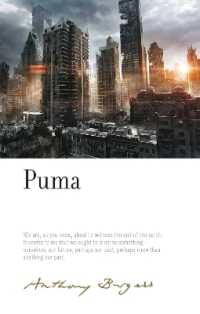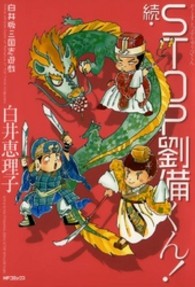目次
戦時の日本に育つ
戦中、戦後の教育
阪大第2内科での医局生活
内科を横断する脂質代謝の研究
City of Hope Medical Centerにて
世界に通ずるリピッドクリニックを作る
大学紛争の時代
コレステロールを下げる
国立循環器病センターに移る
研究所副所長としての立場からの思い出を綴る
老健の医者になる
高齢者介護の重要課題
稿を終えて:恵まれた人生、家族と友人・同僚への感謝
著者等紹介
山本章[ヤマモトアキラ]
昭和7年大阪生まれの大阪育ち。大阪大学医学部付属病院第2内科学教室で脂肪肝の研究に取り組み、昭和38年「肥満外来」を開始。昭和39‐42年米国カリフォルニア州City of Hope Medical CenterのGeorge Rouser博士のもとで脂質分析の開発研究。42年に大阪大学に復帰して「高脂血症外来」を開設。昭和53年遠藤博士(当時三共株式会社)の発見した最初のスタチンを世界ではじめて臨床に応用。昭和54年国立循環器病センター研究所に移籍して「動脈硬化に関連した血漿リポ蛋白異常の遺伝素因と栄養の関連についての研究」を推進した。この間家族性高コレステロール血症のアフェレーシス療法を確立。平成7年定年退職、平成8年から箕面市立老人保健施設施設長として高齢者の介護と医療に従事する傍ら、国立循環器病センター研究所名誉所員として動脈硬化に関する研究の補完を行うとともに、老年医学に臨床研究の場を広げている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。