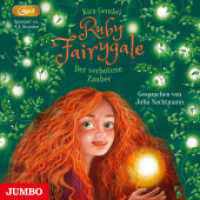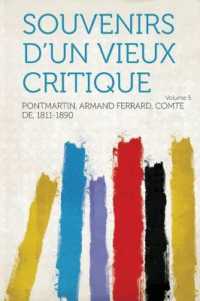出版社内容情報
《内容》 本書は日常で最もよく遭遇する病態のひとつでありながら,その理解と対応が難しい本症の臨床での実際をわかり易く,具体的に解説したものである. 病歴,身体所見,検査所見のとり方,鑑別診断,心機能の評価法,心エコーによる診断から治療,管理までを実際の例,写真を多用してプラクティカルに示している.随所に用語や概念などを脚注の形でコメントし,又,ケーススタディのQ&Aで診断・治療の応用力の育成を図るなど,その基本から実践までが平易に身につくよう著されている. まえがき 心血管系に著明な異常が生じれば,遅かれ早かれ心不全という病態に陥る.そこにはあらゆる心疾患や内分泌系の異常が包括される.そのような基礎疾患の多様性に比し,臨床像には多くの共通点があるので,診療の要点をつかむことは決して困難なことではない. 心不全は古典的には,心室の収縮力が低下するために生じると考えられ,したがって治療は強心薬と利尿薬が中心であった.その後,左室の収縮は悪くなくても,拡張機能の異常によって心不全が起こり得ることが知られるようになった.また圧受容器を介した,交感神経系およびレニン-アンジオテンシン系などの体液性因子によって,血圧が維持されることも知られた.しかしその代償機構が過度に働くと,心筋を傷害することが判明して,利尿薬,血管拡張薬などの左室の負担を減らす減負荷療法が,心不全治療の中心になった.カテコラミンおよびPDE阻害薬などの強心薬は,不全心のエネルギーを枯渇させ,一方では細胞内カルシウムイオンを増加させ不整脈を生じやすくさせる.そのためかえって心不全患者の予後を悪くすることが判明した.そして近年,組織のアンジオテンシンIIが,心筋に加わる負荷に対して細胞を肥大させ,コラーゲン線維を増やす適応現象が生体に不利に働く事実も判明した.その結果,アンジオテンシンIIを抑制することが,心不全患者の予後の改善に重要であることがわかって,ACE阻害薬が心不全治療薬として脚光を浴びた.さらにいくつかの新しい強心薬には期待がもたれているが,生命予後を改善するかどうかは将来の課題である. 心不全の臨床においては,生理学的異常を迅速かつ正確に捉えることが特に重要である.そのような生理学的な変化を実際に目で追えることは,循環器診療の最も興味深い面であるといえる. 本書は臨床医を始め,医学生や実地医家,さらに臨床研究を志す人を対象に心不全の解説書として書かれた.内容は机上の空論とならないために,実例を用いて解説し,特に心エコー図はそのアトラスとしても用いられるように図を豊富にした.また初学者にも理解されやすいように,各所に脚註を設けて用語解説に努めた. 臨床医は心不全患者を目の前にして,4種類のcommon technic(問診,身体所見,心電図,胸部X線写真)によって,その重症度,基礎疾患に関して大体の診断を下せるはずである.さらにベッドサイドにおける心エコー図,心機図などの非侵襲的検査の威力は甚大である.したがって本書では,これらの基本的手技の解説に重点を置き,たとえ立派な理論でも臨床で応用が不可能なものや,心不全患者に侵襲の多い手技は割愛した. 本書が循環器診療に従事する読者諸兄姉の心不全に対する理解と診療の助けになれば,この上ない幸いである. 最後に本書は多くの人々の協力のもとに完成された.特に近畿大学第四内科の長坂行雄助教授には,肺循環について,多くの貴重な助言をいただいた.さらに清恵会病院生理検査室の技師諸氏には,忍耐強く良い記録を得ることに協力していただいた.また出版を進めていただいた中外医学社の荻野邦義氏,秀島悟氏および森本俊子氏視に感謝する. 1996年2月 著者 《目次》 目次 §1 心不全の病態生理 A.概念および定義 1 1)古典的な定義 1 2)新しい定義 1 3)代償機構 2 4)急性心不全および慢性心不全 2 5)循環動態による心不全の様式 3 6)心不全の臨床症状 3 7)心不全の診断 4 8)NYHAの心機能分類 4 9)慢性心不全における運動耐容能について 6 10)左心不全と右心不全 6 B.代償機構の役割と心不全の成立 8 1.圧受容体と体液性調節機構 8 2.代償機構の破綻と心不全の成立 10 C.心不全の基礎疾患および時代的変遷 14 I.時代的変遷 14 II.心不全の基礎疾患とその病態 16 1.虚血性心疾患 16 2.高血圧性心疾患 18 3.特発性心筋症 19 4.弁膜症 20 5.三尖弁逆流,僧帽弁逆流を伴った心房細動 22 6.成人の先天心疾患 22 7.肺性心 23 D.心不全の重症度と予後 24 1.欧米における多施設共同研究について 24 2.心不全の予後を規定する因子について 25 §2 問診および身体所見のとりかた A.問診 30 B.身体所見 30 1.顔面および四肢の診断 30 2.頸静脈の視診 31 3.頸動脈の触診 31 4.前胸壁の視診・触診 32 5.前胸部の聴診 33 6.肺の聴診 33 7.腹部の診察 33 §3 基本的な検査所見 A.心電図 34 B.胸部X線写真 34 1.左心不全時の所見 34 2.右心不全時の所見 38 C.心音・心機図 38 1.心音図 38 2.頸動脈波 39 3.頸静脈波 45 4.心尖拍動図 45 §4 心不全に類似する疾患の鑑別 A.肺水腫 46 1.心原性肺水腫と非心原性肺水腫 46 2.左心不全時の肺水腫 47 3.医原的肺水腫 47 4.肺水腫以外の疾患の鑑別 48 B.気管支喘息 48 C.両側肺炎 50 D.成人呼吸促迫症候群 52 E.尿毒症肺 54 §5 左室収縮機能の評価 A.前負荷,後負荷,FRANK-STRARLINGの法則 56 1.FRANK-STARLINGの法則 56 2.前負荷 57 3.後負荷 57 B.心エコー図を用いた左室収縮機能の評価 58 1.左室収縮機能の指標 58 2.左室収縮性 59 3.収縮期左室挙動 61 C.左室収縮時間 61 1.左室収縮時間 61 2.Mモード心エコー図法を用いた方法 61 3.パルスドプラー法を用いた方法 62 4.左室収縮時間の臨床応用 62 5.パルスドプラー法を用いた大動脈駆出血流 62 D.Post-extrasystolic potentiation 64 1.PESPの機序 64 2.FRANK-STARLING機構は関与しない 64 3.臨床応用 64 E.心房細動における収縮機能 65 1.FRANK-STARLING機構の関与 65 2.先行R-R間隔に起因する心筋線維に固有の収縮増強効果 65 F.甲状腺機能亢進症 67 1.高拍出量性心不全 67 2.臨床例 69 §6 左室拡張機能の評価 A.拡張早期弛緩と拡張末期充満 70 1.拡張早期弛緩 70 2.左室弛緩の指標 70 3.等容弛緩期の長さ 70 4.緩速流入期 72 5.左室拡張末期充満 72 6.不完全弛緩 72 7.左室拡張機能傷害 72 B.拡張期圧-容積関係 72 1.左室拡張期圧-容積曲線 72 2.分子生物学的な解釈 73 3.拡張期圧-容積曲線の変化 74 C.Mモード心エコー図を用いた左室拡張機能 74 1.拡張期壁後退速度 74 2.僧帽弁のエコーの動き 74 3.Mモード心エコー図と心尖拍動図の併記 76 D.パルスドプラー法を用いた左室拡張機能 76 1.左室流入血流波形 76 2.加速時間,減速時間 77 3.左房寄与率 78 4.A/E比 78 5.偽正常化 79 E.左房機能および左房-左室間相互作用 79 1.左房機能 79 2.左房-左室間相互作用 80 §7 心不全例の心エコー図所見 A.左室拡大および左室収縮機能低下 83 B.拡張不全 86 1.概念および病態 86 2.求心性左室肥大の場合 86 3.アミロイドーシスおよび拘束型心筋症の場合 88 C.圧負荷,容量負荷に対する左室の反応 89 1.圧負荷を主とする疾患 89 2.左室容量負荷 90 D.冠動脈疾患の心エコー図所見 92 1.急性心筋虚血 92 2.亜急性期から慢性期の変化 92 3.慢性期 92 4.大動脈弁の収縮後期開放減少 95 E.特発性心筋症および二次性心筋疾患の心エコー図所見 95 1.肥大型心筋症 95 2.拡張型心筋症 100 3.心筋炎および他の二次性心筋疾患 101 F.弁膜疾患の心エコー図所見 105 1.僧帽弁疾患 105 2.大動脈弁疾患 106 3.三尖弁疾患 111 4.肺動脈弁疾患 113 G.慢性血液透析患者の心エコー図所見 114 1.慢性透析患者における左室収縮機能 114 2.慢性透析患者における左室拡張機能 114 H.右室圧負荷,容量負荷の心エコー図所見 118 1.肺高血圧の心エコー図所見 118 2.肺高血圧症の2種類の病態 118 3.右室容量負荷 118 §8 心不全の治療と非侵襲的検査所見 A.治療概論 122 1.心不全の原因をとり除く 122 2.心不全治療の一般的原則 122 3.減負荷療法 124 4.強心薬 124 5.cyclic-AMP依存性およびcyclic AMP非依存性強心薬 126 6.Ca2+センシタイザー 126 7.カテコラミン 126 8.β受容体遮断薬 127 9.アンジオテンシン変換酵素阻害薬 128 10.KATZ AMによる3つのパラダイム 129 11.心不全治療薬の選択と組み合わせ 130 12.心不全治療による血行動態の変化 130 B.非侵襲的検査を用いた心不全重症度評価 130 1.非侵襲的検査を用いた左室収縮機能の評価 130 2.左室の形態および左心機能の重症度評価 131 3.非侵襲的検査を用いた拡張機能傷害の評価 131 4.心不全の憎悪および改善 132 C.心不全の経過に伴う変化 132 1.左室拡張機能および肺高血圧 132 2.左室拡張機能の異常とIII音(S3),IV音(S4) 133 3.IV音-I音間隔(S4-S1間隔)の臨床的意義 133 D.奔馬調律の成因と推移 135 1.III音(S3),IV音(S4)の発生 135 2.S3の病的意義について 135 3.S4ギャロップおよび四部調律 136 4.左房収縮力低下例におけるギャロップ 136 5.心不全経過における奔馬調律の推移 137 6.重合奔馬調律 139 §9 心不全治療の実際 Case 1(労作時呼吸困難,起坐呼吸,咳嗽) 140 Case 2(労作時呼吸困難,咳嗽,微熱) 146 Case 3(労作時呼吸困難,夜間発作性呼吸困難) 151 Case 4(労作時呼吸困難,夜間発作性呼吸困難) 156 Case 5(胸痛,心窩部痛,嘔吐) 161 Case 6(心雑音の精査) 166 Case 7(労作時呼吸困難,起坐呼吸) 170 Case 8(起坐呼吸,全身倦怠感) 175 Case 9(起坐呼吸,歩行時呼吸困難) 180 文献 185 あとがき 195 索引 197
-

- 和書
- Tokyo Sketch