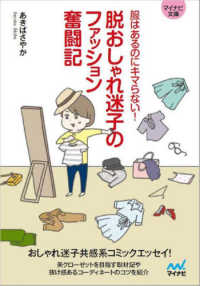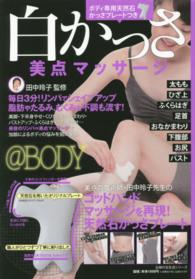出版社内容情報
《内容》 生命維持に必要な心機能を維持する心臓のエネルギーとは何か,その生理学的,病態生理学的な最新の答えとアプローチの方法を解説した書である.その研究が最先端にあり,世界の心臓力学,心臓病学の分野で高く評価されている著者らの研究成果をわが国の心臓生理学,心臓病学に関る研究者,臨床医に広く理解して頂くべくわかり易くまとめられた初めての解説書である.心臓の生理,病態に根源的に迫る心臓エネルギー学の基礎から臨床までを様々の問題点,角度からとらえて,読者に新しい視点を与える,関係者必読の書である. 序 心臓はそのポンプ機能を多量の化学エネルギーを消費しながら行っている.この心臓活動は生涯休むことがない.数秒でも心臓へのエネルギー供給が絶たれると収縮力が低下する.狭心症や心筋梗塞はこのようなエネルギー不足に起因する.このように生命維持に必要な心機能を維持する心臓のエネルギーとは何か? どのような医学,生理学的意義があるのか? どうやって測定するのか? などに対する最新の答えをわかりやすく用意するのが本書の目的である.幸い,我々の新しい考え方に基づく最近の生理学的,病態生理学的研究成果が,その答えを大分用意してくれている. 生体にとって心臓収縮の重要性は人類の起源と同じ頃から認識されてきた.17世紀のWILLIAM HARVEY(循環生理学の父)以来,循環や心臓収縮に対する科学的研究が進められてきて,やって前世紀末から今世紀初めにかけて,大きくの研究者が心臓の収縮を科学的研究の対象とすることができるようになってきた.そしてこの収縮によって発生する仕事の元になるエネルギーが興味の対象となってきた.しかし,それから1世紀弱経ったにもかかわらず,いまだに心臓の収縮が必要とするエネルギーを何が規定するかについては,充分理解されていない. 一方,心臓病で亡くなる人は,わが国では年間死亡数の20%を越え,しかも虚血性心疾患がその大部分と推測される.虚血性心疾患では,冠血管が動脈硬化性病変を起こして,心筋への循環が不充分になり,血流,灌流障害,代謝基質,酸素不足,代謝老廃物洗い出しも不充分になり,心筋のアシドーシス,カルシウム過負荷,ミトコンドリア障害,エネルギー産生不足,収縮蛋白のカルシウム感受性低下,心筋壊死などが引き起こされて,最終的に心筋の収縮不足が起きてくると考えられている.したがって,このような臨床上の重要な疾患の診断,治療,予防を効率的に行うためには,心臓の収縮のためのエネルギー需給バランス,およびそれに関連する因子をよりよく理解することが必要であろう. とくに,虚血性心疾患でしばしば存在するアシドーシス心筋や,心筋梗塞後の冠再灌流障害(スタンド,気絶)心筋の異常な酸素消費量亢進状態の存在は,臨床上充分解明されるべきであろう.また,収縮不全心の治療薬として何を用いるかという選択の場合に,充分注意されるべきことは,種々の新しく開発されてきた強心薬(ホスホジエステラーゼ抑制作用や収縮蛋白カルシウム感受性増強作用を持つ)が,急性動物実験においてではあるが,カテコラミンと同様な酸素浪費効果を持つことは,臨床で投与する際に充分認識されておくべきであろう. また高血圧治療薬としてアンジオテンシン変換酵素阻害薬がよく用いられるようになってきているが,古くより心臓の後負荷として血圧の下降は,心臓酸素消費量を著しく減少することが知られており,心肥大の退縮とからんで,興味ある点であろう. 本書では,編集者の一人(菅)が世界に先駆けて15年前に提案した心臓エネルギーの概念(収縮期圧容積面積,pressure-volume area:PAV)に基づいて,それ以来継続して編集者のグループが世界をリードする努力を注いで明らかにしてきたPVAを心臓酸素消費量の規定因子として適格性を,グループのメンバーがそれぞれ担当した研究部分をわかりやすく解説した.本書の内容が少しでも心疾患の克服に資することができれば望外の喜びと考えている.巻末の文献番号200番台医科のものは編者の少くともどちらかが直接関係している論文を年代順にリストしてある.300番台はそれぞれの章の末尾の文献を参考にして下さい. 1994年7月 菅 弘之 後藤葉一 《目次》 目次 §1.心臓エネルギーと酸素消費量 〈菅 弘之〉 1 A.心臓エネルギー研究の歴史 1 B.生体エネルギー 4 C.心臓酸素消費量の規定因子 7 D.心筋エネルギー消費機構 11 §2.収縮期圧容積面積(PVA) 〈菅 弘之〉 13 A.心室可変弾性モデル 13 B.総機械的エネルギー 17 C.収縮期圧容積面積(PVA) 19 §3.心臓酸素消費量とPVA 〈後藤葉一〉 22 A.心筋酸素消費量の規定因子 22 B.心筋酸素消費量の指標 23 C.PVA依存性酸素消費量 25 D.PVA非依存性酸素消費量 28 E.収縮効率 31 F.収縮性の酸素コスト 31 G.心臓のエネルギー代謝経路 33 §4.負荷条件と心臓エネルギー 37 1.前負荷からの独立性 〈後藤葉一〉 37 A.前負荷と収縮機能 37 B.前負荷とVo2-PVA関係 37 2.後負荷からの独立性 〈後藤葉一〉 40 A.後負荷と収縮期末圧-容積関係(ESPVR) 40 B.後負荷とVo2-PVA関係 42 C.圧負荷仕事と容量負荷仕事 43 D.負の仕事 44 3.収縮様式 〈後藤葉一〉 46 A.等容収縮と拍出収縮 46 B.異常収縮 47 4.FENN効果 〈能沢 孝〉 48 A.FENN効果とは 48 B.PVAとFENN効果 49 5.急速解放 〈安村良男〉 52 6.駆出速度 〈川口 鎮〉 56 A.内部抵抗 56 B.心室の電流源モデル 59 C.駆出速度増加にともなう心室圧低下と酸素消費 61 7.拍出の活性化 〈五十嵐祐一郎〉 64 A.各心室構成単位での拍出の活性化 64 B.拍出の活性化の機序 67 8.拍出活性化のエネルギー 〈安村良男〉 68 §5.収縮性と心臓エネルギー 70 1.カルシウム 〈菅 弘之〉 70 2.カテコラミン 〈菅 弘之〉 75 3.ジギタリス 〈畑 勝也〉 79 4.PDE阻害薬 〈畑 勝也〉 82 5.カルシウム感受性増強薬 〈畑 勝也〉 86 6.β遮断薬,カルシウム拮抗薬 〈能沢 孝〉 91 A.β遮断薬 91 B.カルシウム拮抗薬 92 7.2,3-butanedione monoxime(BDM) 〈高砂利行〉 95 8.リアノジン 〈高砂利行〉 102 9.カフェイン 〈高砂利行〉 109 10.麻酔薬 〈難波健利,高木 都〉 114 A.麻酔薬の心収縮性への影響 114 B.麻酔薬と心エナジェティクス 114 C.ペントバルビタール(ネンブタール(R))の心エナジェティクスに与える影響 114 11.機械的振動 〈西岡武彦〉 118 A.方法 119 B.結果 119 C.総括 122 D.今後の展望 122 12.弛緩,拡張機能 〈後藤葉一〉 125 A.弛緩,拡張機能に影響を及ぼす因子 125 B.弛緩障害と収縮性との関係 127 C.拡張機能障害の左室ポンプ機能に及ぼす影響 129 D.拡張機能と心筋酸素消費量 130 E.拡張機能障害における収縮効率と収縮性の酸素コスト 132 §6.心拍数,不整脈と心臓エネルギー 134 1.心拍数 〈佐伯彰夫〉 134 A.心拍数の心収縮性に及ぼす影響 134 B.心拍数の心筋酸素消費量に及ぼす影響 137 C.至適酸素消費量と心拍数 140 2.期外収縮,paired pulse 〈能沢 孝〉 141 A.双対刺激 142 B.二段脈 144 3.心房細動 〈川口 鎮〉 148 A.心房細動の心室圧への影響 148 B.心房細動時の心室メカニクス 150 C.心房細動のエナジェティクス 151 D.心房細動の拡張機能に関する影響 151 4.心室細動:理論と実験 〈夜久 均〉 154 A.歴史的背景 154 B.細動心の力学的モデル 155 C.細動心室のエナジェティクス 157 D.心室細動が心機能に与える影響 160 E.病的心における心室細動 160 5.心室内伝動障害:シミュレーション 〈菅 弘之〉 162 §7.温度と心臓エネルギー 166 1.低体温 〈夜久 均〉 166 A.低体温と収縮性 166 B.低体温とエナジェティクス 167 2.低体温による陽性変力作用の機作 〈楠岡英雄〉 170 A.収縮性の規定因子 170 B.低体温が興奮収縮連関に及ぼす影響 171 C.低体温が最大Ca2+活性化張力に及ぼす影響 171 D.低体温によるカルシウム反応性変化の機序 172 E.心臓エネルギーとの関連 173 3.高温 〈佐伯彰夫〉 175 A.高温と心機能 175 B.高温と心臓エネルギー 176 §8.冠循環と心臓エネルギー 180 1.心筋虚血 〈後藤葉一〉 180 A.心筋のエネルギー代謝 180 B.虚血時の心筋エネルギー代謝 182 C.心筋虚血と収縮期末圧-容積関係 182 D.冠灌流圧低下が左室エナジェティクスに及ぼす影響 184 E.冠動脈閉塞が左室エナジェティクスに及ぼす影響 187 F.hibernating myocardiumとstunned myocardium 187 2.GREGG現象 〈佐伯彰夫〉 190 A.GREGG現象とは 190 B.GREGG現象の機序 192 C.GREGG現象の生理学的意義 193 3.冠灌流様式 〈佐伯彰夫〉 194 A.冠血流量の調節 194 B.冠灌流様式と心臓エネルギー 195 C.閉鎖回路での収縮期末圧-容積関係 197 §9.不全心と心臓エネルギー 199 1.スタン心筋 〈大越祐一〉 199 A.スタン心とは 199 B.方法 200 C.結果 201 D.考察 202 2.アシドーシス心 〈畑 勝也〉 205 3.甲状腺機能亢進症 〈後藤葉一〉 212 A.甲状腺機能とミオシンアイソザイム 212 B.甲状腺機能亢進症心の収縮性 212 C.心収縮性とは何か:短縮速度と発生張力 215 D.甲状腺機能亢進症家兎心のVo2-PVA関係 216 E.Vo2-FTI関係 218 F.甲状腺機能亢進症イヌ心のVo2-PVA関係 219 4.うっ血性心不全,肥大心 〈後藤葉一〉 221 A.うっ血性心不全研究の背景 221 B.心不全の心収縮性 222 C.心不全のエナジェティクス 225 D.心不全における収縮性低下の機序 228 E.慢性心不全治療への示唆 229 F.肥大心のメカニクスとエナジェティクス 231 5.機械的心補助:myoplastyモデル 〈川口 鎮〉 234 A.機械的心補助の分類 234 B.歴史的背景 235 C.機械的心加圧補助の心室のメカニクスに与える効果 236 D.機械的心加圧補助の心室の酸素消費に与える効果 237 §10.種々の測定系における心臓エネルギー 241 1.心筋標本 〈久納隆一〉 241 A.実験的事実 心筋酸素消費量とFLA 241 B.PVAとFLAの関係 244 2.心室局所 〈後藤葉一〉 249 A.心室局所収縮機能と冠灌流 249 B.局所収縮機能とエナジェティクス 255 C.局所総機械的エネルギー指標としての「壁張力-面積」面積(TAA) 256 D.局所心筋エナジェティクスにおける今後の展望 260 3.右心室 〈山田 修〉 263 A.右室のエネルギー,酸素消費に関する研究の歴史 264 B.左室と同じ方法論が有効か? 265 C.右室の仕事をいかに定量化するか? 265 D.PVAは実際に右室でも有効か? 267 4.人工液灌流心 〈後藤葉一〉 270 A.人工液灌流心のメカニクス 270 B.人工液灌流心のエナジェティクス 272 5.生体内心臓 〈能沢 孝〉 276 A.開胸心におけるVo2-PVA関係 277 B.覚醒犬におけるVo2-PVA関係 280 6.成長:成犬と仔犬 〈菅 弘之〉 282 7.種差:イヌとウサギとネズミ 〈夜久 均〉 286 A.イヌ摘出交叉灌流心臓標本 286 B.ウサギ摘出交叉灌流心臓標本 286 C.ウサギ摘出赤血球灌流心臓標本 287 D.ネズミ摘出晶質液灌流心臓標本 287 8.ヒトにおける成績 〈高岡秀幸〉 289 A.臨床例における心筋酸素消費量の規定因子 289 B.臨床例における心筋酸素消費量の規定因子の測定方法 289 C.臨床例における心筋酸素消費量とその規定因子関係 292 D.ドブタミン投与の影響 296 E.臨床例における収縮効率の評価 296 F.臨床例における興奮-収縮連関のための心筋酸素消費量の評価 296 §11.心臓機械効率 〈畑 勝也〉 298 §12.心臓の最適収縮性:理論と実験 〈田中伸明〉 304 A.最適収縮性の歴史的背景 305 B.最適収縮性の理論的背景 308 C.実験データ 310 D.実験結果についての考察と問題点 311 E.最適収縮性の応用と可能性 313 §13.クロスブリッジ運動のエネルギー:理論的解析 〈TAD W. TAYLOR,菅 弘之〉 315 A.筋モデル 315 B.張力長さ関係 317 C.クロスブリッジ運動のエネルギー 318 §14.カルシウムキネティクスとエネルギー:シミュレーション 〈菅 弘之〉 320 §15.心筋酸素消費量の指標の比較 325 1.double productの問題点 〈安村良男〉 325 2.BRETSCHNEIDER indexの問題点 〈菅 弘之〉 328 3.pressure-work indexの問題点 〈安村良男〉 330 4.張力時間積分の問題点 〈安村良男〉 331 §16.preload recruitable stroke work 〈高岡秀幸〉 333 A.preload recruitable stroke work関係 333 B.他の収縮性の指標との比較 335 C.臨床例における評価 335 D.PRSW関係の直線性 336 §17.心筋ミトコンドリアの呼吸機能の測定 〈高木 都,趙 丹丹,趙 凌雲〉 342 A.心筋ミトコンドリアの分離法 342 B.ミトコンドリアの呼吸調節比(RCI),ADP:O比およびstate 3における酸素消費速度(state 3 O2)の測定 343 C.結果 344 §18.効率と経済性 〈菅 弘之〉 346 §19.残された課題と今後の展望 〈菅 弘之〉 349 共通文献 351 用語説明 365 索引 371

![iPhone完全マニュアル 〈2025〉 [テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48663/4866367164.jpg)