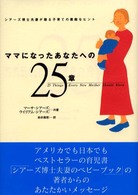出版社内容情報
《内容》 ●透析に必要とされる知識のキーポイント,データ,注意点,ノウハウなどを満載した透析治療の便覧.1項目を1頁又は見開き2頁で図,表,チャートにまとめて各々にコメントを簡明に記載した. まえがき 透析治療がわが国に定着してから約30年経過しようとしている.血液透析治療が一般化した当時,今日の透析医療の進歩や普及があるとは夢にも思わなかった.この間に公費負担や社会復帰も可能になるなど社会的に透析療法の意義が理解され,患者数は一段と増加し,透析施設が全国的に普及することになった.事実,慢性透析の治療は国公立の医療機関というよりは,大部分が民間の施設において行われている.このような事実から,わが国における透析治療は日常的な診療となったことを意味している.治療法の進歩は医学・薬学領域だけに留まらず,医工学や関連企業の援助協力により行われてきた.とくにダイアライザの膜の開発はわが国における繊維業界の技術により行われ,病態の解明と治療の有用性のために多大の貢献がなされてきたといえる.薬剤についてもエリスロポエチンを初めとして多数の有用な薬が開発され患者のQOLは著しく改善してきた. わが国における透析療法の現況は毎年,日本透析医学会によりアンケート調査が行われ,その結果は学会において報告されている.患者数は年々着実に増加を示し,1997年度末では約18万人に達するほどになり,しかも長期透析患者数や新規導入患者の増加も止むことはない状況である.長期生存率の向上と高齢者の増加により透析治療に伴う合併症が多発し,医療管理の困難さが年々深刻になってきている状況にある.生存率の成績は諸外国に比べるときわめて良好といえるが,細かな点を見れば解決困難な多くの問題点が山積していることがわかる. 治療の進歩に伴って長期生存が可能になり,このことが長期透析に伴う合併症や併発症・偶発症を出現させることになり,毎年病態の解明が検討されてきている.日進月歩の知識が毎年集積される結果,透析治療の進歩についていくことが難しくなりつつある.21世紀を迎えるに当たって,これまでの透析医療の膨大な知識を集大成することは意味があるといえる.医療の現場においても,これまでの経験を生かして効率の良い教育と治療方針を立てることが必要になると思われる. 本書は図表を中心に,透析医療に必要な多彩な知識を簡便にまとめ,ベッドサイドでも利用できるようなコンパクトなマニュアルとしてまとめたものである.著者も大学を卒業以来,透析医療を中心とした診療を行ってきたのであるが,これまでのわずかな経験をもとに自分なりにまとめる必要があると考えたことが本書を上梓するきっかけとなった.まとめるに当たって,先人や内外の研究者の優れた業績を利用させていただいたわけであるが,自分なりに図表に変更したりして理解しやすいように工夫した.このような知識を次の世代に引き継ぐことも有意義なことと考えたのである. 本書には透析治療に必要な項目はほぼ網羅され,できる限り要点のみを概説してある.このため文献や細かな点については不十分な部分があり,成書により確認されることを希望する.あくまでも必要な部分を備忘録としてまとめてあるので,基本的な知識を理解してから利用するのが本書の利用法といえる. 本書が日常の臨床の現場で広く活用されることになれば,本書を上梓した意味があると考える. 1999年5月 望星病院 北岡建樹 《目次》 目 次 I.透析療法の現状ー統計的資料 1.慢性透析患者数の変遷 2 2.透析患者の年齢推移 3 3.原因疾患(導入時)の推移 4 4.年度末の原因疾患の推移 5 5.死亡原因の推移 6 6.原因疾患別の生存率 7 7.年齢別の生存率 8 II.腎臓病の病態と診療指針 1.腎臓の機能 10 2.腎疾患の診療の方式 11 3.腎不全の検査 12 4.クリアランスとGFR 13 5.血清クレアチニン濃度 14 6.血液尿素窒素濃度(BUN) 15 7.血液尿素窒素値と血清クレアチニン濃度の比 16 8.β2マイクログロブリン(β2MG) 17 9.腎機能障害の型 18 10.腎機能増悪因子とl/cr 19 11.腎不全の重症度分類 20 12.腎機能障害時の病態 21 13.尿毒症毒素(uremic toxins) 22 14.尿毒症の病像 23 15.保存期腎不全の治療方針 24 16.慢性腎不全の治療的分類 25 III.急性腎不全 1.急性腎不全の原因 28 2.急性腎不全の成因 29 3.腎前性高窒素血症の成因 30 4.急性腎不全(腎性)の成因 31 5.急性腎不全の病期分類(乏尿性型) 32 6.急性腎不全の鑑別 33 7.横紋筋融解症による急性腎不全 34 8.O-157による溶血性尿毒症症候群(HUS) 35 9.急性腎不全の治療指針 36 IV.慢性腎不全 1.慢性腎不全の定義 38 2.慢性腎不全の原因 39 3.慢性腎不全の病期分類(Seldin) 40 4.慢性腎不全の症候と検査異常 41 5.保存期慢性腎不全の治療方針 42 6.慢性腎不全に対する透析適応基準 43 7.透析療法の目的 44 8.透析患者への薬物療法 45 9.体液・電解質の作用 46 10.透析患者の水分バランス 47 11.体液量過剰の徴候と治療方針 48 12.体液量欠乏の原因と徴候 49 13.Na平衡と調節因子 50 14.透析患者にみられるNa濃度異常の原因 51 15.K平衡と調節因子 52 16.血清カリウム濃度異常の症候 53 17.透析患者における血清K濃度異常の原因 54 18.血清Ca濃度異常の測定 55 19.Ca代謝の調節機構 56 20.透析患者におけるCa濃度異常の原因 57 21.透析患者における血清P濃度異常の原因 58 22.腎不全における代謝性アシドーシスの成因 59 V.血液浄化法の基礎 1.物質輸送の原理 62 2.透析の原理 63 3.血液浄化法の種類 64 4.血液浄化と除去物質 65 5.血液浄化法と溶質除去性能 66 6.血液浄化法の選択 67 7.血液透析療法の構成 68 8.ECUM(extra corporeal ultrafiltration method) 69 9.高ナトリウム透析法 70 10.血液濾過法(hemofiltration:HF) 71 11.血液濾過法の適応と注意事項 72 12.血液濾過用補充液組成(理論値) 73 13.血液透析濾過法(hemodiafiltration:HDF) 74 14.on line HDF 75 15.push and pull HDF 76 16.血液濾過・血液透析濾過法で改善が期待される症候 77 17.バイオフィルトレーション 78 (アセテートバイオフィルトレーションAFBF) 18.血液交換療法 79 19.二重濾過血漿交換法(DFPP) 80 20.LDL吸着療法 81 VI.血液透析療法 1.血液透析法 84 2.ブラッドアクセス 85 3.ブラッドアクセスの条件 86 4.外シャントの特徴 87 5.内シャントの特徴 88 6.ブラッドアクセスの合併症(1) 89 7.ブラッドアクセスの合併症(2) 90 8.透析液供給装置・水処理装置 91 9.水道水に含有する有害物質と水質基準 92 10.透析液 93 11.低Ca透析液の適応 94 12.アセテート(酢酸)の副作用 95 13.透析液の種類(理論値) 96 14.顆粒型透析液の特徴 97 15.顆粒型透析液組成(調整後の電解質濃度)理論値 98 16.エンドトキシン(endotoxin:ET)とは 99 17.エンドトキシン除去対策 100 18.ダイアライザの種類と性能評価 101 19.透析膜の種類 102 20.透析膜の必要条件 103 21.拡散に関する因子 104 22.限外濾過係数,限外濾過率 105 23.ダイアライザの評価 106 24.高性能膜ダイアライザ 107 25.血液透析療法の膜選択 108 26.高性能膜ダイアライザの効果 109 27.ダイアライザの選択法 110 28.抗凝固剤の種類 111 29.ヘパリンの種類と特徴 112 30.ヘパリンの問題点 113 31.ヘパリンの特徴と使用法 114 32.低分子ヘパリンの特徴と使い方 115 33.メシル酸ナファモスタット(フサン) 116 34.合成抗トロンビン薬: アルガトロバン 117 35.局所ヘパリン化法 118 36.凝固時間の測定の種類と特徴 119 37.出血傾向時の抗凝固法 120 38.ダイアライザ・回路内凝血の原因 121 39.透析条件の設定 122 40.血液透析操作手順 123 41.透析治療前のチェック項目 124 42.透析治療中の点検事項 125 43.透析治療後のチェック項目 126 44.ダイアライザの残血対策のチェック 127 VII.腹膜透析療法 1.腹膜透析法とは 130 2.腹膜透析法の原理 131 3.CAPDの特徴 132 4.CAPDの利点 133 5.CAPDの利点・欠点 134 6.腹膜透析法の物質移動の式 135 7.腹膜クリアランス 136 8.腹膜平衡試験の操作 137 9.腹膜平衡試験の解釈 138 10.CAPD用腹膜透析液組成(理論値) 139 11.腹膜透析の合併症 140 12.CAPD腹膜炎の原因 141 13.CAPD腹膜炎の診断 142 14.CAPD腹膜炎の治療 143 15.難治性CAPD腹膜炎の管理 144 16.硬化性被嚢性腹膜炎の成因と影響 145 VIII.透析療法の合併症・併発症ー病態と治療指針 1.腎不全の合併症・併発症 148 2.主要な長期透析の合併症・併発症 149 3.透析困難症とは 150 4.透析困難症の概念と対策 151 5.不均衡症候群 152 6.不均衡症候群・透析困難症への対策 153 7.循環器系合併症の関連因子 154 8.腎不全の高血圧の成因 155 9.腎不全の血圧異常 156 10.腎不全の高血圧の型と治療指針 157 11.透析患者の高血圧の治療指針 158 12.降圧薬の種類と薬物動態 159 13.透析治療中の低血圧症の成因 160 14.慢性低血圧症の成因 161 15.長期透析の持続性低血圧症の成因 162 16.透析患者の低血圧の対策 163 17.腎不全にみられる心不全の原因 164 18.ドライウエイト(基準体重) 165 19.末梢循環不全の成因 166 20.末梢循環障害 167 21.不整脈の原因 168 22.腎不全と動脈硬化症の進展 169 23.動脈硬化症の成因 170 24.虚血性心疾患の成因 171 25.虚血性心疾患の成因と特徴 172 26.虚血性心疾患の疑われる透析患者の検査チャート 173 27.心房性Na利尿ペプタイド 174 28.腎性貧血の成因 175 29.赤血球産生の調節機構 176 30.腎性貧血の対策 177 31.エリスロポエチンの投与法 178 32.エリスロポエチンの副作用 179 33.エリスロポエチンによる高血圧の成因 180 34.エリスロポエチン抵抗性の病態 181 35.慢性透析患者の鉄欠乏の判定 182 36.DFO試験 183 37.腎性骨症の概念 184 38.腎性骨症の成因 185 39.副甲状腺ホルモン(PTH)の測定 186 40.i-PTHによる副甲状腺機能分類 187 41.骨のリモデリング 188 42.骨代謝のマーカー 189 43.二次性副甲状腺機能亢進症 190 44.二次性副甲状腺機能亢進症の成因 191 45.無形成骨の成因 192 46.副甲状腺機能亢進症と機能低下症 193 47.ビタミンDパルス療法 194 48.経皮的エタノール注入法 195 49.二次性副甲状腺機能亢進症に対する手術療法の適応 196 50.異所性石灰化の成因と影響 197 51.透析アミロイドーシス(腎不全アミロイドーシス) 198 52.透析アミロイドーシスの成因 199 53.補体活性化の影響 200 54.透析アミロイドーシスの症候 201 55.腎不全アミロイドーシス・透析アミロイドーシスの診断 202 56.手根管症候群の症候 203 57.破壊性脊椎関節症 204 58.アミロイド骨・関節症 205 59.透析アミロイドーシスの対策 206 60.β2MG吸着器(リクセル) 207 61.透析脳症の成因(アルミニウム脳症) 208 62.透析患者にみられる神経・筋肉症状 209 63.尿毒症性末梢神経障害 210 64.腎不全にみられる自律神経障害 211 65.薬物性脳障害 212 66.腎不全と免疫能の低下(免疫不全) 213 67.腎不全と免疫能の低下 214 68.易感染性の原因 215 69.血液-膜間相互作用 216 70.モノカイン仮説(インターロイキン仮説) 217 71.エンドトキシンとサイトカイン 218 72.補体活性化の影響 219 73.腎不全の呼吸機能の異常 220 74.肺水腫・肺うっ血の原因と症候 221 75.多嚢胞化腎の成因 222 76.多嚢胞化腎の影響 223 77.微量金属 224 78.微量金属の異常 225 79.亜鉛欠乏症 226 80.アルミニウム骨症 227 81.DFO投与法 228 82.掻痒症の機序 229 83.腎不全の掻痒症の成因と対策 230 84.掻痒症に用いられる薬剤 231 85.腎不全における内分泌異常の原因 232 86.ビタミンDの作用 233 87.ビタミンDの代謝 234 88.腎不全におけるビタミンD代謝異常 235 89.女性化乳房症,乳汁分泌異常 236 90.腎不全にみられる主要消化器病変 237 91.腸管機能に影響する因子 238 92.透析患者の脂質異常の特徴 239 93.慢性腎不全のリポ蛋白の特徴 240 94.高脂血症の対策 241 95.腎不全の糖質代謝 242 IX.糖尿病性腎症と透析療法 1.糖尿病と糖尿病性腎症 244 2.糖尿病の合併症 245 3.糖尿病性腎症の臨床経過 246 4.糖尿病性腎症の特徴と透析導入の問題点 247 5.糖尿病性腎不全に対する透析療法の適応基準案 248 (厚生省糖尿病研究班) 6.糖尿病性腎不全における透析困難症の成因 249 7.糖尿病性神経・筋障害 250 8.糖尿病性腎症と代謝異常の治療方針 251 9.糖尿病性透析患者の血糖コントロール目標 252 X.高齢者の透析療法 1.高齢者診療上の注意点 254 2.高齢者の身体的特徴 255 3.体液量と加齢の影響 256 4.高齢者の循環器系問題 257 5.高齢者の精神心理的特徴 258 6.高齢者の透析療法の方針 259 7.高齢者の血液透析法の問題点 260 8.高齢者の食事療法の問題点 261 9.高齢者の治療目標―cureよりもcare 262 XI.食事療法と検査の評価 1.腎不全における食事療法 264 2.透析患者の食事療法の意義 265 3.透析食の内容 266 4.タンパク質摂取量の原則 267 5.水分摂取量の原則 268 6.塩分摂取量の原則 269 7.カリウム摂取量の原則 270 8.リン摂取量の注意 271 9.透析患者への高カロリー輸液(TPN) 272 10.栄養評価法 273 11.検査の頻度(例) 274 12.血液検査の目標値(週3回の血液透析療法治療前値) 275 13.透析の効果に関係する因子 276 14.1週間のBUNの変動と尿素除去率 277 15.Urea Kinetics の原理 278 16.標準化透析量(Kt/v)の簡易式 279 17.タンパクの異化率 280 18.TACBUNの意味 281 XII.適正透析,外科手術 1.適正透析 284 2.適正透析の目標 285 3.生体適合性 286 4.補体活性化の影響 287 5.透析膜と血小板付着 288 6.透析患者にみられる外科手術 289 7.透析患者の外科手術の注意点 290 XIII.透析時の事故・偶発症の対策 1.血液透析治療の事故の原因 292 2.天災・事故の対策 293 3.血液透析治療中の事故・偶発症の対策(1) 294 4.血液透析治療中の事故・偶発症の対策(2) 295 5.血液透析治療中の事故・偶発症の対策(3) 296 6.低血圧発作・ショックの対策 297 7. 不整脈の対策 298 付表 1.透析期腎不全の抗菌薬使用の原則 300 2.透析期腎不全の薬物使用(1) 301 3.透 析期腎 不全の薬物使用(2) 302 4.透析期腎不全の薬物使用(3) 303 5.透析期腎不全の薬物使用(4) 304 6.透析低血圧症の薬物療法 305 7.抗不整脈薬 306 8.抗高脂血症治療薬 307 9.腎不全用アミノ酸製剤の内容 308 10.高カロリー輸液 309 索引 3110 0 0
内容説明
透析医療に必要な知識のキーポイント、データ、注意点、ノウハウなどを収録した便覧。巻末に索引がある。
目次
1 透析療法の現状―統計的資料
2 腎臓秒の病態と診療指針
3 急性腎不全
4 慢性腎不全
5 血液浄化法の基礎
6 血液透析療法
7 腹膜透析療法
8 透析療法の合併症・併発症―病態と治療指針
9 糖尿病性腎症と透析療法
10 高齢者の透析療法
11 食事療法と検査の評価
12 適正透析、外科手術
13 透析時の事故・偶発症の対策
-

- 和書
- 中世王権の形成と摂関家