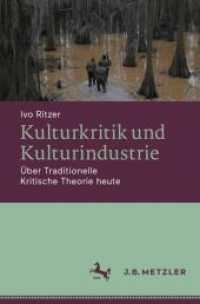出版社内容情報
《内容》 生体におけるカルシウム代謝は大変複雑な仕組みで営まれており,一般に難解なものとされているが,本書はその基礎から診断法,治療法の実際をわかり易く解説したものである.とくに最近,高カルシウム血症の治療薬が次々と開発され,従来なすすべもなかった悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症も十分にコントロールすることが出来るようになっており,その治療法を実践的に紹介している.その最新情報や自験例,研修医から受ける質問によるQ&Aを盛り込んで,日常の診療に役立つための解説書として著わされたものである. 序 最近,わが国では高齢社会を迎え,いわゆる老年病,特に骨粗鬆症等のカルシウム代謝異常に対する関心が高まっているが,今度東京女子医科大学内分泌センターの佐藤幹二博士が「カルシウム代謝異常 新しい診断法と治療法」という本を出版されるはこびとなったことは,この分野の研究のpioneerの一人として,大変喜んでいる次第である. 佐藤博士は昭和45年東京大学医学部医学科を卒業後,昭和47年に同大学第三内科の研究生となり,昭和53年から2年間米国NIH研究所およびConnecticut大学にてDr. RobbinsおよびDr. Raiszの指導のもとに甲状腺ホルモン及び骨代謝の研究に従事され,帰国後東京女子医科大学内分泌センター助教授として,日夜カルシウム代謝の研究に精力的に取り組んでおられる現在最も脂の乗り切った新進気鋭の学者である.生体におけるカルシウム代謝は大変複雑な仕組みで営まれており,一般には大変難解なものとされているが,本書ではその基礎および臨床について一般の医師にもきわめてわかりやすく解説されている. 本書の特長としてまず第1にあげられることは,自験例についての解説が非常に豊富であること,第2は随所にQ&Aの項目が設けられており,その処々に佐藤博士らしい大変ユニークな解説がなされていることで,そのいずれもが日常の診療において役に立つものであろう. 高カルシウム血症に関する解説は佐藤博士のlife workを十分に反映させた力作であり,最近の知見の紹介とともにご自身の新しい考え方が述べられている.Bisphosphonateについては本書の副題でもあり,その作用機序,使用法等につき詳しく述べられている.本書はカルシウム代謝異常症に関する最新の情報を提供してくれるきわめて優れた解説書であり,臨床医にとり大変役立つものと信ずる. 1995年1月11日 折茂 肇 はじめに 最近,高カルシウム血症の治療薬(bisphosphonate剤)が次々と開発されており,従来は,なすすべもなかった悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症でも十分にコントロールすることが可能になってきている.著者は,このような骨吸収抑制剤の治験にたずさわる機会に再三恵まれ,bisphosphonate剤の切れ味のすばらしさを十分に体験することができた.しかし,同時に受持ち医のカルシウムに対する関心のなさやカルシウム代謝の無理解さに,落胆させられる機会も多かった.これは,従来の成書には難解なものが多く,また,内科指導医のなかにもカルシウムの恐ろしさを知らないものが多いことも一因のようである. このような義憤を感じていたところ,中外医学社から,bisphosphonate剤の紹介書を依頼されたので,渡りに船とばかりに引き受けた次第である.最初に,カルシウム代謝の要点を簡潔に記載したあと,最新の診断法や治療法の進歩をまとめてみた.特に,bisphosphonate剤による悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症の治療法をできるだけ実戦的に紹介した.なお,研修医からよく受ける質問も質疑応答形式で一部まとめておいた. この小著が,患者の診断や治療にあけくれている第一線の臨床医の方々に参考になり,ひいては高カルシウム血症のためにquality of lifeを著しく損なっている患者さんの治療に少しでも役にたてば幸である. 最後に,幸いなことに折茂肇東大教授より序文をいただくことができた.本書は,bisphosphonate剤の治験総括医師を努められた折茂先生より治験世話人のひとりにしていただいたお陰で世に出たようなものであり,この場を借りて,厚く御礼申し上げます. 1994年12月 著者 《目次》 目次 第1章 カルシウム代謝の基礎 A.カルシウムとリン代謝 1 1.血中CaおよびPの正常値 1 2.補正カルシウム値:測定値を読むときの注意 2 3.尿中CaおよびP排泄量の正常値 3 4.血中カルシウムのコントロール機構 3 カルシウム代謝 3 B.副甲状腺ホルモン 5 1.PTHの生物活性 5 a)PTHの腎尿細管に及ぼす作用 6 b)PTHの骨吸収作用 8 c)PTHの消化管に対する作用 8 2.PTHの代謝 9 3.PTHの血中濃度 10 C.カルシトニン 11 D.ビタミンD 14 a)D3とD2 14 b)ビタミンD代謝の制御機構 16 c)ビタミンDの生物活性 17 d)ビタミンDの作用 19 文献 28 第2章 高カルシウム血症 A.高カルシウム血症の臨床症状 31 1.軽度の高カルシウム血症 31 2.中等度の高カルシウム血症 31 3.高度の高カルシウム血症 33 4.超高度の高カルシウム血症 33 B.高カルシウム血症患者の診断法 34 C.高カルシウム血症の鑑別 34 1.PTHが高値を示す高カルシウム血症 38 2.PTHがほぼ正常(またはやや高値)の高カルシウム血症 39 3.PTHが低値を示す高カルシウム血症 42 4.カルシウムを結合する蛋白の増加によるもの 45 5.原因不明の高カルシウム血症 45 文献 47 第3章 原発性副甲状腺機能亢進症 A.PHPの病態 51 1.高カルシウム血症 51 2.高カルシウム尿症 53 3.低リン血症 53 4.代謝性アシドーシス 53 B.血中PTH濃度と高カルシウム血症 53 C.PHPの臨床症状 56 1.生化学型 56 2.腎結石型 56 3.骨病変型 57 4.特殊な合併症 58 a)骨軟化症 58 b)偽痛風の発作 58 c)腺腫の梗寒 58 d)急性膵炎 58 e)高カルシウム血症クリーゼ 62 D.PHPと骨密度 62 E.内科的な治療法と手術の適応 63 1.無症候性PHP 63 2.腎結石型 64 3.骨病変型 65 4.高カルシウム血症クリーゼ 65 F.PHPの病理と手術術式 67 1.副甲状腺の腺腫 67 2.副甲状腺の過形成 67 3.副甲状腺癌 67 文献 69 第4章 悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症 A.MAHの発生頻度 72 B.MAHの成因 74 1.悪性腫瘍の産生する骨吸収促進因子 74 a)PTHrP産生腫瘍 75 b)OAF産生腫瘍 77 c)PTHrP+OAF産生腫瘍 78 2.悪性腫瘍の産生するPTHrP以外の骨吸収促進因子 79 a)IL-1 79 b)IL-6 79 c)TGF-α 80 d)TNF-α 80 e)活性型ビタミンD 81 f)PTH 81 C.MAHの診断法 81 1.血中PTHrP N末端部フラグメントの測定 82 2.PTHrP C末端フラグメントの測定 84 D.MAHの治療法 84 1.一般的な現行の治療法 84 軽度の高カルシウム血症のある場合 84 2.新しいMAH治療法 89 Bisphosphonate剤 89 3.将来の特異的なMAH治療法 91 a)PTHrP産生を抑制する方法 93 b)抗PTHrPモノクローナル抗体による受動免疫法 93 c)PTH/PTHrP受容体に対する阻害型抗体 93 d)その他の特異的治療法 94 文献 96 第5章 高カルシウム血症クリーゼ 1.臨床症状 102 2.鑑別診断 103 3.入院当日にするべき検査 105 4.高カルシウム血症クリーゼの治療 107 文献 112 第6章 Bisphosphonate剤 A.Bisphosphonate開発の歴史 114 B.Bisphosphonateの作用機序 116 C.Bisphosphonateのpharmacokinetics 118 D.Bisphosphonateの臨床応用 119 a)悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症 119 b)悪性腫瘍の骨転移 119 c)Paget病 119 d)骨粗鬆症 120 e)その他の臨床応用 120 E.Bisphosphonate剤の実際の使用法とMAHに対する効果 125 F.副作用 127 文献 133 第7章 高カルシウム血症患者の輸液 136 第8章 ビタミンD中毒症 A.活性型ビタミンDの生物活性 142 B.種々の活性型ビタミンD過剰症 142 1.外因性のビタミンD中毒 144 a)1,25-(OH)2D3 144 b)1α-OHD3の過剰摂取 144 c)ビタミンD中毒症 144 2.内因性のビタミンD中毒症 147 a)Granulomatous disease 147 b)PTHrP産生腫瘍 148 c)活性型ビタミンD産生性の悪性腫瘍 149 C.1,25-(OH)2D3産生性の造血器腫瘍 149 1.高カルシウム血症をおこす疾患 149 2.1,25-(OH)2Dの産生細胞 149 D.腎尿細管型とサルコイド型1α-hydroxylaseの性質 150 E.1,25-(OH)2D3高値を呈するMAHの治療法 152 文献 153 第9章 低カルシウム血症 A.副甲状腺機能低下症 156 1.PTH分泌不足による副甲状腺機能低下症 156 a)本症の病態 156 b)活性型ビタミンDの補充療法 159 2.PTH不応症:偽性副甲状腺機能低下症 161 B.慢性腎不全に伴う低カルシウム血症 161 C.その他の低カルシウム血症 162 a)低マグネシウム血症 162 b)敗血症 162 c)急性膵炎 163 d)悪性腫瘍に伴う低カルシウム血症 163 D.テタニーのときの処置 165 文献 166 第10章 骨軟化症 1.診断 168 2.一般検査データ 168 3.骨軟化症の確定診断 170 4.鑑別疾患 171 a)低リン血症性ビタミンD抵抗性クル病 171 b)Oncogenic osteomalacia 172 c)薬剤による骨軟化症 173 d)原発性副甲状腺機能亢進症 173 文献 174 第11章 骨粗鬆症 A.現行の治療薬 176 1.カルシウム 176 2.ビタミンD 177 3.カルシトニン 179 4.エストロジェン 180 5.イプリフラボン(オステン) 182 B.現在,開発中の骨粗鬆症薬剤 182 1.Vitamin K 182 2.Bisphosphonate 182 3.その他の新しい治療薬 183 文献 188 付表 191 索引 199