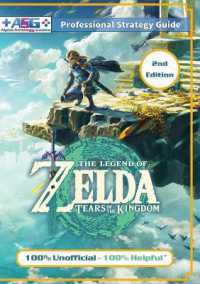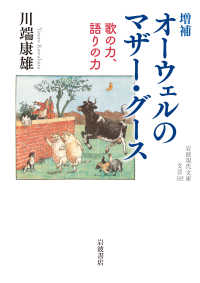出版社内容情報
《内容》 本書は検査値の読み方,特に境界値または疑惑値と呼ばれる“あやしい数値”をどう読み,いかに対処するかを具体的に示した書として,長年多くの読者の支持を得てきたものの全面改訂版である.今回は従来の検査項目を新しいニーズに応える様,書き改めると共に,40項目余を追加,更に高齢者の測定値の問題についても極力触れるようにした.検査値をキメ細く読み,対応するための臨床検査診断のマニュアルである. 初版の序 病気の診断や予後決定には,正確な病歴や診察所見が重要な役割を演じることはいうまでもないが,20世紀とくにその後半の臨床検査のめざましい進歩は,診断や予後判定の水準を驚くべきほどに高めたことは誰もが認める事実である. 検査値の中には,病状によりその変動が目立つものと,目立たないものとがある.後者の場合でも,検査方法が進歩して,その目盛が細かく出されれば出されるほど,わずかな変動も診断学的意義をもってくる. また,病気が早期に発見されるにつれて,検査値の変動が目立たないこともしばしばみられる事実である. 病状が落ちつく過程において,検査値の改善がどのような傾斜でみられるか,それが急激に正常値に近づく場合と,徐々に改善される場合とがあるが,それは病気の性質や検査内容によってまちまちである.そのような場合に,わずかの変動が,どのような診断学的,または予後学,治療学的の意味をもってくるかを正しく判別することが必要になってくる わずかな検査値の動きを,あたかも科学天秤の針のゆれを拡大してみる時のようなきめ細かさで注視し,その意義を正しくつかむためには,病気ならびに検査法そのものに対する学理的,技術的な細かい知識と経験が要請される. このように考えると,まずわれわれが大ざっぱに心得ていると思っている正常値を,ここでもう一度細かく再検討し,その検査値の生理的変動,年齢差による変動,検査方法による変動などを正しく心得ておかなければならない. もちろん,その検査上の誤り,すなわち技術的誤りや誤差,検体の取り扱い上に起る問題,ならびに偽陽(陰)性の可能性についての知識をも心得てこそ,高いレベルの診断技術が獲得されるのである. そのほか,いわゆる境界値といわれるものの正確な把握はどうすれば可能であろうか.境界値といわれるものも正常から異常への境界値と,異常から正常への境界値では,その意味は診断や治療の観点からは明らかに区別されなければならない. 境界値の読みいかんによって,治療を早期にスタートさせたり,患者に安静を命じたり,またその逆に,治療を中止し,もとの生活に早く戻すということもなされるのである. また境界値が得られた時,いつの時期に同じ検査の再検を行うべきか,また他に組み合わせる検査のセットとして何々が適切であるか,境界値が薬物治療上の影響として現れるかどかなど,臨床医学上の重要な問題が数多く提起されるわけである. 以上のようなことをふまえて,検査が正しく行われたか否かを監視し,検査値のもつ正確さや誤差を心得,そのわずかな変動を注視して,検査室からの報告書の背後にある意味を読みとることは,臨床検査とベッドサイドでの患者の観察経験を長年もっている専門家によってこそ正しくなされるものといえよう. その意味で,本書は数多い臨床検査を整理して,それぞれの専門家に分担してもらい,専門家にしてはじめて自信をもって発表できる有益な学問的,経験的情報を収集した次第である.ところが,医療がいつまでも経験にのみ頼ることは許されない.客観化できるものはできるだけ客観的に整理することが必要で,近年,推計学的ならびに情報科学的な取り扱いが注目されはじめているのはそのためである.貴重な経験の上にきめ細かい観察がなされ,さらにそれに科学性をもたせることによって一層その価値が増すものであろう.そこで関連した基礎的な論文を併せて収録したわけである. 本書はまた,検査値の解説だけでなく,そのわずかな変動値から,早期に患者の生活を指導し,適切な治療をするための示唆が専門家によってなされている. 最後に,この検査のわずかな異常値,または境界値をもって,あるいは疑陽性反応をもって,いたずらに患者にiatrogenic deseaseをおいかぶせる不幸を作らないためにも,本書は臨床医の適切な指導書となることを信じて疑わない. 1972年6月 日野原重明 河合 忠 《目次》 目次 〔総論〕 1.正常値(基準値)と境界値とカットオフ値 〈河合 忠〉 2 2.小児の正常値 〈小島祥子〉 8 3.高齢者の正常値 〈河合 忠〉12 4.検査結果の共通表示法 〈丹羽正治 河合 忠〉18 〔各論〕 I.尿検査 1.比重・浸透圧/尿濃縮試験 〈酒井 紀〉 24 2.総蛋白 〈酒井 紀〉 26 3.BENCE JONES蛋白 〈河合 忠〉 29 4.微量アルブミン 〈長坂昌一郎 岩本安彦〉 31 5.尿糖(グルコース) 〈長坂昌一郎 岩本安彦〉 34 6.ケトン体 〈長坂昌一郎 岩本安彦〉 37 7.クレアチニン 〈浅野 泰〉 39 8.クレアチニン-クリアランス 〈浅野 泰〉43 9.N-acetyl β-D-glucosaminidase(NAG) 〈伊藤喜久〉 48 10.潜血・ヘモグロビン 〈酒井 紀〉 52 11.尿沈渣 〈伊藤機一〉 55 12.PSP排泄試験 〈酒井 紀〉 62 II.便検査・胃酸検査 1.便潜血反応 〈石森 章 川村 武〉 64 2.PABA排泄試験(PFD試験) 〈石森 章 川村 武〉 67 3.胃液検査 〈石森 章 川村 武〉 70 III.穿刺液(胸水・腹水)検査 1.比重 〈椎名晋一〉 74 2.蛋白 〈椎名晋一〉 76 3.細胞数と細胞の種類 〈椎名晋一〉 77 IV.血液学的検査(1) 1.赤血球数・ヘマトクリット 〈桑島 実〉 78 2.ヘモグロビン 〈桑島 実〉 84 3.赤血球指数(MCV・MCHC) 〈桑島 実〉 88 4.網赤血球数 〈桑島 実〉 92 5.血小板数 〈櫻川信男〉 96 6.白血球数・白血球分類 〈桑島 実〉 99 7.リンパ球サブセット 〈桑島 実〉 106 8.好酸球数 〈桑島 実〉 110 9.赤沈 〈磯貝行秀〉 112 10.血液粘度 〈磯貝行秀〉 116 11.赤血球抵抗試験 〈藤井寿一〉 119 V.血液学的検査(2)凝結・線溶 1.毛細血管抵抗試験 〈櫻川信男〉 123 2.出血時間 〈櫻川信男〉 125 3.血小板機能 〈櫻川信男〉 129 4.部分トロンボプラスチン時間(PTT・APTT) 〈小池克昌 福武勝幸〉 133 5.プロトロンビン時間(PT) 〈小池克昌 福武勝幸〉 138 6.トロンボテスト 〈福江英尚 福武勝幸〉 141 7.ヘパプラスチンテスト 〈福江英尚 福武勝幸〉 144 8.フィブリノゲン 〈松田道生〉 147 9.可溶性フィブリンモノマーとフィブリンペプチドA 〈松田道生〉 149 10.アンチトロンビンIII(AT III) 〈朝倉英策 松田 保〉 150 11.プロテインC・プロテインS 〈朝倉英策 松田 保〉 154 12.FDP・DダイマーおよびBβ15-42 〈松田道生〉 157 13.β-トロンボグロブリン 〈朝倉英策 松田 保〉 159 14.凝血因子定量 〈新井盛夫 福武勝幸〉 161 15.PIVKA 〈新井盛夫 福武勝幸〉 166 16.プラスミノゲン・α2プラスミンインヒビター・プラスミン-α2PI複合体 〈朝倉英策 松田 保〉 168 VI.免疫学的検査(1)ウイルス性感染症 1.単純ヘルペスウイルス抗原,抗体 〈中村良子〉 172 2.EBウイルス抗体・PAUL-BUNNELL反応 〈中村良子〉 175 3.サイトメガロウイルス抗体 〈中村良子〉 179 4.風疹ウイルス抗体 〈中村良子〉 181 5.ロタウイルス抗原,抗体 〈中村良子〉185 6.A型肝炎ウイルス抗体 〈清澤研道〉 188 7.B型肝炎ウイルス関連マーカー 〈清澤研道〉 190 8.C型肝炎ウイルス抗体 〈清澤研道〉 195 9.ATLウイルス抗体 〈田口博國 三好勇夫〉 200 10.HIV抗体 〈玉川重徳〉 203 VII.免疫学的検査(2)非ウイルス性感染症 1.C反応性蛋白(CRP) 〈河合 忠〉 207 2.シアル酸・ムコ蛋白 〈臼井敏明〉 211 3.寒冷凝集素反応 〈雨宮洋一〉 213 4.クラミジア抗原,抗体 〈大里和久〉 217 5.梅毒血清反応 〈大里和久〉 219 6.淋菌抗原検査 〈大里和久〉 223 7.トキソプラズマ抗体 〈中村良子〉 225 8.マイコプラズマ抗原,抗体 〈中村良子〉 227 9.溶連菌抗原,抗体 〈河合 忠〉 230 10.エンドトキシン 〈吉田 稔 大林民典〉 235 11.真菌関連抗原,抗体 〈大林民典〉 238 VIII.免疫学的検査(3)自己抗体・その他 1.抗サイログロブリン抗体・抗甲状腺マイクロゾーム抗体 〈網野信行〉 240 2.TSH受容体抗体 〈小林 功〉 244 3.リウマトイド因子 〈廣瀬俊一〉 247 4.LE細胞・LEテスト 〈吉田 浩〉 250 5.ANA-抗核抗体 〈吉田 浩〉 252 6.抗DNA抗体 〈吉田 浩〉 256 7.抗SSA/R0抗体・抗SSB/La抗体 〈吉田 浩〉 258 8.抗Sm抗体 〈吉田 浩〉 260 9.抗U1-RNP抗体 〈吉田 浩〉 262 10.抗Scl-70抗体 〈吉田 浩〉 265 11.抗血小板抗体 〈雨宮洋一〉 267 12.抗白血球抗体 〈雨宮洋一〉 271 13.抗赤血球抗体・COOMBS試験 〈雨宮洋一〉 276 14.抗マイトコンドリア抗体 〈網野信行 西山 沢〉 283 IX.ホルモン検査・その他の生理活性物質 下垂体 1.GH・ソマトメジン 〈赤水尚史 森 徹〉 285 2.ACTH 〈赤水尚史 森 徹〉 290 3.LH・FSH 〈赤水尚史 森 徹〉 294 4.プロラクチン 〈赤水尚史 森 徹〉 297 5.TSH 〈小林 功〉 299 6.ADH 〈瀬谷 彰 吉田 尚〉 304 甲状腺・副甲状腺 7.総サイロキシン(T4)および総トリヨードサイロニン(T3) 〈小林 功〉 308 8.遊離サイロキシン(FT4)および遊離トリヨードサイロニン(FT3) 〈小林 功〉 312 9.TBG(サイロキシン結合グロブリン) 〈小林 功〉 316 10.サイログロブリン(Tg) 〈小林 功〉 319 11.副甲状腺ホルモン(PTH) 〈富田明夫〉 322 12.カルシトニン 〈富田明夫〉 327 副腎皮質 13.レニン・アンギオテンシン・アルドステロン 〈木村 聡 尾形 稔〉 329 14.コルチゾール 〈尾形 稔〉 334 15.17-OHCS 〈尾形 稔〉 337 16.17-KS・17-KS分画 〈尾形 稔〉 341 副腎髄質 17.血漿,尿中カテコールアミン 〈中井利昭〉 344 18.尿中メタネフリン2分画(メタネフリン・ノルメタネフリン) 〈中井利昭〉 347 19.尿中VMA,HVA 〈中井利昭〉 349 性腺・胎盤 20.エストロゲン・プロゲステロン 〈藤原敏博 武谷雄二〉 351 21.テストステロン 〈藤原敏博 武谷雄二〉 355 22.hCG・hCGサブユニット・免疫学的妊娠反応 〈藤原敏博 武谷雄二〉 358 23.尿中エストリオール 〈藤原敏博 武谷雄二〉 362 X.腫瘍マーカー 1.AFP 〈大倉久直〉 364 2.PIVKA-2 〈大倉久直〉 368 3.CEA 〈大倉久直〉 372 4.シアリルルイスA糖鎖抗原(CA19-9・KMO1) 〈大倉久直〉 376 5.CA125とCA130 〈高見澤裕吉 稲葉憲之 太田順子 深澤一雄〉 380 6.BFP(塩基性フェトプロテイン) 〈石井 勝〉 385 7.PAP(前立腺性酸性フォスファターゼ) 〈松岡 啓〉 387 8.γ-Sm 〈松岡 啓〉 390 9.PA(前立腺特異抗原) 〈松岡 啓〉 392 XI.血液科学検査(1)酵素 1.酸性フォスファターゼ 〈松岡 啓〉 394 2.CK・CKアイソザイム 〈高木 康 五味邦英〉 396 3.AST(GOT)ALT・(GPT) 〈飯野四郎〉 402 4.アルカリホスファターゼ 〈菅野剛史〉 407 5.LDHおよびLDHアイソザイム 〈尾形 稔 杉田 収〉 412 6.γ-GTP 〈村脇義和 川崎寛中〉 416 7.LAP 〈村井哲夫〉 420 8.コリンエステラーゼ 〈孝田雅彦 川崎寛中〉 424 9.アミラーゼおよびアミラーゼアイソザイム 〈尾形 稔 杉田 収〉 427 10.リパーゼ 〈尾形 稔 杉田 収〉 431 11.血中エラスターゼ1 〈木村 聡 尾形 稔〉 433 12.グルコース-6-リン酸脱水素酵素 〈藤井寿一〉 436 13.アンギオテンシン変換酵素(ACE) 〈泉 孝英〉 439 14.TdT(ターミナルトランスフェラーゼ) 〈佐々木龍平〉 441 XII 血液科学検査(2)蛋白・窒素化合物 1.血清総蛋白 〈河合 忠〉 443 2.血清蛋白分画 〈河合 忠〉 447 3.プレアルブミン 〈大谷英樹〉 450 4.α1アンチトリプシン 〈大谷英樹〉 452 5.α1酸性糖蛋白 〈大谷英樹〉 454 6.α1マイクログロブリン 〈伊藤喜久〉 456 7.α2マクログロブリン 〈大谷英樹〉 459 8.ハプトグロビン 〈大谷英樹〉 461 9.セルロプラスミン 〈大谷英樹〉 463 10.血清補体価とC3,C4など補体系蛋白 〈稲井眞弥〉 465 11.血中,尿中β2-マイクログロブリン 〈伊藤喜久〉 472 12.免疫グロブリン (A,G,M,D) 〈河野均也〉 474 13.IgE 〈河野均也〉 479 14.クリオグロブリン 〈河野均也〉 483 15.ミオグロビン 〈高木 康〉 485 16.ミオシン軽鎖I 〈高木 康〉 489 17.プロコラーゲンIIIペプチド 〈河西浩一 石田俊彦〉 492 18.IV型コラーゲン・7S 〈河西浩一 石田俊彦〉 494 19.尿素窒素 〈浅野 泰〉 496 20.クレアチニン 〈浅野 泰〉 500 21.尿酸 〈赤岡家雄〉 504 22.血酸(血液)アンモニア 〈菅野剛史〉 508 23.アミノ酸分画 〈菅野剛史〉 510 XIII.血液科学検査(3)糖代謝・有機酸 1.グルコース(血糖) 〈松田文子〉 513 2.耐糖能試験(糖付加試験) 〈松田文子〉 518 3.グリコヘモグロビン(HbA1・HbA1c) 〈松田文子〉 522 4.フルクトサミン 〈松田文子〉 525 5.1,5-アンヒドログルシトール(1,5AG) 〈松田文子〉 527 6.インスリン(IRI) 〈岩本安彦〉 530 7.Cペプチド(CPR) 〈岩本安彦〉 535 8.グルカゴン(IRG) 〈岩本安彦〉 538 9.乳酸・ピルビン酸 〈河西浩一 石田俊彦〉 540 XIV.血液科学検査(4)脂質・色素関連物質・ビタミン 1.総コレステロール 〈中村治雄〉 543 2.HDL-コレステロール 〈中村治雄〉 547 3.β-リポ蛋白(LDL) 〈板倉弘重〉 551 4.アポリポ蛋白 〈板倉弘重〉 555 5.トリグリセライド(TG) 〈中村治雄〉 560 6.遊離脂肪酸(FFA) 〈中村治雄〉 564 7.血清総胆汁酸 〈大久保昭行〉 566 8.血清ビリルビン 〈大久保昭行〉 568 9.ICG 〈大久保昭行〉 570 10.ビタミンB12 〈橋詰直孝〉 572 XV.血液科学検査(5)電解質・金属・血液ガス 1.Na 〈越川昭三〉 575 2.K 〈越川昭三〉 579 3.Cl 〈越川昭三〉 582 4.総合カルシウム(Ca) 〈稲葉雅章 森井浩世〉 585 5.無機リン(IP) 〈稲葉雅章 森井浩世〉 590 6.血清鉄(Fe)・不飽和鉄結合能(UIBC)・総鉄結合能(TIBC)・トランスフェリン 〈浦部晶夫〉 594 7.マグネシウム(Mg) 〈浦部晶夫〉 597 8.銅(Cu) 〈浦部晶夫〉 598 9.浸透圧 〈飯野靖彦〉 600 10.動脈圧pH 〈青山昭徳 工藤翔二〉 603 11.動脈圧CO2分圧(PaCO2) 〈青山昭徳 工藤翔二〉 608 12.動脈血O2分圧(PaO2)と動脈血O2飽和度(SaO2) 〈青山昭徳 工藤翔二〉 612 13.肺機能検査 〈福井順一〉 617 索引 625
-
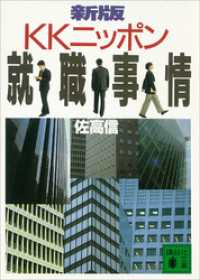
- 電子書籍
- 新版 KKニッポン就職事情 講談社文庫
-

- 和書
- 虹とクロエの物語