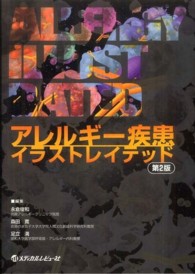出版社内容情報
《内容》 はじめに 科学研究に発表は欠くことのできないものである.科学論文の書き方といった実践的なガイドブックは,数多く刊行されている.しかし,投稿誌の選択から,論文審査.オーサーシップを含めた出版倫理,さらに研究業績の評価についての手引書は,ほとんど出版されていない.本書は,論文発表をめぐる科学コミュニケーションの世界への,研究者のためのガイドブックを意図したものである. 研究者は自己の成果を論文として発表していくことで,オリジナリティーを主張し科学コミュニティーに認められていく.論文の発表,質の評価,情報の普及,社会の受容といったプロセスへの理解は欠かせないものであろう.論文のオーサーシップを例にしても,本質的な貢献が無いにもかかわらず,研究室のトップを著者に入れることが慣例になっていたり,短い報告でありながら,教室員すべての名を連ねた論文なども目にする.オーサーシップの定義が混乱しているだけでなく,昇進や助成金の獲得のためにゆがめられていないだろうか. 研究論文をめぐる評価システムであるレフェリー制や業績評価をめぐる議論も,科学界でオープンに討議されるべきである.しかし,論文審査や出版倫理,そして引用評価についての基礎的な理解が,必ずしも普及していないように思う.現在,科学界に対する外部からの批判も厳しいものがあり,研究者自身が科学コミュニティーへの批判的な視点を共有するよう求められている.同僚審査(peer review)を例にすれば,業績評価は同じ領域の専門家にしかできないとする考えには問題があり,より広い社会的な視点から検討されなければならない. 本書は,投稿誌をどのように選択したら良いのかといった実践的な指針から,論文発表をめぐる倫理や研究業績の評価までをカバーした研究発表のための新しいガイドブックになっている.生命科学領域を例にしているが,科学者にとって共通する論文発表とコミュニケーションをめぐるトピックスが解説されている.科学コミュニケーションの世界に関心を持つ人々に,広く読んでいただければ幸いである. 本書を執筆するにあたり,企画段階で中外医学社の小川孝志氏から多くの助言をいただき,編集段階では久保田恭史氏からご協力を得ました. なお,本書4章は「あいみっく」15巻1-4号(1994年)に発表した「日本の生命科学研究者がよく投稿する外国雑誌のレフェリーシステム」に加筆したものであり,8章は同じく「あいみっく」12巻4号(1991年)に発表した「医学情報の普及と信頼性」をもとにしたものです.また,10章はメディカル朝日24巻1号(1995年)に発表した「海外発表論文からみた日本の医学研究機関の評価」に加筆したものです. 1996年5月 山崎茂明 《目次》 目次 1章 学術雑誌と科学コミュニケーションの世界 1 1.学術雑誌と論文 1 2.publish or perishからpublish and perishへ 1 3.毎週1論文クラブ 2 4.引用されない膨大な論文 3 5.rocorder journalからnewspaper journalへ 5 6.IMRADスタイルの形成と今後の変化 7 7.学術論文の量から質,そして出版の倫理へ 10 2章 論文発表の実態 13 l.世界の論文生産状況 13 2.日本の研究者はどのような外国雑誌に論文を発表しているのか 13 3.外国雑誌と国内欧文誌 17 4.学会誌と国際的商業誌の違い 19 5.国際的な情報交換の共通語としての英語 21 3章 インパクト ファクターと雑誌の評価 12 l.JCRとは何か 23 2.インパクト ファクターとは何か 28 3.引用の意味とその間題点 30 4.インパクト ファクターと被引用数による重要誌の変化 32 4章 投稿誌をどのように選択するか 34 1.投稿誌の選択 34 2.分野別のインパクト ファクターによるランク変化 34 1)自然科学 36 2)生物学 36 3)生理学 37 4)生化学・分子生物学 39 5)薬理学・薬学 39 6)免疫学 39 7)病理学 41 8)癌 41 9)内科・総合医学 41 10)循環器病学 44 11)消化器病学 44 12)腎臓・泌尿器病学 45 13)神経学 46 14)精神医学 47 15)放射線医学 48 5章 レフェリー システム 49 1.レフェリー システムとは 49 2.レフェリー システムの実際 49 3.論文の不採用率 51 4.レフェリーとはどんな人か 52 5.レフェリーになる意義 52 6.レフェリー・編集者・著者のコミュニケーション 54 7.レフェリーは審査論文を慎重に扱うべきである 55 8.匿名性 55 9.刊行遅れの原因か 56 10.剽窃への注意 57 11.レフェリーの保守主義と編集者の積極性 57 12.レフェリー間の意見の不一致 59 13.審査実態の公表 59 14.言葉の定義:レフェリーとpeer revier 60 15.第三番目のフィルターとしてのコレスポンデンス欄の役割 61 16.専門家集団のアイデンティティー 61 6章 日本の生命科学研究者がよく投稿する外国誌のレフェリー システム 64 l.レフェリー システムの実情を知るには 64 2.アンケート調査 64 3.レフェリーの人数と審査期間 66 4.審査の匿名性 67 5.論文不採用率 67 6.日本人研究者への編集者からのアドバイス 69 7.何が大切か 71 7章 論文発表の倫理 73 1.オリジナリティーと優先権 73 2.著者数の変化 74 3.オーサーシップとは 75 4.オーサーシップについての指針 77 5.重複出板,多重出阪,平行出版 78 6.二重投稿と既発表諭文 80 7.サラミ論文とミート エクステンダー論文 80 8.科学研究と発表をめぐる不正行為 81 9.論文の撤回 82 10.論文撤回と米国国立医学図書館の対応 85 11.日本における事例 88 8章 医学情報の普及と信頼性 90 1.情報の普及 90 2.NCIのClinical Alert 90 3.Clinical Alertをめぐる論点 92 4.研究情報の伝達についてのガイドラインの作成へむけて 92 5.問われたIngelfingerルール 93 6.Ingelfingerルールの変化 94 7.迅速で正確な情報提供への学術雑誌側の対応 98 8.Edward J. Huthの新ジャーナル 99 9.スピードよりも信頼性 100 9章 研究業績の評価とビブリオメトリックス 103 1.業績評価は可能か 103 2.方法としてのビブリオメトリックス 104 3.論文生産数と研究肋成金や名声との相関 105 4.引用文献による業績評価 108 5.アメリカの医学校ランキング 112 6.日本の生命科学系大学・研究機関の評価 112 10章 論文発表からみた日本の研究機関の業績評価 118 1.海外発表論文 118 2.研究活動と業績評価の指標 119 3.世界の主要医学校との比較 119 4.大学ランキング 121 5.研究所ランキング 130 6.企業ランキング 131 11章 日本の索引・抄録データベースへの収載 132 1.索引・抄録データベースへの収載状況を知るには 132 2.Index MedicusとMedlineに収載されている日本誌 133 3.MedlineとIndex Medicusにおける収載誌決定の現状 135 4.MedlineとIndex Medicusの選択基準 136 5.Gurrent ContentsとScience Citation Indexの選択基準 137 参考文献 141 索引 147