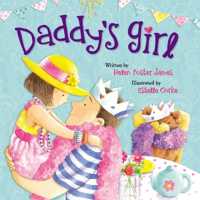出版社内容情報
《内容》 免疫学は現在爆発的進展を見せており,その新しい知識を常に得るのは容易でない.本シリーズは免疫学の領域から興味深いテーマやトピックスにスポットを当て,各テーマごとの分冊として,最も新しい内容を図表を多用し,読み易く,volumeも手頃にまとめたものである.免疫学領域のホットな最新情報が容易に得られるシリーズである. T細胞の分化と選択の分子機構を中心に,T細胞研究の最前線をまとめたupdateな書.内容は“造血細胞からTリンパ球へ:分化の過程とその機構”“T細胞初期分化の分子機構:CD4+CD8+細胞の生成とその制御”“recombinase activating geneはVDJ遺伝子再構成のリコンビネス遺伝子か”“CD8:その機構と発現,機能”“T細胞抗原レセプターを介する信号伝達”“positive and negative selection:トランスジェニックマウスの貢献”などである. まえがき 免疫学はここ25年間に他の学問領域で類を見ないほど急速な進歩を遂げ,医学・生物学の発展に大きく貢献してきた。モノクローナル抗体,分子生物学的手法の導入,トランスジェニックスマウスなど生物学の最新の技術の進歩とともに,これまで明らかにされていなかった免疫系の大問題が次々と解明されてきている。例えば,抗原がどのように処理されて主要組織適合抗原(MHC)に提示されT細胞受容体によって認識されるか(T細胞のMHC拘束性と抗原認識機構),多種多様な抗原に対応できるだけの種類の抗原受容体をどのようにして産生するか(多様性産生の分子機構),また自己寛容の成立のために自己成分と反応する免疫担当細胞が分化の過程で除かれること(自己寛容の機構としてのクローン欠損)もトランスジェニックマウスやスーパー抗原を利用した実験から証明された。さらに最近のFas抗原関連遺伝子のクローニングはキラーT細胞の機能発現や,自己免疫病マウスの病因といった免疫学の問題に答えてくれただけでなく,生物学一般の問題であるアポトーシスの分子機構にも重要な手がかりを与えてくれている。ところがこのような免疫学の急速な進歩にもかかわらず,自己免疫病,アレルギー,臓器移植などの現実的な問題には依然として不明な点が多い。免疫学の進歩にもかかわらず,現実的に最も問題となっている拒絶反応やGVHを阻止できないのはなぜだろうか? 免疫系の機構が大筋では理解できたとはいえ,自己寛容の成立に関する分子レベルでの理解はまだ十分とは言えない。胸腺内で正と負の選択が起こり,多数のT細胞がアポトーシスで死んでいることが明らかになっても,どのようなシグナルが最終的にT細胞にアポトーシスを誘導するかは依然として不明である。自己寛容の機構を制御するためにはT細胞の分化と選択の分子機構を解明することが必須である。同一の受容体から入るシグナルが,あるときはアポトーシスによる負の選択を誘導し,あるときは分化増殖シグナルとして正の選択を誘導する機構はどんなものなのだろうか? これこそ現在の免疫学が抱えている最も大きな問題である。 免疫系の「自己」と「非自己」の認識機構を考える上でT細胞の分化と発生の過程を切り離して考えることはできない。リンパ球を含む全ての血球細胞は骨髄中に存在する造血幹細胞より分化派生するが,T細胞だけはその分化・増殖に胸腺という骨髄から離れた場所に存在する臓器を必要とする。B細胞とT細胞のそれぞれの研究の進歩が比較されるが,T細胞研究の一番の難しさはB細胞と異なりin vitroの培養が難しいことが挙げられる。造血幹細胞からT細胞へのコミットメントは骨髄で行われるのか,それとも胸腺という環境がなければT細胞へのコミットメントも起らないのだろうか? 骨髄から胸腺までどのようにして前駆細胞がやってくるのだろうか? リンパ球系幹細胞があるとすればいったい何時何処でT細胞とB細胞は分岐するのだろうか? FACSを利用した細胞の解析分離技術が進んだことにより,骨髄中の造血幹細胞および胸腺中の最も未分化な細胞がそれぞれ同定され,これらの問題に回答が得られつつある。胸腺中の最も未分化な細胞はT細胞だけでなくB細胞にも分化する能力を持つリンパ球系幹細胞である点が興味深い。クローン欠損やアナジーはB細胞でも同様に存在するのに,なぜT細胞だけは骨髄で分化・増殖せず胸腺という特殊な臓器を必要とするのだろうか? いったい胸腺のどのような環境がT細胞の分化・増殖と選択を可能にするのだろうか? 胸腺内のリンパ球系幹細胞はやがてCD8を発現し,つぎにCD4を発現してCD4CD8ダブルポジティブと呼ばれる細胞に分化する。この間にリンパ球系細胞の最も大きな特徴である抗原レセプター遺伝子の再構成が行われる。T細胞の負の選択はCD8陽性からCD4CD8ダブルポジティブへ移行する時期に既に起こりえることが示され,T細胞受容体の発現がT細胞の分化に重要な影響を持っていることがわかる。この遺伝子再構成にはrecombinase activating gene(RAG)が必要である。RAG遺伝子の発現の制御がリンパ球系へのコミットメントの必要条件であることは確実だが,T細胞もB細胞も抗原レセプター遺伝子の再構成に同じRAG遺伝子を使うにもかかわらず,T細胞ではT細胞レセプター遺伝子,B細胞では免疫グロブリン遺伝子だけが再構成している。免疫系が多様性を獲得する手段として抗原受容体遺伝子の再構成を行うためにRAGが重要な役割を果たしていることがノックアウトマウスの実験から確認された。しかし,RAG-1,RAG-2そして,同じく遺伝子の再構成に関与すると予想されるSCID遺伝子がそれぞれどのように再構成に関わっているかは今後の課題である。 胸腺内における分化の過程がCD4・CD8の発現と特に密接に関連していることを先に述べた。CD4CD8ダブルポジティブ細胞の一部は正と負の選択を経た後,その細胞が発現しているT細胞受容体のMHC拘束性によってCD4かCD8のどちらかの発現を失い,成熟T細胞となって胸腺から末梢に出ていく。クラスI MHC分子上の抗原を認識する受容体を持つT細胞ではCD4の発現を失い,クラスII MHC分子上の抗原を認識する受容体を持つT細胞ではCD8の発現を失って成熟型のT細胞に分化する。このようなCD4やCD8のレシプロカルな発現の制御についてはinstructive modelとstochastic modelの二つの説が唱えられているが,未だ決着はついていない。それぞれの遺伝子の発現調節についても研究が進められているが、複雑な転写制御を受けいるらしく,その解析は容易ではない。転写に関与する因子そのものの同定および,lck以外のCD4・CD8からの信号伝達物質の発見が持たれる。 T細胞の正と負の選択にT細胞受容体を介した信号が決定的な役割を果たしていることは明らかである。しかし,同じ受容体からの信号が,あるときはアポトーシスを誘導して負の選択となり,あるときは分化増殖を誘導し正の選択を引き起こす。これが信号の量的な違いによるものなのかそれとも質的に異なる信号が入るのかは大変興味深い問題である。これらの信号伝達に関与する物質としてZAP70が同定されたが,信号伝達に関与する一連の物質が明らかにされる日も近いと思われる。 また,リンパ球系細胞の特徴として一つ一つの細胞が遺伝子再構成により一種類の抗原受容体を発現することが挙げられる。片方の遺伝子座で再構成がうまくいくともう一方の遺伝子の再構成が止まる機構(allelic exclusion)は,免疫担当細胞が1種類の抗原レセプターだけを発現することを保証している。この機構は生物学的にも大変興味ある問題であるが,この機構のおかげでT細胞レセプター遺伝子のトランスジェニックマウスを使った実験によりバーネットが40年前に唱えたクローン選択説を直接証明することができた。トランスジェニックマウス作製の技術が学問的に貢献した好例といえる。 T細胞の分化と選択に関する問題は沢山残っていて興味は尽きないが,本書ではT細胞関連の研究を行っている若手の免疫学者に彼らの研究成果を概説してもらい,読者の方にこの領域での最前線の状況を理解してもらうことを目的として編集した。T細胞研究が益々進展し,近い将来「自己寛容」や「記憶」の制御が可能になり,より現実的な臨床医学への貢献がもたらされることを強く期待するものである。 最後に,貴重な時間を割いて原稿を書き上げてくれた著者の方々と,辛抱強く原稿の完成を待ち続けてくださった中外医学社の高橋衛氏に心よりお礼を申し上げる。 1995年5月 中内啓光 《目次》 目次 I.造血幹細胞からTリンパ球へ 分化の過程とその機構 〈松崎有未,中内啓光〉 1 A.骨髄中の造血幹細胞 3 1.造血幹細胞 3 2.骨髄中のリンパ球幹細胞 4 B.胸腺中のT前駆細胞 7 C.胸腺内T細胞初期分化の開始とその機構 10 D.DNからDPへの移行とそれに伴う細胞増殖 12 II.T細胞初期分化の分子機構 CD4+CD8+細胞の生成とその制御 〈高浜洋介〉 15 A.CD810細胞とそのCD4+CD8+細胞への分化 18 B.CD810細胞上のTCRの発現 20 C.CD810細胞上のTCRによるT細胞分化の制御 21 D.CD810細胞上のTCRによるnegative selection 22 E.CD810細胞上のTCRによるT細胞分化制御の機構 24 III.recombinase activating gene(RAG)はVDJ遺伝子再構成のリコンビネース遺伝子か? 〈真貝洋一〉 29 A.RAG-2欠損マウスの作製とそのフェノタイプ 31 B.RAG-2欠損マウスは抗体およびTCR遺伝子のVDJ再配列を全く起こしていないらしい 37 C.RAG-2欠損マウスの応用性と残された課題 44 IV.CD8 その構造と発現,機能 〈川内康弘〉 47 A.CD8の構造とMHCとの結合 48 B.CD8の発現と機能 51 C.CD8の機能 57 V.T細胞抗原レセプターを介する信号伝達の分子生物学 〈岩島牧夫〉 63 A.TCR信号伝達とARAM 65 1.ARAMの一次構造 65 2.ARAMの機能 66 B.ARAMによる信号伝達の機構 68 1.ZAP-70との結合の誘導 68 2.ZAP-70の機能 70 C.CD45とCSKによるTCRシグナルの調節 71 VI.positive and negative selection トランスジェニックマウスの貢献 〈中山敬一〉 75 A.クローン選択説とMHC拘束性 76 B.TCRトランスジェニックマウスのメリットは何か 77 C.TCRトランスジェニックマウス作製の条件 78 D.トランスジェニックマウスにおけるTCRの発現 79 E.TCRトランスジェニックマウスにおけるpositive/negative selectionの解析 80 1.H-Yマウス(1988) 81 2.2Cマウス(1988) 82 3.2B4マウス(1989) 85 4.PCCマウス(1989) 87 5.LCMVマウス(1989) 87 6.DO10マウス(1990) 88 F.in vitro negative selection系の開発 91 G.negative selectionのシグナル伝達系はTリンパ球活性化シグナルとは異なる 94 H.今後の展望 98 文献 101 索引 119