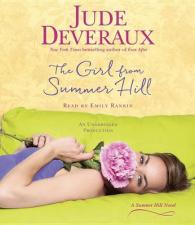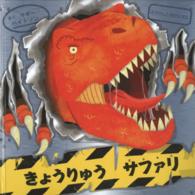出版社内容情報
《内容》 薬理学の講義に際しては,化学構造式,薬物の作用点や作用機序の図表をノートに写すことが多いが,書き違いの恐れもあり,かつ煩雑なことでもある.本書はこうした図表をまとめたサブノート“目でみる薬理学”として好評を博してきたが,この度改訂し,最新の内容とした.より正確な,能率のよい学習のためにおすすめする. 序 旧版「図解薬理学」の刊行以来,すでに9年余りの歳月が経過したので,旧版作製時の精神を生かしながら,内容を全く一新することを計画した. とかく,無味乾燥になりがちな薬理学講義を,少しでも理解し易くするために,また学生諸君の薬理学への興味を少しでも呼び起こすことができるようにとの意図を,旧版以上に盛り込むために,元の執筆者3人(岩田,植木,高木)の他に,新執筆者として瀬川,田坂,宮田の3人が加わり,6人が互いにそれぞれの分担原稿を持ち寄って,全員が1頁から最終頁まで目を通し,何回も,長時間検討を加え,練り上げた結果でき上がったのが本書である. 新版では,その後に登場した新薬を加えるとともに,旧い薬は削除し,新しい章や図表を追加し,ほとんどの表を書き直し,できるだけオリジナルな形のものにするよう努力を重ねた.また旧版では図表の背景となる基礎的な説明が不十分な箇所もあったので,新版ではそれらの点も改善したつもりである. したがって本書は全く新しい著書といってもよい程,内容を一新した. 本書が教材として,また参考書としてお役に立てば誠に幸いである. なお本書執筆にあたり,下記の3氏の多大の御協力を得た.ここに厚く感謝する次第である. 佐藤公道(京都大学薬学部薬理学助教授) 野村靖幸(富山医科薬科大学和漢研究所教授) 藤井俊志(九州大学医学部附属病院薬剤部薬品情報室掛長) 1985年1月 高木博司 植木昭和 岩田平太郎 瀬川富朗 田坂賢二 宮田健 初版の序 薬理学の講義の際に,私達は薬物の化学構造式の一覧表や,薬理作用に関する図などを各自がプリントして学生諸君に配布したり,あるいは黒板上に書いたりすることを長年やってきた.しかし各講義の前にプリントを準備することは実際上なかなか手間もかかり,また黒板に書いた構造式や図をノートに写す場合,書き間違いのおそれもある.そこで化学構造式や図表を印刷した簡単な本があれば便利であろうと常々考えていた.たまたま同じようなことをドイツでも考えたらしく,LEMBECKとSEWINGによりほぼ上記の趣旨に沿った小冊子(Pharmacological facts and figures)が出版された.これが刺激になって,わが国でもこのような本が欲しいということになり,岩田の呼びかけに高木と植木が賛同し,3人がそれぞれ図表類を持ちより,検討を加えた結果まとまったのが本書である.しかしながら,本書はLEMBECKとSEWINGの本の単なる模倣ではなく,更に充実し,体系化したものを狙ったつもりである. 一枚の良い図が薬物の作用点や作用機序の理解にどんなに有用であるかは多言を要しないであろう.しかし明解な図を作るためにはためには可成りの単純化が必要であり,一方単純化が行きすぎると真実がゆがめられるおそれも出てくる.図の作製や選択に当り,この辺のバランスをどうとるかという点に苦心をはらった.図は出来るだけ本書独自のものを作るよう努力したが,それでも他の成書や論文から借用したり作図上のヒントを得たりしたことも少なくない.借用した図については原著者名を記して敬意を表した次第である. 化学構造式については出来るだけ新薬のそれを採用するように配慮したが,臨床評価の定まっていないものや古い薬で使用されていないものは歴史的に必要なもの以外は省いた.なお化学構造式の表示法については,神戸女子薬科大学の二宮一弥教授(薬化学)にお願いして,原稿に目を通していただき,内容の統一や訂正をしていただいた.ここに二宮教授の御助力に対し厚く御礼申し上げる次第である. 著者らはこの本が完璧なものとは思っていないが,一応講義の教材用として必要最少限を満たすよう努力したつもりである.万一本文中に間違いや,脱落などがあれば講義者や読者から御注意いただければ幸いである. 最後に,本書の企画から出版までの長い間,終始御助力頂いた中外医学社の青木三千雄,鴨志田和夫両氏に感謝する. 1974年11月22日 著者 《目次》 目次 §1.総論 薬理学の基礎となる領域および関連領域 1 薬理学の内容 1 各種投与ルートによる薬物の吸収,分布,代謝,排泄 2 薬物の作用点 4 作用点からみた薬物の分類 4 レセプターモデルの1例 4 薬物とレセプター結合後におこる細胞膜および細胞内における物質の 動き 5マグヌス装置による摘出小腸の運動記録法の1例 7 用量-反応曲線 8 graded response 8 quantal response 10 bell-shape dose-respons curve 12 時間-反応曲線 12 薬効に影響を及ぼす諸因子 13 薬物代謝の生化学的反応の型 14 肝ミクロゾームの電子伝達系と薬物代謝 16 新医薬品の開発 17 医薬品副作用情報収集および伝達機構 18 プラセボ効果 19 薬物乱用 20 §2.中枢神経に作用する薬 中枢神経の区分 21 中枢神経作用薬研究法 23 薬物による一般症状および行動変化の観察 23 電気生理学的研究 23 薬物の脳内投与法 25 生化学的研究 26 形態学的研究 26 神経伝達物質 27 アミン系 27 アミノ酸系 28 ペプチド系 29 シナプスにおける薬物の作用点の可能性 31 血液-脳関門 32 全身麻酔薬 33 吸入麻酔薬 33 静脈麻酔薬 36 催眠薬 38 benzodiazepine 40 barbiturates 40 その他 42 エタノールの体内における代謝 42 エタノール血中濃度と中毒症状 43 鎮痛薬 44 鎮痛効力試験法 44 各種痛み刺激の知覚神経への作用と疼痛反応 45 痛覚求心路と鎮痛薬の作用部位 46 アヘンアルカロイドおよびその関連鎮痛薬 48 合成麻薬性鎮痛薬 49 拮抗性鎮痛薬 50 付)麻薬拮抗薬 50 解熱性鎮痛薬(消炎鎮痛薬) 51 特殊な疼痛に用いられる薬物 51 諸種鎮痛薬の薬理学的特徴 52 抗けいれん薬(抗てんかん薬) 53 てんかんの分類 53 barbiturates 54 deoxybarbiturates 54 hydantoins 54 oxazolidinediones 54 succinimides 54 acetylureas 54 iminostilbenes 55 benzodiazepines 55 valpronic acid 55 その他 55 向精神薬 56 主な精神障害 56 向精神薬の行動薬理学的作用評価 59 向精神薬の分類 62 抗精神病薬 63 抗うつ薬 68 抗不安薬 74 抗精神病薬,抗うつ薬,抗不安薬の作用の一般的比較 79 精神異常誘発物質 79 抗パーキンソン病薬 84 パーキンソン病 84 錐体外路系の主要な線維連絡と伝達物質 84 付)パーキンソン病発症関連物質 87 中枢性骨格筋弛緩薬 88 中枢興奮薬 89 おもな脳内作用部位による分類 89 strychnineのシナプス後抑制作用 91 §3.局所麻酔薬 哺乳類の神経線維の分類 93 局所麻酔の方法 94 局所麻酔薬の作用機序 95 エステル型 96 アミド型 98 キノリン系 98 その他 99 寒冷麻酔薬 99 代表的局所麻酔薬の適用濃度と作用持続 100 §4.自律神経薬 自律神経系模式図 101 自律神経系および運動神経系の神経伝達物質による分類 102 自律神経線維の解剖学的特徴 102 交感,副交感神経の主要器官に対する効果 103 自律神経薬の分類 104 コリン作動薬 105 コリン作動神経におけるAChの合成,貯蔵,遊離と薬物の作用部位 105 AChおよびその類似薬物 106 各種cholinesterの作用比較 106 acetylcholineレセプター(サブタイプ)の種類 106 コリン作動性レセプターの分類 107 AChによる血圧下降とatropine投与後のACh大量による血圧上昇 108 ACh以外のコリン作動薬 108 アセチルコリン レセプターを介する生化学的反応 108 可逆的抗コリンエステラーゼ薬 109 有機リン化合物 109 コリンエステラーゼ再賦活薬 110 アセチルコリンエステラーゼの活性中心モデルと基質および阻害薬との結合様式 110 抗コリン作動薬 111 ベラドンナアルカロイドおよびその関連薬物 111 合成抗ムスカリン薬 112 アドレナリン作動薬 113 アドレナリン作動ニューロンの構造 113 noradrenaline含有ニューロン終末におけるNAの生合成,貯蔵,遊離 113 noradrenalineおよびadrenalineの生合成 114 noradrenalineおよびadrenalineの主要な代謝経路 114 アドレナリンレセプターの種類と機能 115 αおよびβレセプターのサブタイプの分類,局在,機能と作用メカニズム 115 おもなアドレナリン作動薬 116 3種のcatecholaminesの循環器効果比較 117 アドレナリンαレセプター遮断薬 118 アドレナリンβレセプター遮断薬 119 3種のcatecholaminesの血圧作用と遮断薬の効果 121 adrenalineのβ効果の発現機構 122 付)中枢神経系のアドレナリンレセプターに作用する薬物 122 アドレナリン作動ニューロン抑制薬 123 神経節遮断薬 124 各種臓器における自律神経の優位性と節遮断薬の効果 124 神経節遮断薬 124 神経節刺激薬 125 交感神経節に作用する薬物の作用部位 125 ドーパミンレセプターの分類 126 §5.環状ヌクレオチド cyclic-AMP 生成と分解 127 筋肉内グリコーゲンホスホリラーゼのアドレナリンによる活性化 128 cyclic-AMPを介して効果をあらわすホルモン 129 §6.運動神経骨格筋接合部遮断薬 運動神経骨格筋接合部 131 運動神経興奮から骨格筋収縮まで 132 興奮-収縮連関 133 運動神経筋接合部遮断をおこす条件 133 運動神経骨格筋接合部遮断薬 134 競合的遮断薬 134 脱分極性遮断薬 135 二相性作用型 136 競合的遮断薬と脱分極性遮断薬の比較 137 §7.呼吸器に作用する薬 呼吸運動調節機構 139 呼吸興奮薬 140 呼吸鎮静薬 140 鎮咳薬 140 咳の原因 140 咳の受容器の分布状態 140 咳反射の経路 141 中枢性鎮咳薬 142 末梢性鎮咳薬 143 気道の清浄化機構 144 去痰薬 145 気道分泌促進剤 145 気道粘液溶解剤 145 防腐性去痰剤 146 その他 146 §8.循環器に作用する薬 心臓のポンプ作用 147 心臓の刺激伝導系 148 心臓反射 149 心臓神経 149 心臓神経の作用 149 心電図 151 うっ血性心不全 151 強心薬 152 強心配糖体 152 強心配糖体以外の強心薬 154 狭心症治療薬 155 亜硝酸化合物 155 平滑筋弛緩薬 156 カルシウム拮抗薬 157 アドレナリンβレセプター遮断薬 157 不整脈治療薬 158 不整脈 158 不整脈治療薬の分類 158 不整脈治療薬の作用機序による分類 159 高血圧症治療薬 160 血圧 160 高血圧症 161 高血圧症治薬の分類 161 高血圧症に用いる薬物の作用点 162 ショックとその治療薬 164 ショック 164 ショックの種類と治療薬 164 末梢血管拡 張薬 165末梢血行障害 165 末梢血行障害に用いる血管拡張薬 165 動脈硬化症に用いる薬物 166 動脈硬化症 166 動脈硬化症治療の原則 167 §9.利尿薬 尿の生成 171 ネフロン 171 尿生成の機構 172 尿細管における水-電解質の再吸収 173 クリアランス 174 尿細管における酸塩基平衡の調節 175 重炭酸塩の再吸収 175 酸性尿の生成 175 アンモニアの排泄・K+の排泄 176 浮腫 177浮腫の原因 177 心臓性ならびにネフローゼ性浮腫の発生機序 177 利尿薬 179 浸透圧性利尿薬 179 炭酸脱水酵素阻害薬 179 benzothiadiazidesおよびその類似化合物 180 HENLE上行脚に作用する利尿薬 181 カリウム保持性利尿薬 181 xanthine誘導体 182 §10.血液および造血臓器に作用する薬 貧血治療薬 183 人体内における鉄 183 鉄の体内における動態 183 鉄吸収機序 183 ヘモグロビンの構造と酸素と炭酸ガス結合 184 骨髄での赤血球新生 185 erythropoietine 185 貧血 185 貧血に対して用いる薬物 186 血液凝固に影響を与える薬物 189 血液凝固 189 線維素溶解 189 フィブリンの形成とその溶解 190 抗凝血薬 191 血液凝固促進薬 192 抗プラスミン薬 193 血液代用薬 193 §11.オータコイドおよびその関連薬物 ヒスタミンおよび抗ヒスタミン薬物 195 ヒスタミンのおもな作用 195 ヒスタミンの生合成,分解経路 196 組織ヒスタミンの遊離要因 196 compound 48/80によるヒスタミン遊離機序 197 ヒスタミン遊離抑制作用をもつ薬物 197 H1-receptor agonist 197 H1-blockerの薬理作用 198 おもなH1-blocker 198 H1-blockerの構造活性相関 199 H2-receptor agonist 200 H2-blockerのおもな薬理作用と副作用 200 おもなH2-blocker 201 セロトニンおよび抗セロトニン薬 202 セロトニン生合成とおもな代謝経路 202 セロトニンの体内分布 202 セロトニンの作用 203 セロトニンと疾患 203 抗セロトニン薬 204 レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系 206 アンジオテンシンIIの生成 206 アンジオテンシンIIの薬理作用 206 レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系の循環器ホメオスタシスにおける役割 207 レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系抑制薬 207 血漿キニン類 208 キニンの生成と分解 208 カリクレイン-キニン系 208 キニンの整理作用 209 カリクレイン-キニン抑制薬 209 プロスタグランジンおよび関連物質 210 プロスタグランジンおよび関連化合物の分類 210 PGおよび関連化合物の生合成 211 PGおよび関連化合物の代謝 214 PGおよびLTの生理作用 215 PGの合成阻害薬 216 ロイコトリエン拮抗薬 217 PGの臨床的応用 217 血小板活性化因子 218 PAFの主な生理作用 218 PAF拮抗薬 218 §12.ホルモンおよびホルモン拮抗薬 下垂体ホルモン 219 下垂体前葉ホルモン 219 下垂体中葉ホルモン 222 下垂体後葉ホルモン 223 下垂体ホルモンの分泌と生理作用 224 副腎皮質ホルモン 225 副腎皮質ホルモンの作用比較 225 副腎皮質ホルモンの生合成 226 糖質コルチコイド 227 鉱質コルチコイド 227 合成副腎皮質ホルモン 227 構造活性相関 229 副腎皮質ホルモン生合成阻害薬 230 男性ホルモン 231 合成男性ホルモン 231 女性ホルモン 232 卵胞ホルモン 232 黄体形成ホルモン 233 蛋白同化ステロイド 235 甲状腺ホルモン 236 thyroxine・triiodothyronine 236 カルシトニン 238 上皮小体ホルモン 239 膵臓ホルモン 241 付)唾液腺ホルモン 241 §13.抗炎症薬 炎症 243 抗炎症薬 244 抗炎症薬のスクリーニング法 244 抗炎症薬の分類とその作用時期 245 ステロイド性抗炎症薬 246 非ステロイド性抗炎症薬 247 §14.痛風治療薬 痛風 255 プリン代謝 255 §15.免疫薬理 免疫の成立とアレルギー反応 257 アレルギー反応の分類と特徴 258 I型アレルギー 258 II型アレルギー 259 III型アレルギー 261 IV型アレルギー 261 薬物アレルギー 262 免疫グロブリンの物理的および生物学的性状 264 IgGのサブクラス 264 免疫抑制薬 265 アルキル化物質 265 代謝拮抗薬 266 副腎皮質ステロイド 266 cyclosporine A 267 抗リンパ球血清および抗リンパ球グロブリン 267 付)免疫抑制薬の副作用 267 免疫調節薬 268 合成薬 268 生物学的物質 268 抗アレルギー薬 気管支喘息治療薬を中心として 269 気管支喘息の病態生理と治療対策 269 β2レセプター興奮薬 270 気管支平滑筋弛緩薬 270 抗アレルギー薬 270 糖質コルチコイド 271 抗コリン作動薬 272 補助療法 272 §16.消化器に作用する薬 消化管壁の構造 273 胃腺の分布と構造 273 消化薬 274 健胃薬 274消化管ホルモンの生理作用 275 消化性潰瘍の成因と治療薬の作用機序 276 消化性潰瘍治療薬 277 制酸薬 277 抗コリン作動薬 277 ヒスタミンH2遮断薬 278 抗不安薬 278 抗ガストリン薬 278 抗ペプシン薬 278 粘膜保護薬 278 組織修復薬その他 279 催吐薬と制吐薬 280 嘔吐発現の機序 280 催吐薬 281 制吐薬 281 胃腸管における吸収と内容物の状態 282 止瀉薬 283 下剤 284 塩類下剤 284 刺激性下剤 284 膨張性下剤 284 浸潤性下剤 285 各種下剤の効果発現時間と便の性状 285 利胆薬 285 胆汁生成および分泌亢進薬 285 排胆薬 286 胆石溶解薬 286 §17.子宮収縮 子宮収縮ホルモン(オキシトシン)の分泌と作用 287 子宮収縮薬の臨床的応用 288 オキシトシン 288 バッカクアルカロイド 289 sparteine 290 quinine 290 gravitol 290 hydrocotarnine 290 prostaglandinおよびその誘導体 290 §18.糖尿病治療薬 膵内分泌の相互調節 291 インシュリンの主な生理作用 292 インシュリン作用の欠乏をおこしう る要因 292 インシュリン作用の欠乏時の病態生理 293 インシュリン製剤の作用比較 294 経口糖尿病治療薬 295 sulfonylurea系 295 sulfonamide系 296 biguanide系 296 その他 296 §19.化学療法薬と抗生物質 作用様式による分類 297 主な作用機序による分類 298 対象疾患または病原微生物による分類 299 主要抗生物質の有効菌種 300 スルファミン類 302 抗生物質 303 βラクタム系 303 クロラムフェニコール類 310 テトラサイクリン類 311 アミノグリコシド系 311 マクロライド系 314 ペプチド系 317 ナリジク酸系 319 その他の抗生物質 319 抗結核薬 321 抗らい薬 324 抗真菌薬 325 抗生物質 325 flucytosine 326 イミダゾール系化合物 326 その他の抗真菌薬 327 抗ウイルス薬 328 抗寄生虫薬 330 抗蠕虫薬 330 抗原虫薬 332 抗腫瘍薬 337 アルキル化剤 337 代謝拮抗物質 340 抗腫瘍性抗生物質 343 ホルモン 346 植物成分 348 免疫賦活物質 349 その他 350 §20.駆虫薬 santonin剤 351 カイニン草剤 351 chenopodium oil剤 351 piperazines 352 phenolsとその誘導体 352 ハロゲン化合物 353 色素類 353 antimony化合物 354 その他 355 §21.消毒薬 用途による分類 357 化学的分類 357 フェノール類 357 アルコールおよびアルデヒド 358 ハロゲンおよびハロゲン化合物 359 酸 359 酸化剤 360 重金属化合物 360 界面活性剤 360 色素剤 361 その他 362 §22.重金属中毒治療薬 重金属の侵入経路と中毒症状 363 中毒症状発現機序 364 中毒症状 364 重金属中毒解毒薬 365 索引 367 0 0 0
-
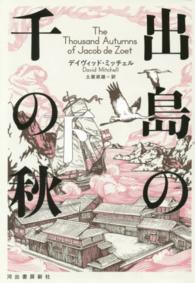
- 和書
- 出島の千の秋 〈下〉