内容説明
紀元前11世紀に造られた青銅器の銘文が「中国」の初出とされている。爾来数千年、「中国」という言葉には様々なイメージが投影され、膨張し続けている。この、日本が、世界が、さらには中国自身が理解しがたい「中国イメージ」について、膨大な資料より掘り起こした歴史的叙述および周辺地域(日本・朝鮮・ヨーロッパなど)の視点とその交流史から描き出し、多面的な「中国」理解に対する一つの方向性を提示する。
目次
序論 「中国」についての歴史論述の再構築―民族国家から歴史を救済するか、それとも歴史のなかで民族国家を理解するか
第1編 歴史のなかで中国を理解する(宋代に顕在化する「中国」意識―近世ナショナリズム思想の一つの淵源;『山海経』、「職貢図」と旅行記における異域の記憶―マテオ・リッチ来華前後の中国人の異域に関する知識リソースとその変化;思想史としての古地図)
第2編 交錯するアジア、東アジア、中国(西洋と東洋、あるいは東洋と東洋―清代中葉における朝鮮と日本の中国に対しての感懐;イメージの、そして現実の…誰が「アジア」をアイデンティティとするのか―清末から民国初頭にかけての日本と中国の「アジア主義」言説について;国家と歴史のはざま―中国の道教と日本の神道および天皇制との関係をめぐる日本の論争を起点として)
第3編 アジア理解と中国史の方法(国境の関所はどこにあるのか―一九、二〇世紀交代期における日本の「満蒙回蔵鮮」学の背景から論じる;「西域」から「東アジア海域」へ―新しい歴史世界の形成とその方法および問題)
結論 預流、立場、方法―歴史研究の新たな視野を求めて
著者等紹介
葛兆光[カツチョウコウ]
1950年上海市生まれ。北京大学大学院中国古典文献学専攻を修了後、清華大学歴史系教授、復旦大学文史研究院院長などを歴任。現在、復旦大学歴史系特聘資深教授
橋本昭典[ハシモトアキノリ]
1968年滋賀県生まれ。神戸市外国語大学外国語学部中国学科卒業、関西大学大学院文学研究科中国哲学及哲学史専修修了。博士(文学)。現在、奈良教育大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
-
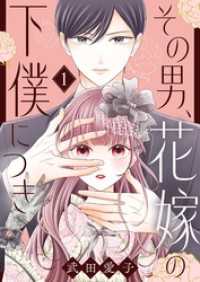
- 電子書籍
- その男、花嫁の下僕につき【描き下ろしお…
-

- 電子書籍
- FukuokaWalker福岡ウォーカ…






