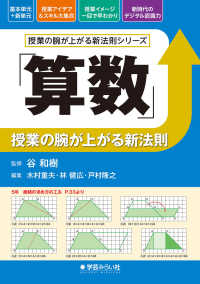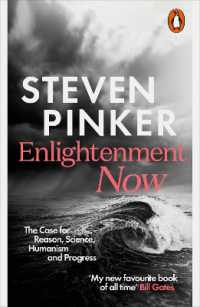内容説明
三世紀末から五世紀半ばにかけて、中国北部では匈奴を始めとする諸民族が移動・定住し、彼らによって建てられた政権が並立する「五胡十六国時代」と呼ばれる大分裂時代を迎えた。従来、この時期は暗黒時代と考えられがちであったが、後の隋唐帝国の制度や文化、東アジア世界の国際関係などは、五胡十六国時代の諸政権にその淵源を求めることができるのである。本書は、諸政権の興亡を詳述するとともに、新たな中国建設への胎動の時代という観点からこの時代に光を当てる。本新訂版では、十年間の研究の進展に基づいて内容を修正し、また墓室画像などをふんだんに用いて、民族融合の様子を再現した。
目次
序章 民族の時代
第1章 後漢~西晋時代の少数民族
第2章 「五胡」とは何か、「十六国」とは何か
第3章 「十六国」の興亡
第4章 「十六国」の国際関係と仏教と国家意識
第5章 人の移動
第6章 「五胡」と漢族の融合
終章 南北朝から隋唐帝国へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kuroma831
22
大学生の頃に旧版を読んだが、新訂版で結構な加筆があると聞き再読(新訂版が出たのも10年以上前だが)。東方選書の「周縁の三国志」と「北魏史」を買ったので、間に繋がる五胡十六国のおさらい。五胡十六国諸国の歴史を淝水の前後でそれぞれ概略としてまとめており分かりやすい。新訂版では墓室の発掘調査等から分かる胡漢融合の歴史を辿れる。五胡十六国以前から胡漢の混住は進んでおり、西晋末の混乱で一気に動乱が広がったという経緯がよく分かる。五胡十六国各国の君主号や元号使用、遷都などからも国際関係が分かり、面白い。2024/10/06
coolflat
16
31頁。「五胡」ということばは五種類の少数民族を意味し、3~5世紀に北方・西方から中国に移住した匈奴・羯族・鮮卑・氐族・羌族を指すことはほとんど常識となっている。しかしこの時期に活動した少数民族には他にも丁零・烏桓や扶余・高句麗もあり、巴族・蛮族・りょう族・胡族などと呼ばれる人々もいた。また匈奴と羯族の関係と匈奴と盧水胡の関係の捉え方は一定ではなく、さらに成漢を建国した民族は氐族・そう族あるいは巴族・巴氐などとされることもある。五胡という名称は、数の点では当時の華北の民族状況を表すことばとして正確ではない2023/04/07
ピオリーヌ
15
原著は2002年の刊。新訂版の同書は2012年の刊。入り組んだ印象のあるこの時代だが、豊富な写真、系図によりだいぶ理解できた気がする。特に第三章「『十六国』の興亡」が分かり易い。あとがきにある『五胡十六国覇史輯佚』が気になる。2021/11/25
ジュンジュン
15
五胡十六国時代とは、"五胡"でも"十六国"でもなかった事にまず驚く。秦漢帝国から隋唐帝国までの谷間の時代、そんな消極的なイメージから、多くの民族(漢民族も含めて)が移動、融合した活力のある時代へと積極的に評価しようと試みる。理解を助ける工夫を随所に感じるが、それでも手ごわい。2021/01/17
MUNEKAZ
12
五胡十六国時代の概説書。「五」や「十六」はただの修辞でこれにとらわれる必要はないということで、23もの国の興亡が紹介されている。多くの民族の流入が進み、文化の混合が行われたこの時代らしく、漢族と胡族の両方の支持を得なければ政権を維持できない姿が特徴的。君主号は「皇帝」か「天王」か(はたまた「可汗」か)、漢族の正統である東晋との向き合い方は、など自らのアイデンティティの悩む姿が印象に残る。また本拠地の移動や征服地の失陥に伴って大規模な住民移動が頻発しており、これが混乱に拍車をかけたのだろうと思われる。2020/02/14
-

- 洋書電子書籍
- 初歩から中級の現代標準アラビア語の語彙…