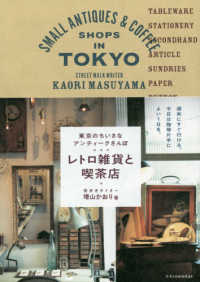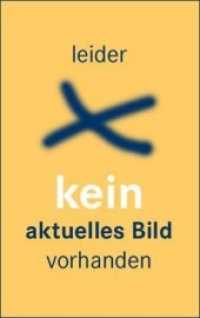出版社内容情報
貨幣と貨幣数量説の意味を、経済史・経済学史の中で追究。2000年代の金融危機も踏まえ、「古典派の二分法」の再検討を提言。
貨幣とは、経済の中でどのような意味を持つ存在なのか。
20世紀初頭に「貨幣数量説」がひとつの完成形に到達し、それは1970~80年代のマネタリズムへ、その後の合理的期待学派や新しい古典派マクロ経済学へと引き継がれた。
それらの理論のコアが、「貨幣の中立性」「古典派の二分法」という考え方である。
一方、貨幣数量説的な立場に対しては、それぞれの時代において多くのアカデミックな論争が展開された。
2000年代以降は、金融市場における危機が実体経済に悪影響を及ぼす事態も観察されている。
本書はそのような今日的な問題意識に立って、貨幣と貨幣数量説の意味を、経済史・経済学史の中で追究している。
第1章 イントロダクション
第2章 貨幣数量説の歴史的発展
第3章 16世紀「価格革命」論の検証
第4章 19世紀イギリスにおける貨幣理論の発展
第5章 大恐慌と貨幣
第6章 第2次世界大戦後のマクロ経済学と金融理論の変遷
第7章 まとめ
【著者紹介】
平山 健二郎(ヒラヤマ ケンジロウ)
関西学院大学経済学部教授
1952年、兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業、大阪大学大学院前期課程、イェール大学大学院、京都産業大学経済学部講師、関西大学商学部助教授を経て、現在、関西学院大学経済学部教授。
専攻は金融論、証券市場論。大阪大学経済学修士、イェール大学 Ph. D.
主要著作:
“How Fast Do Tokyo and New York Stock Exchanges Respond to Each Other?: An Analysis with High-Frequency Data.” (with Y. Tsutsui) Japanese Economic Review, Vol. 66, Issue 2, 2009.
『インタラクティブ・エコノミクス』(共著、有斐閣 、2003年)
『日本の株価』(共著、東洋経済新報社 、2009年)
内容説明
「貨幣の中立性」「古典派の二分法」の命題は今日も有効なのか?歴史を振り返り、2000年代の金融危機も踏まえて、貨幣数量説の意味を検証する。
目次
第1章 イントロダクション
第2章 貨幣数量説の歴史的発展
第3章 16世紀「価格革命」論の検証
第4章 19世紀イギリスにおける貨幣理論の発展
第5章 大恐慌と貨幣
第6章 第2次世界大戦後のマクロ経済学と金融理論の変遷
第7章 まとめ
著者等紹介
平山健二郎[ヒラヤマケンジロウ]
1952年、兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業、大阪大学大学院前期課程、イェール大学大学院、京都産業大学経済学部講師、関西大学商学部助教授を経て、関西学院大学経済学部教授。専攻は金融論、証券市場論。大阪大学経済学修士、イェール大学Ph.D.(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 偽りの女神【タテヨミ】第64話 pic…