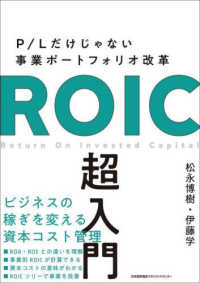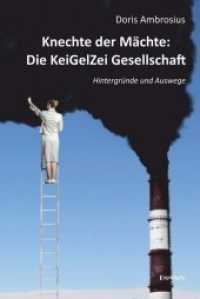内容説明
日本では個人金融資産が1400兆円もあり大変豊かであるにもかかわらず、家計の資産選択が安全志向すぎるとよく言われる。しかし本当にそうなのだろうか。本書では日本の家計の資産選択行動を国際比較を交えて分析し、その行動が合理性に裏付けられていることを明らかにする。貯蓄をもたない世帯が全体の2割を超えたこと、日本の株式保有世帯比率が決して欧米よりも突出して低いわけではないことなど、家計の資産選択の大きな流れを示すとともに、家計の詳細なデータを用いて借入制約、日本型経営システム、社内預金や従業員持株制度、住宅ローン、税制、生保の破綻、ペイオフなどがどのような影響を与えているかを実証的に示す。
目次
豊かさのなかの分裂―ゼロ貯蓄、ゼロ金融資産保有世帯の急増
金融資産選択の推移と国際比較
企業の資金調達、家計・企業間関係と家計の資産選択
安全資産投資と株式投資の選択理由
情報の非対称性下の借入制約と危険金融資産シェアの関係
勤労者・企業間関係と家計の株式需要
住宅・土地シェアと危険金融資産シェアの関係―貯蓄・負債目的の影響を踏まえて
株式収益率と個人金融市場の厚みの効果―家計の危険金融資産選択のパネル分析
税制と資産選択―老人マル優制度を手がかりとして
生命保険会社破綻と家計・保険契約者の選択―保険契約者は何に注目して生保会社を選べばよいか、あるいは会社の何に注目しているのか〔ほか〕
著者等紹介
松浦克己[マツウラカツミ]
1951年福岡県生まれ。1975年九州大学法学部卒業、郵政省入省。大阪大学経済学部助教授、長崎大学経済学部教授、横浜市立大学商学部教授を経て、現在広島大学大学院社会科学研究科経済学部教授、郵政総合研究所客員研究員。経済学博士
白石小百合[シライシサユリ]
1963年長野県生まれ。1986年上智大学外国語学部卒業。日本経済研究センター入社。2004年慶応義塾大学経済学研究科後期博士課程単位取得退学。現在、日本経済研究センター副主任研究員、政府税制調査会金融小委員会委員、厚生労働省独立行政法人評価委員会委員。経済学修士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。