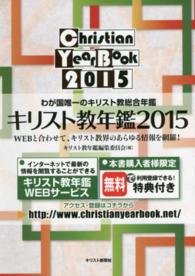出版社内容情報
究極の情報整理は情報遮断。アウトプットに集中しイノベーションを生む!名著『スパークする思考』(角川書店)を復刊!
内容説明
情報は放っておいて熟成させよ!インプットの労力を最小化し、アウトプットを最大化する、ムダな努力いらずの発想法。
目次
第1章 問題意識がスパークを生む(スパークとは;「異業種競争戦略」のきっかけはテレビ ほか)
第2章 アナログ発想で情報を集める(情報は整理するな、覚えるな;自分だけの情報にこそ、価値がある ほか)
第3章 情報は放っておいて熟成させる(20の引き出し;時代による引き出しの変遷 ほか)
第4章 アイデアを生み育てるアナログ思考(なぜアナログがデジタルに勝るのか;キャプテンの唇 ほか)
第5章 創造力を高める右脳発想(右脳と左脳の連鎖がアイデアを生む;スパークを生むメカニズム ほか)
著者等紹介
内田和成[ウチダカズナリ]
早稲田大学ビジネススクール教授。東京大学工学部卒業。慶應義塾大学経営学修士(MBA)。日本航空を経て、1985年ボストンコンサルティンググループ(BCG)入社。2000年6月から2004年12月までBCG日本代表、2009年12月までシニア・アドバイザーを務める。2006年より早稲田大学教授。ビジネススクールで競争戦略論やリーダーシップ論を教えるほか、エグゼクティブ・プログラムでの講義や企業のリーダーシップ・トレーニングも行なう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
速読おやじ
21
巻末の楠木健教授の解説がこの本の要約になっている。情報は整理するな、覚えるな、無理に集めるな、脳にレ点を打つ、時が情報を熟成させるのだ。自分にピンと来た情報に脳内にインデックスをつけるのだが、著者は自分の脳に20くらい引き出しがあるのだそうだ。何でもかんでも情報を入れるとパンクしてしまう。情報整理とは情報遮断なのだと、楠木教授は言う。脳内にある引き出し以外の情報は遮断!無駄な情報あるもんなあ。放っておくと、洪水の様に情報が溢れる時代なので、遮断する!というのは大切なことなんだろうな。2021/04/17
hk
21
…「外部情報は小見出しをつけて脳の中でジャンル分けせよ。これが情報を知識へと整頓する一里塚。なぜなら同じ小見出しが付与された情報群内部で化学反応を起こし、閃きのきっかけとなるからだ。この外部情報整理の際に、複数の小見出しをつけるとより効果的。そうすれば1つの情報が接着剤となり、別ジャンルの情報群どうしの類推が可能になる。ここからアナロジーによる閃きが起こり、仮説が生まれることがままあるからだ」…といった具合に「スパーク」が起こるプロセスの解説が趣旨。最近流行りの「類似推論系書籍」草分けの一冊ですわな。2020/01/27
しんこい
14
関心あるところにインデックスをつける、おおざっぱな分類の引き出しにとりあえず入れておく、決して記録も整理もしない、とかまさに自分のやりたいことだ。それをビジネスでなく日常の延長でというあたりが実践できていないな。2019/12/27
アルカリオン
11
p100「チェスの盤面を見て記憶した後に再現する」という実験を多人数で行ったところ、"実際のチェス勝負の一場面"を課題にした場合はチェスの実力と再現度合いが比例傾向にあった。一方、"実際の局面では生じ得ないようなランダムな配置"を課題にした場合、上級者の再現度合いは素人よりもむしろ低かった▼素人にとってはどちらの課題も難易度に差はない。上級者にとっては前者は記憶のカギとなる情報が多く埋め込まれているので再現しやすいが、後者では知識・常識が邪魔をして混乱してしまい、素人以下の再現度となったのだ。KU2024/11/02
チャー
8
アイデアや閃きについて著者の視点から有用性とその扱い方を述べている。仕事が来てから考えるとロクなものができないという点は、普段から様々な事に疑問、問題意識を持ち、考えることの大切さを再認識。優れたアイデアは妄想とほとんど区別がつかないという点はなるほどと思う。情報の豊かさは注意の貧困を作るという見方は、情報多寡の時代の弊害を共感した。成功(従来)の固定観念からなかなか脱却できないところは自分にも思い当たるところがあり、立ち止まるきっかけになる。行き詰まったら俯瞰するという方法を今後試してみたい。2020/01/13
-
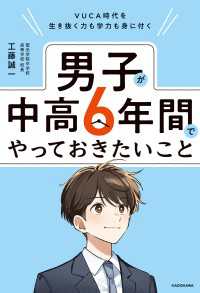
- 電子書籍
- VUCA時代を生き抜く力も学力も身に付…