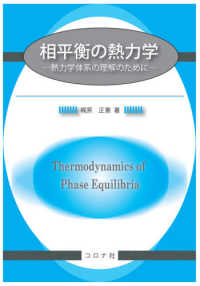内容説明
直観、仮説、物語、綜合―五感を総動員してコト/経験をデザインする技法。エスノグラフィー、ビジネスモデル、シナリオ・プランニング。イノベーションを生む「知のしかけ」を設計するための画期的手引書。
目次
1 知のデザインの世紀(知識デザインとデザイン思考;産業社会の知となったデザイン;イノベーションを生むデザイン・マインド)
2 デザイン経営の知的方法論(コンセプトをデザインする―質的データのデザインの方法論;ビジネスモデルをデザインする―関係性のデザインの方法論;シナリオをデザインする―時間・空間のデザインの方法論)
著者等紹介
紺野登[コンノノボル]
KIRO(知識イノベーション研究所)代表、多摩大学大学院教授、同知識リーダーシップ綜合研究所(IKLS)教授。京都工芸繊維大学新世代オフィス研究センター特任教授、同志社大学ITEC客員フェロー、東京大学i‐schoolエグゼクティブ・フェロー。2004‐10年グッドデザイン大賞審査員。早稲田大学理工学部建築学科卒業。博士(経営情報学)。知識産業の事業開発、PSF組織戦略、リーダーシップ・プログラム、ワークプレイス戦略等の領域で知識経営とデザイン・マネジメントの研究と実践を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
naobana2
7
さすが、図がたくさんあって読みやすい(笑) ところどころ日本のものづくりのよくないところが書かれていたり。 シナリオプランニングの必要性や、フューチャーセンターについても書かれていた。 難しいけど、徐々に理解します。。2014/01/26
mattu
6
part2からが本題ですね。差し込まれている図が読みにくくしているのが残念。。。2015/10/31
coppe
2
内容に比べ解りやすさの工夫がおいついておらずもったいない印象。「モノのデザインからコトのデザインへ考え方を変える」のではなく、「コトのなかにモノ・技術を埋め込む」という考え方を強調する。フレームワークの適用と論理的思考からはイノベーションを生み出せないため、アブダクション(直感的推論)を用いる。そのために現場に入って人間中心で問題や社会的ギャップ(兆候)を観察し、仮説を立ててプロトタイプを作ってフィードバックを繰り返す。2018/05/14
あっと
2
環境が変化し続けている環境ではモノを分析・管理する手法では上手く立ち回る事ができない。そこでは企業・個人が様々なモノとの関係性を意識し、デザインする必要がある。ハード、ソフト、システム・サービスとの三位一体を生み出して顧客価値を生み出すためのプロセスとしてデザイン思考は有効である。「デザインとはどういうものなのか?」から始まり、多くの事例や幅広い学問から得られる知見を通してデザイン思考の有効性を説明してくれる。そのためやや難解に思える部分もあるが、非常に面白い良書。2011/04/05
はしも
1
いかに90年代までと現在とでビジネスのあり方が変わっているかがよく分かる。やや抽象的な内容だったが、人文学的な知のあり方を活かすヒントが見つかった気がする。2020/07/15