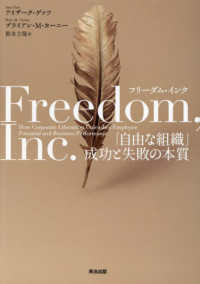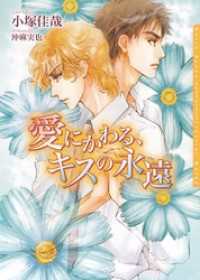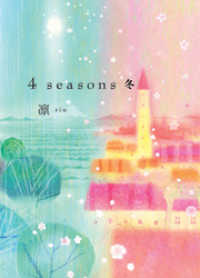出版社内容情報
2050年、日本の経済成長率は4.5%に達し米国と並ぶ二大超大国となる。米国で話題となった衝撃の「新・日本論」。2050年、ある米国人が久方ぶりに羽田に降りたつと、日本は見違えるほど活力のある国になっていた。バブルの崩壊以降、長らく低迷から立ち直れなかったこの国が、たった35年でどのように復活を遂げたのか? そんな仮想の設定に基づき、2015年以降の日本の歩みを“近未来シミュレーション”として創作。こうすれば日本が経済復興を遂げ、人口減少を食い止め、地政学的により大きな役割を担う大国になれると処方箋を提言した一冊。日本の復活が単に日本のためだけではなく、米国をはじめとする世界全体にとっていかに重要なものかについても説明した、全米知日派の間で話題の書。
【主な内容】
●2017年、中国による「尖閣占領」危機
●米軍撤退。日米同盟から集団安全保障体制へ
●有力企業を外資が買収。日本株式会社は完全崩壊
●移民受入れと出生率回復で総人口は1億4000万人に
●英語公用化で日本の国際競争力は急上昇する
●2050年、日本の成長率は4.5%に達し米国と並ぶ大国へ
はじめに??二つのブックエンド
第1章 2050年 東京
第2章 2017年 危機
第3章 パックス・パシフィカ??太平洋の平和
第4章 女性が日本を救う
第5章 バイリンガル国家、日本
第6章 イノベーション立国
第7章 エネルギー独立国
第8章 日本株式会社から日本型「ミッテルシュタンド」へ
第9章 「インサイダー」社会の終焉
第10章 民尊官卑の国へ
結び??アメリカと世界にとって日本が重要である理由
謝辞
クライド・プレストウィッツ[クライド プレストウィッツ]
クライド・プレストウィッツ
1941年米国デラウェア州生まれ。スワスモア大学卒業、ハワイ大学東西センターで修士課程(極東アジア地域・経済学専攻)修了、ペンシルベニア大学ウォートン校で経営修士課程修了。その間、慶應義塾大学にも留学。初めて来日したのは1965年、それ以降1970年代にも再度外資系企業役員として日本に滞在する。国務省勤務、民間企業勤務などを経て、1981年商務省に入り、86年までの間、レーガン政権で商務長官特別補佐官などを務め、自動車や半導体などの日米貿易交渉をはじめ中国、ラテンアメリカ、ヨーロッパ諸国との数々の貿易交渉にあたる。現在、経済戦略研究所(Economic Strategy Institute)所長。太平洋経済委員会の副議長や、上院議員時代のヒラリー・クリントン氏の貿易・通商アドバイザーも務めた実績がある。日米貿易摩擦時に辣腕対日交渉担当官として鳴らし、テレビ・新聞・雑誌などで日本に多数の提言を行っている。著書にベストセラー『日米逆転』(ダイヤモンド社)、『ならずもの国家アメリカ』(講談社)、『東西逆転』(日本放送出版協会)などがある。
村上 博美[ムラカミ ヒロミ]
村上 博美(ムラカミ ヒロミ)
ワシントンDC経済戦略研究所(Economic Strategy Institute)シニア・フェロー、米国戦略国際問題研究所(CSIS)グローバルヘルス・ポリシーセンター兼任フェロー、日本医療政策機構理事。2015年からJapan Institute for Social Innovation and Entrepreneurship (JSIE)パートナー。米国ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)や政策研究大学院大学にて講義や政策分析プロジェクトを担当。専門は産業政策、イノベーション政策、国際保健政策。上智大学理工学部卒業。St. Mary’s大学国際経営学修士、米国ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)国際関係論博士。
小野 智子[オノ トモコ]
小野 智子(オノ トモコ)
日本女子大学家政学部住居学科卒。設計事務所勤務ののち、渡米。独・英を経て帰国後、理工系英文学術誌編集、翻訳会社勤務を経て翻訳者の道へ。共訳書に、ノーベル平和賞受賞者バーナード・ラウンの『生存のための処方箋』(第20回IPPNW世界大会実行委員会)をはじめとして、ナショナル ジオグラフィック協会『最高の休日 世界の美しい都市』、ダニエル・スミス『絶対に行けない世界の非公開区域99』『絶対に見られない世界の秘宝99』『絶対に明かされない世界の未解決ファイル99』(日経ナショナル ジオグラフィック社)などがある。ノンフィクションを中心に仕事の幅を広げている。
内容説明
ニッポンは三度目の復活を遂げる!米国発、衝撃の問題作。日米両超大国時代の到来を予見!知日派論客による「新・日本論」
目次
第1章 2050年東京
第2章 2017年危機
第3章 パックス・パシフィカ―太平洋の平和
第4章 女性が日本を救う
第5章 バイリンガル国家、日本
第6章 イノベーション立国
第7章 エネルギー独立国
第8章 日本株式会社から日本型「ミッテルシュタンド」へ
第9章 「インサイダー」社会の終焉
第10章 民尊官卑の国へ
著者等紹介
プレストウィッツ,クライド[プレストウィッツ,クライド] [Prestowitz,Clyde]
1941年米国デラウェア州生まれ。スワスモア大学卒業、ハワイ大学東西センターで修士課程(極東アジア地域・経済学専攻)修了、ペンシルベニア大学ウォートン校で経営修士課程修了。その間、慶應義塾大学にも留学。初めて来日したのは1965年、それ以降1970年代にも再度外資渓企業役員として日本に滞在する。国務省勤務、民間企業勤務などを経て、1981年商務省に入り、86年までの間、レーガン政権で商務長官特別補佐官などを務め、自動車や半導体などの日米貿易交渉をはじめ中国、ラテンアメリカ、ヨーロッパ諸国との数々の貿易交渉にあたる。現在、経済戦略研究所(Economic Strategy Institute)所長
村上博美[ムラカミヒロミ]
ワシントンDC経済戦略研究所(Economic Strategy Institute)シニア・フェロー、米国戦略国際問題研究所(CSIS)グローバルヘルス・ポリシーセンター兼任フェロー、日本医療政策機構理事。2015年からJapan Institute for Social Innovation and Entrepreneurship(JSIE)パートナー。米国ジョンズ・ホプキンス大学院大学にて講義や政策分析プロジェクトを担当
小野智子[オノトモコ]
日本女子大学家政学部住居学科卒。設計事務所勤務ののち、渡米。独・英を経て帰国後、理工系英文学術誌編集、翻訳会社勤務を経て翻訳者の道へ。ノンフィクションを中心に仕事の幅を広げている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
たんかれ~
おおたん
GASHOW
澄