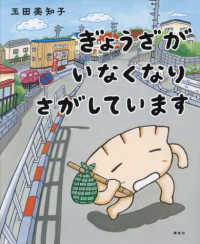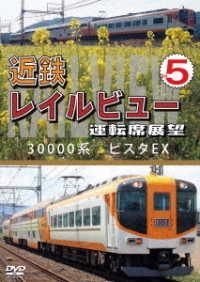出版社内容情報
同情や善悪論から脱し経済学の冷静な視点から障害者の本当の幸せや雇用・教育のあり方を考える。日経・経済図書文化賞受賞書の新版。障害者を作っているのは私たち自身である
制度の問題点を経済学で一刀両断にする
障害者本人のニーズに合わない障害者福祉制度でいいのか?
選りすぐりの生徒だけ受けられる職業訓練、
補助金目当てで仕事をさせない障害者就労施設、
障害者雇用を肩代わりするビジネス……。
脳性麻痺の子どもを持つ気鋭の経済学者が、経済学の冷静な視点から、
障害者を含めたすべての人が生きやすい社会のあり方を提言
障害者だからと特別視して終わるのではなく、一般化した上で深く考えれば問題の本質が見えてくる。私たちに必要なのは、障害者に映し出されている社会の姿に気づくことである。これは障害者に学ぶといってもいいだろう。(終章より)
はしがき
序章 なぜ「障害者の経済学」なのか
第1章 障害者問題の根底にあるもの
第2章 障害者のいる家族
第3章 障害児教育を考える
第4章 「障害者差別解消法」で何が変わるのか
第5章 障害者施設のガバナンス
第6章 障害者就労から学ぶ「働き方改革」
終章 障害者は社会を写す鏡
あとがき
中島 隆信[ナカジマ タカノブ]
著・文・その他
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
カレー好き
32
障害者にまつわる社会のカラクリ。日本とは違う外国の障害者への環境の違いなど、コラムが面白い。ちょっと昔の東横インや乙武さんの銀座のレストラン騒動の見解も面白い。障害者雇用率を高めるため必死になる大企業と、そのしわ寄せを食らう中小企業。障害者本人たちの働きがいなど、置いてけぼりにされていないか?知的障害はできることの範疇が様々だから、その本人に見合う仕事が社会に貢献できて、何よりも本人が元気に仕事を続けられる環境を提供する社会になってほしい。☆4つ2018/11/09
なるみ(旧Narumi)
22
多面的に述べられていて、学ぶことの多い一冊でした。2021/02/13
Natsuko
14
著者は脳性まひの息子を持つ経済学者。障害福祉を、時に私たちが心に抱きながらも口に出すのは憚るようなワードを使って、客観的に切っている。タイトルのような障害者と経済とは、考えること自体がタブーの風潮があるが違う。お金をいただいて施設を利用していただき、国からも補助金をいただき、給料をもらって生活している。私自身も、仕事として職業としてそして経済活動の一環として組織で活動していることを常に頭に置く意識は必要だと感じた一冊。2019/09/12
naohumi
8
前作から12年。障害者の数、制度、取り巻く環境は大きな変遷があった。そういった流れを受けて、世の中の障害者についてを経済的な視点から分析、課題や提案についてを客観的且つ合理的に考えられている。 そこには、守るべき弱者ではなく、経済活動の一旦を担う障害者観があり、感情を挟み込む余地がない感想を持った。よい悪いは別にして、世の中を俯瞰して見る当たり前の考え方なのかもしれない。そんな気づきが得られた事は収穫だった。タイトルは障害者の経済学であったが、障害者を起点に世の中を深堀する内容。2019/07/14
貧家ピー
7
経済学者の著者が、経済学の視点で障害者をめぐる問題を、経済学の視点からとらえ直した本の改訂版。機能不全があっても社会が問題視しなければ障害者にはならない。障害の原因は機能不全ではなく社会の方にあるという考え方が障害の社会モデル。原則として人間が持っているはずの機能について一定の基準を満たさない時に障害と定義づけるのが医学モデル。医学モデルに基づく福祉の考え方は障害者と言う特別枠をあらかじめ設定し、そこに収まった人を支援の対象とすることが、社会モデルが広がらない原因という見方が興味深かった。2024/10/21
-

- 電子書籍
- 素直になれない雪乙女は眠れる竜騎士に甘…