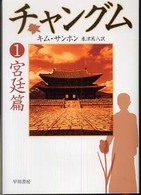内容説明
ニート対策の現場のプロが書いた若者たちの真実。
目次
第1章 「ニートは働く意欲のない若者」論の誤解(ニートとは誰か;誰でもニートになりうる ほか)
第2章 ニートとその親たち(同級生たちの「受験パパ」化;子育ての変質と受験競争 ほか)
第3章 ニートが生まれる時代(人生や仕事に希望がないからニートになる;ニートには自分が拠って立つ人間関係が必要 ほか)
第4章 どうニートと向き合うか(親と子を引き離すのが出発展;ニートはきっかけを待っている ほか)
第5章 ニートという希望(効率至上主義とスローワーク;新パラサイト主義のすすめ ほか)
著者等紹介
二神能基[フタガミノウキ]
1943年、韓国大田市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。学習塾、幼稚園経営のあと、世界各地の教育プロジェクトに参画。早稲田大学講師、文部科学省、千葉県などの各種委員を歴任。現在、NPO法人「ニュースタート事務局」代表。1993年から目的を喪失した若者をイタリアのトスカーナ地方の共同農園に預け、農作業を通じて元気を取り戻そうというプロジェクトを手がける。その後、千葉県で引きこもりや不登校、ニートの若者たちの再出発を支援するNPO法人「ニュースタート事務局」を設立。現在は、「世の中をよくする仕事、生きることが楽しくなる働き方を創り出そう」と、世界88カ所に「雑居福祉村」をつくる活動に邁進している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
lily
5
ニートの概論をさらっと解説している。マイペースさが介護職に向くとか、お遍路が自分探しに役立つということをNPOを通じて支援をしている代表の話。実際に行動する姿には頭が下がるが、内容にもう少し深みがほしかった。「あらゆる子育ての結果は偶然にすぎない。」という言葉が印象的。気楽に考えることが一番大切だということは理解できた。2015/06/24
貧家ピー
2
著者は、NPO法人ニュースタート事務局代表。 旅行の添乗員をやっている派遣社員やIT会社でシステムエンジニアとして働いている男の子も、自分の役割を果たせていることが嬉しいと言っている。承認欲求。 「木を植うるは、10年の計なり、徳を植うるは100年の計なり」2006/01/17
わたし
2
この本は実際に悩む親御さんには読んでほしくない。読んでも何も解決はしないだろう。何故なら作者の経営する寮に入れてお金を払う事しか書かれていないからだ。問題定義もされていたものの、解決の糸口は見えず投げっぱなしに感じる。寮生活で家族と完全に切り離される場合のデメリットには全く触れず、全体を通して耳触りの良く上辺の澄んでいる所だけを飲まされているような気がして気持ち悪かった。巻末の雑居福祉村を検索してみたが2004年前後の記事しか見当たらないのも残念でならない。正直時間の無駄とも思える本であった。2013/04/17
がっち
2
社会現象でもあるニートについて書かれた本。ニート分類として、①就労についての情報がない情報力必要型②人間関係が苦手な社会力必要型③生きがいを感じられない人間力必要型に分類されるそうであり、ニートになってしまうのはその個人がかならずしも悪いわけではなく、家庭環境、社会環境がそれを生み出していると述べている。教育論的にも良書であり、この人のやっている事業はすごいなと感じた。B2010/10/29
カナセ
1
図書館で流し読み。内容は結構きれいで、綺麗事のような印象かな。ニートの分類に関しては一般的かなー…と。いや、ほら、私みたいなのいるので(国家試験浪人=無職なので。)まぁ、定義からは外れますが、実際予備校行ってないので、他人からみたらニートみたいなもの。例に上がったのがニート歴というか、引きこもり歴だったのが少しだけ残念。引きこもりの人は、外からの刺激を少しずつ取り入れることが大切。あと、親の依存。ということなんだろうけど、ニートよりも引きこもりの人向けの本なのでは…といった感じでした。2015/05/09
-

- 電子書籍
- 魔女の婚姻【分冊版】 5 FLOS C…