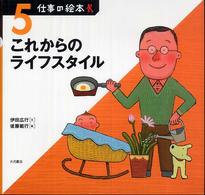出版社内容情報
2013年参院選目前、「ネット選挙」解禁を、新進気鋭の研究者が解説。日本における、その影響力と起こりうる変化を明らかにする!
2013年参院選から解禁されることとなった「ネット選挙」。
しかし、そもそもネット選挙とは何なのか? その解禁によって、巷間言われるように「お金がなくても政治家になれる」、「ネットで見た候補者の発信に触発されて、若者が選挙に行くようになる」というのは本当か? 「この情報化社会にインターネットの使用を禁止するなんて、時代遅れもいいところだ!」という主張は正しいのか? テクニカルな側面だけを見ていても、本質には辿り着けない。ネット選挙を丁寧に一歩踏み込んで考察すれば、これらの主張が幻想に過ぎないことは明らかだ。
しかしそれなら、ツイッター議員はなぜツイッター議員であろうとするのか? なぜ全国紙がソーシャルメディア分析に取り組むのか? 解禁による静かな変化が、候補者・有権者・マスメディア・ネットメディアに及ぼす影響はどのようなもので、そこから日本はどう変わっていくのだろうか? インターネットの設計思想を政治に受け入れることで、日本社会が変わる!?
――ツイッターやフェイスブック、私たちが何気なく利用するソーシャルメディア上で、政治家の個人アカウントを目にする機会が増えてきました。ところが、公職選挙法に定められた選挙運動期間に入ると、新しいツイートも政治家個人のブログ更新もぱったりと止まっていたのが、2012年末の衆院選までのこと(一部例外もあり)。それはなぜだったのでしょうか? その答えからわかるのは、公職選挙法が実現しようとした選挙戦環境のありよう、そしてその基となる理念です。
一般市民による選挙関連のツイートやYouTubeへの動画投稿も、場合によっては合法とはいえなかった、という意外な事実に驚かされます。日常の中でほとんど意識することのない法律ですが、公職選挙法はそもそも何を実現しようとしたものだったのか? 改正によって何が可能になり、その影響は日本社会、私たち個人にどう及ぶのか? まさに、「制度だけでなく、これは思想の問題だ!」
序章:ネット選挙とは何か?
1.政治がインターネットに近づこうとした日
2.ネット選挙が意味すること―インターネット投票はできません
3.選挙で利用できる「文書図画」
1章:間違いだらけのネット選挙論
1.なぜ政治家は選挙運動が始まった途端にオフラインになったのか?
2.ネット選挙の禁止は「時代遅れ」か? その解禁は「時代の必然」か?
3.ネット選挙にはお金がかからない?
4.ネット選挙で日本の政治環境が変わる?
5.やってみないとわからないのだから、やるべき?
6.ネット選挙の本質はなにか?
2章:ネット選挙解禁の土壌、日本の事情
1.情報化日本のインターネット・SNS
2.インターネットの設計思想―漸進的改良主義と反権威の系譜
3章:2012年までの日本のネット選挙の歴史
1.1990年代のネット選挙問題
2.2000年代に高まった、野党主導の解禁の機運
3.ネット選挙解禁を望む民間の動き
4.民主党政権下で、ついに与野党合意に至る
4章:2012年衆院選から2013年の動向
1.「雄弁でありたい政治家」たちの攻防戦
2.ソーシャルメディアと「雄弁な有権者」
3.マスコミも注視する“情報と政治”
4.ソーシャルリスニングとインフォグラフィクスの登場
5.与党自民党が主導した2013年のネット選挙解禁
5章:ネット選挙を考えるためのヒント
1.海外のネット選挙事情―アメリカ・韓国のケース
2.変化仮説と正常化仮説
6章:日本の議員たちとソーシャルメディア―「ツイッター議員」の登場
1.なぜ数あるソーシャルメディアのなかでツイッターなのか?
2.「ツイッター議員」を分析する
3.ツイッターの技術特性は、ほとんど引き出されていない
4.なぜ、日本の政治化たちはツイッターを“有効活用”しないのか
7章:ネット選挙解禁がもたらす変化
1.候補者と政党―“先進的なネット選挙に取り組む政治家”という称号の魅力
2.有権者
3.ネットメディア
4.マスメディア
終章:ネット選挙が日本の民主主義をよくするには?
1.デジタル・デモクラシー再考
2.オープンガバメントの手段としてのネット選挙
3.出発点としてのネット選挙解禁
4.技術論に終始するネット選挙の議論を超えて
【著者紹介】
西田 亮介(ニシダ リョウスケ)
立命館大学特別招聘准教授
立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘准教授(有期)。
1983年京都生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。
同助教(有期・研究奨励?U)、(独)中小機構経営支援情報センターリサーチャー、東洋大学・学習院大学・デジタルハリウッド大学大学院非常勤講師等を経て現職。
共編著に『「統治」を創造する』(春秋社)、共著分担執筆に『大震災後の社会学』(講談社)、『グローバリゼーションと都市変容』(世界思想社)他。
専門は情報社会論と公共政策学。情報と政治、ソーシャルビジネス、協働推進、地域産業振興等。
内容説明
「均質な公平性」「漸進的改良主義」日本はどちらを選ぶのか。気鋭の社会学者、緊急書き下ろし。
目次
序章 「ネット選挙」とは何か?
第1章 間違いだらけのネット選挙論
第2章 ネット選挙解禁の土壌、日本の事情
第3章 2012年までの日本のネット選挙の歴史
第4章 2012年衆院選から2013年の動向
第5章 ネット選挙を考えるためのヒント
第6章 日本の議員たちとソーシャルメディア―「ツイッター議員」の登場
第7章 ネット選挙解禁がもたらす変化―候補者・有権者・ネットメディア・マスメディア
終章 ネット選挙が日本の民主主義をよくするには?
著者等紹介
西田亮介[ニシダリョウスケ]
立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘准教授(有期)。1983年京都生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。同助教(有期・研究奨励2)、(独)中小機構経営支援情報センターリサーチャー、東洋大学・学習院大学・デジタルハリウッド大学大学院非常勤講師等を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
そり
おおかみ
ミズグ
takizawa
-
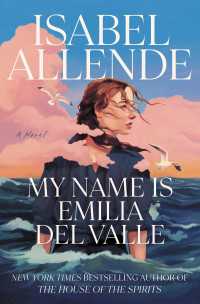
- 洋書電子書籍
- My Name Is Emilia d…